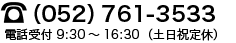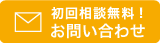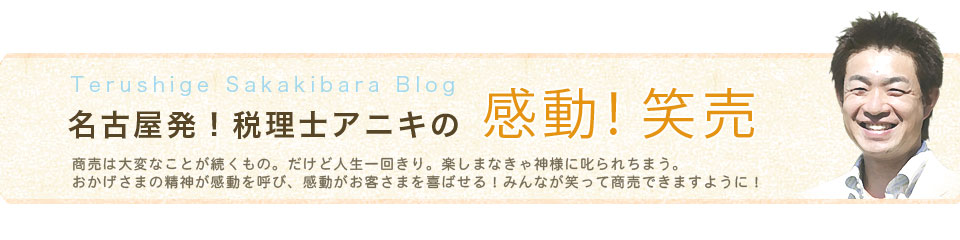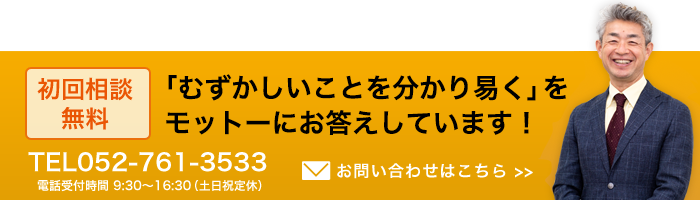2025年7月10日
源泉徴収税のポイント
毎月10日は源泉徴収の納期限です。
7月10日は小規模の会社で特例納付を選択している事業者の納期限でもあります。
源泉所得税の対象について注意すること
源泉所得税は、徴収した日の属する月の翌月10日までに、税務署に支払います。
ここで徴収した日とは、源泉徴収の対象となる支払いを行った日です。
例えば、お給料なら5月末日で締めたものを6月15日に支払ったとします。
すると徴収した日は6月15日となるため、
天引きされた5月分の税金は7月10日までに支払うこととなります。
また、源泉徴収するのは給料だけではありません。
賞与や退職金、その他に士業の報酬や原稿料、デザイン料や翻訳料の報酬なども対象となります。
何が対象になるかは、国税庁のHPに限定列挙で挙げられていますので、
一度ご確認いただくとよいと思います。
納期の特例と納付方法
納期の特例とは、毎月10日に納付するべき源泉所得税を、
年に2回、6か月分をまとめて納付できる制度です。
利用できるのは、給与の支給人員が常に10人未満の源泉徴収義務者です。
「常に」とあるので臨時的に超える場合は含みません。
要件は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署に提出することです。
納める金額は、給与なら税務署から送付される「源泉徴収税額表」から算定します。
その他の報酬は100万円以下なら10.21%、
100万円を超える分には20.42%と決まっています。
(ただし司法書士などへの支払いは100万円を超えても10.21%もありますので要確認)
間違いをしやすいのは納付の時期で、
給与以外の個人へ支払った報酬は、納期の特例を選択していても、原則通り支払った翌月に源泉税を支払わなければなりません。
退職金と士業への報酬だけが半年まとめて納付となります。
うっかり失念すると追徴ばかりか罰金も請求されます。
給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合は、
速やかに「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してくださいね。
退職金を支払うと
退職金は、給与や賞与と違い、所得税法上、退職所得と言って分離課税で計算し、確定申告が必要となります。
しかし「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出すれば、
源泉徴収だけで課税関係が終了し、確定申告は必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」は税務署長に提出とありますが、実務上は会社が保管します。
住民税だって源泉徴収
住民税も源泉徴収で納めるのが原則です。
少し前までは「普通徴収」と言って(普通が例外なんです!)個人で支払うことができましたが、
最近はお役所からの指導で、給与天引きが徹底指導されています。
住民税は年末調整に基づいて翌年5月ごろに金額が確定し、雇用主に通知されます。
新入社員は2年目の方が、手取り額が低くなるのはこのためです。
大きな税務署では、源泉徴収部門が存在します。
源泉徴収の誤りを調べるために調査も行われます。
ルーチンでうっかりがないように、日ごろから気をつけておきたいですね。
そういう時は税理士に確認してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!