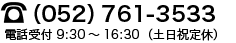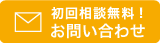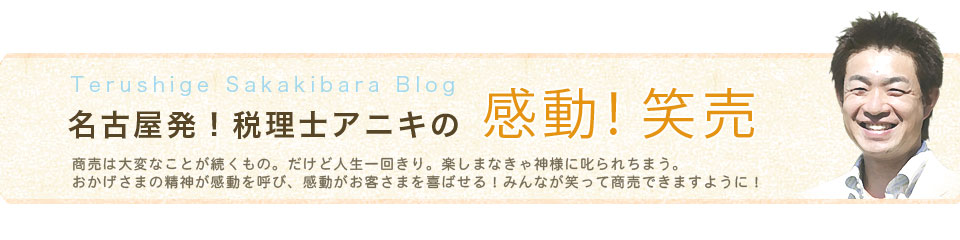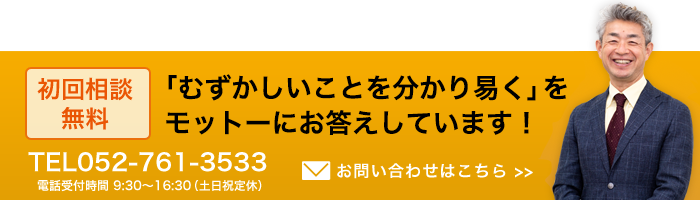2018年4月2日
毎日の振り返り、してますか
4月、新年度になりました。
皆さんのなかには、日記や日誌をつけていらっしゃる人も多いことでしょう。
では、なぜ日誌をつけるのか、
日誌をつけるといいことがあるのか、
考えたことはありますか。
あの球団では、新人から指導しています
プロ野球のある球団では、新人選手にはユニークな指導を行っています。
新人選手に日誌をつけることを習慣としてさせているのです。
ドラフトでは、継続的に日誌を付けられることをできそうな選手しかとらない、とも聞いたことがあります。
今年からメジャーリーグに移籍した、元日本ハムファイターズの大谷翔平選手はその一人です。
大谷選手は実は花巻東高校時代から目標シートを作り、毎日振り返りの日誌をつけていたそうです。
そして日本ハムファイターズへ入団。
くだんの球団はこちらで、ユニークな指導で有名な球団ですね。
高校時代からの習慣がプロに入ってからも継続し、その後の活躍はご存知の通り。
もちろん才能があるのは言うに及ばずですが、
すごい素質を持ってプロ野球選手に入ったとしても、
結局、鳴かず飛ばずで終わる選手が多いですから、大したものです。
振り返る習慣が大切
日誌に書くことは、その日の振り返り。
振り返ることで、自分を客観的に認識し
明日への課題を見つけ、
カイゼンしていくことが可能になるのです。
後から見返して、目で見て確認できることが大切なんですね。
実はウチの事務所でも、シャインズの皆さんや私自身も実践しています。
ここに紹介しますね。
① 今日できたこと
今日一日で、できたことを書いていきます。
できたことを書くというのは「自己肯定感」を高める作用があります。
② 今日もらった「ありがとう」
感謝をもらうと嬉しいですね。やる気につながります。
ありがとうを探すと「自己効力感」が高まり、人の役に立っていることが自覚できます。
やってみると分かりますが、意外と見つけられないものですよ。
③ もう一度やり直すとしたら
とはいえ、うまくいかないこともあるのが普通です。
できなかったこと、うまくいかなかったことを思い出すのは嫌ですが、
反省とカイゼンのアプローチを、「もう一度やり直すとしたら」で考えるのです。
具体的なイメージを伴わせるのです。
自分の脳に失敗ではなく、成功を上書きさせることで、次に活かすようにするのです
人間の記憶はあっという間に忘却の彼方へ。
だからこそ、毎日の振り返りが大切になってきます。
継続は力なり。
いずれその成果は大きな差になって表れてくるのだと思います。
人育てやも子育ても一緒ですね。
地道に、繰り返すこと。
劇的に効く薬はありません。
毎日の習慣が成長となるのだと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年3月23日
医療費控除の申告現場から思うこと
確定申告が終わりました。
お客様にも、
スタッフであるシャインズの皆さんにも
助けられ、無事過ごすことができました。
感謝です。
ありがとうございます!!
税理士会主催の無料相談
確定申告時期には、
税理士会の会務で「無料相談」が区役所で行われます。
これは正しい納税を推進すると同時に、税理士会の公益性から地域の方へのボランティアという意味もあります。
ですからお越しになる方の多くはお年寄りで、
年金を受け取っているような方がほとんどなんですね。
医療費控除の変更
さて、今回の申告から変更になった点で「医療費控除」があります。
医療費控除はたくさん医療費がかかった方は大変なので、税金をおまけしてあげるという趣旨のものです。
だから「私はこんなにも医療費がかかりました~」と申告すれば税金がまかります。
医療費控除の意外と知らないシリーズ。
- 自由診療でも医療費控除が受けられる
- 家族分をまとめて計算できる
- 未払いは計算対象にならない
- 保険などで補助が受けられる、受けられそうなものは金額から差し引く
- 歯列矯正など高額でも受けられる
全部がイエスです。
それで今回の変更は何かというと
薬局でのお薬を購入が対象になるセルフメディケーション税制と
申告に使う用紙が変わって領収書を提出しなくてもよい
ことになったのです。
領収書を提出しなくてもよい、これは申告する方にとっても税務署にとってもメリットはあると思います。
確かに税務署の方も大量の領収書をチェックするのも、保管する場所も大変だわ!と思います。
ただ領収書を添付しなくてもいいのは、今回から新しくなった用紙を使って申告した場合のみ。そして、
その用紙を使わないと医療費控除が受けられない!!
ということなのです。
問題なのは、申告に来たお年寄りたちのほとんどが、それを知らなかった!!ということです。
そりゃ確かに様式に沿って書かないといかんと思うけどさ…。
税金の思想は弱者保護ですぞ
さすがに国税庁も鬼ではありません(苦笑)。
向こう3年間は今まで通り、領収書を提出すれば医療費控除は受けられるそうです。
言い換えれば3年後からはきちんと様式通り書かないと、
たとえ領収書を出したからといって医療費控除は受けさせませんぞ、
となったのです。
いや、弱者保護の思想からすると、ちょっと優しくない!
そりゃあ、納税は国民の義務であるけれど。
「お上」のやり方っぽくないですか?
『もうちょっと税金を納めている国民の皆さんに寄り添ってほしいな~』
とお年寄りの申告を手伝っているときに思いました。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年3月2日
事業をするうえで中心にするものは。
起業しようとしている皆さん、
いえ、すでに事業をおこして継続している方にも、問いたいと思います。
事業をするうえで、中心にするものは何でしょうか?
自分の「あり方」をきめること
事業をおこして、継続する。
とても難しくもあり、やりがいもあることです。
大切なことはたくさんあると思います。
商品。
スキル。
人脈。
マーケティング。
志。
私は「あり方」だと思います。
事業をしていくと、その「あり方」を見失いがちになります。
ともすると「何をするか」に注力してしまうのです。
営業。
商材の開発。
人材育成。
HPの作成。
SNSを使っての発信。
全部が必要なことでしょう。
何をするかは、Ⅾoing.
一方、
あり方は、Being.
そう、「どうありたいか」を追求することです。
自分を突き詰めていく、それが極めること
何をするかにとらわれると、周りに目が行きます。
他との比較に喜んだり、落ち込んだり。
悩みが尽きません。
しかし自分だけに注力します。
自分はどうありたいか。
提供したいものはどうありたいか。
お客様を喜ばせるあり方は。
その問いを繰り返し、深堀していきます。
あるのは、きっと
ぶれない自分
only one.
あなただけの「あり方」なんでしょう。
ぜひ言葉でお伝えしてください。
きっと、周りの人の心が動くはずです。
私は、いつもお客様から「あり方」を聞いて、
感動しています。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年2月15日
保険金の受取りは思わぬ課税があるので要注意
さて、確定申告が始まりました。
税理士事務所も本格的な繁忙期が始まります。
保険金の課税関係は大丈夫?
保険金を受け取ると税金がかかります。
この時期、確定申告で取り扱うのは「贈与税」と「所得税」になります。
皆さんが入っている保険はどの税金がかかるのかご存知でしょうか?
うっかり税金がかかってきた、なんてことがないようにしたいですね。
税金を判断するために知っておくこと
保険金の課税を整理していきましょう。
まずは「契約者」「被保険者」「受取人」この3つを理解してくださいね。
契約者…生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人
被保険者…その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人
受取人…保険金を受け取る人
そして保険にまつわる税金は3つです。
そして税金が安い(負担が少ない)順に
相続税<所得税<贈与税
となります。
ちなみに、所得税では契約内容によっては雑所得として計算する場合(年金保険)と、
一時所得として計算する場合(満期保険金)があります。
かかってくる税金を判断するポイントは
契約者と被保険者が同一か
契約者と受取人は同一か
となります。
あなたが入っている保険はどのタイプ?
具体的に見ていきましょう。
契約者と被保険者が同じケースとしては、父が死亡保険に入って保険料を支払っておき、自分が死んだら家族に保険金がおりる、ものです。これは相続税がかかります。
また契約者と被保険者が同じケースでも、保険料を定期で支払い、満期の時期が来たら保険金がおりる、ものがあります。
これは贈与税か所得税がかかります。
この場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の一時所得で計算します。
一方、契約者と受取人が別人であれば、受け取った人に贈与税がかかるのです。
贈与税は税率が高いので、受取人を決めるときは要注意ですよ。
あれ?自分が契約したけど、受取人は子どもにしてしまったぞ!
なんてこともあるかもしれません。
ただ、契約途中で受取人を自分に変更しておくことも可能ですので、
もし受取人を妻や息子にしている、なんて方は検討してみてくださいね。
最も辛いうっかり
それから最も注意してほしいのは、満期保険金で契約者と保険料の支払い者が違っていた場合です。
例えば、妻を契約者としたけれど、保険料は夫である自分の銀行口座から引き落とされている、なんてケースです。
もちろん夫婦ですから生計同一ですし、お金が家計から出ていくには違いないので、
契約時はうっかり見過ごしてしまいがちなのです。
税務ではお金を負担している人で判断するので、契約者が妻だとしても、
受け取った満期保険金には、夫から妻への贈与として、しっかり贈与税がかけられてしまいます。
満期保険金が500万円で、支払った保険料が400万円だとします。
一時所得であれば、課税される所得は25万円となり、税率が10%であれば25,000円が支払うべき税金となります。
これが贈与税になると、53万円(特例贈与なら48.5万円)が支払うべき税金となります。
この差にはびっくりしますね!
保険の営業マンから契約時には、税金についても説明があるので大丈夫と思いますが、
心配でしたら一度ご自身が入っている保険について、税理士さんに相談してみてもいいかもしれません。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年2月2日
子どもの貧困とシングルママ
子どもの貧困率
先日、愛知県が主催する「子どもの貧困」について考えるシンポジウムに行ってきました。
2012年の調査で、子どもの貧困率が16.1%、6人に一人が貧困となっているデータに、衝撃を受けた人も多いのではないでしょうか。
私もその一人です。
愛知県は、自治体として貧困対策のための調査を、沖縄県に引き続いて全国で2番目に行いました。
愛知県はモノづくりと農水産物が豊かで、県民の所得も安定しており、貧困率は5.9%と全国平均からかなり低い数字でありました。
とはいえ、何もしなくても良い、というものでもありません。
貧困にあえぐ子どもがひとりでもいる限り、手当を続けていかねばと思います。
親の貧困が子どもの貧困に連鎖する、これはデータから立証されています。
子どもの未来は明るいものであってほしい、
どの子にも等しく成長の機会と笑顔が行きわたることを願うばかりです。
私たちに何ができるのでしょうか。
子どもの貧困家庭の半数超がひとり親家庭
貧困家庭の半数超がひとり親です。これは愛知県も全国平均も変わりません。
ひとり親、特にシングルママへの支援は欠かせないのです。
男尊女卑とまで言いませんが、やはり男女間の賃金価格差はあきらかに存在しています。
母子家庭の母親の9割強は仕事に従事しているものの、
OECD(海外諸国)のデータと比較して貧困率が高い、と指摘されています。
働けど、お金がない。
だから長時間働く、環境の悪いところで働く、それが子どもの育ちに悪影響を与える、
そんな悪循環を引き起こしているのです。
法律上の結婚をしなければ税の救いが受けられない
ある人がつぶやきました。
「私の友人なんだけど、未婚の母でさ、寡婦控除が受けられないんだよね…」
そうなのです。
税金の世界では、ひとり親支援の前提は法律婚ありきで設計されているのです。
所得税法法上の「寡婦」は以下に規定されています。
・夫と死別し、または夫と離婚した後、婚姻をしていない人
配偶者控除もそうです。
・「配偶者」とは、婚姻の届出を出している配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません
相続税法でも同じく、内縁関係の人は相続人としてカウントされません。
「じゃあ、籍を入れれば済むじゃないか」
「結婚をしない選択をしているのは個人の判断でしょう」
そう意見をいう方もいらっしゃいます。
もちろん、その意見に反論する気はありません。
しかし
税の世界の根本思想である「弱者保護」に立てば
本来意思決定に参加できていない子どもに、
つらい環境となるのは私は看過できません。
貧困家庭を救うために、全国で「子ども食堂」が増えています。
子ども食堂ではボランティアでなさる人がたくさんいます。
それはとても有り難いことで、素晴らしいです。
とはいえ、善意の方にすべてを頼るのも不足でしょう。
税制や民法には、時代に合った変化と弱き者、特に子どもへの支援を期待したいものです。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年1月19日
積むのは経験、そして信頼残高。
税理士事務所は10周年
新年が始まりましたね。
榊原輝重税理士事務所は、昨年11月に丸っと10周年を迎え、11年目に入りました。
多大なるご支援に感謝いたします。
ありがとうございます。
10年ひと昔といいますように、やはり振り返るには10年というタイムスパンは良いと思います。
ちょうど40歳になる年でしたので、「不惑」。孔子さまの教えです。
自分の生きる道にぶれない考えができました。
今度は50歳。
天命を知る、「天知」です。
ワクワクしますね。
信頼残高を積むこと
10年という時間はたくさんの経験を私にさせてくれました。
良い経験、楽しい経験、うれしい経験、
苦い経験、つらい経験、様々です。
けれど、どの経験も榊原輝重を成長させるために、必要なものばかりだったと思います。
そして経験以外に積んでいきたいものに、
信頼残高
があります。
この言葉は、有名なスティーブン・R・コビーの「7つの習慣」に紹介されています。
信頼残高とは、人間関係における信頼の度合いのこと。
銀行にお金を預けると残高は増えますね。
逆に引き出せば残高は減ります。
同じように、自分の心の中には「じぶん銀行」があって、
・約束を守る
・親切である
・人助けをする
・喜ばせる
・謙虚である
・謝る
・人の悪口を言わない
こういうことをすれば残高は増えていきます。
反対に、
・約束を破る
・嘘をつく
・人の嫌がることをする
・ごまかそうとする
・傲慢である
・陰口や悪口を言う
すると残高は減っていきます。
そして銀行にお金を預ければ「利息」が付きます。
今の日本は低金利でほとんど付きませんが(苦笑)・・・(これもまた信頼残高の観点からすれば異常ですね)。
利息は残高が多ければ多いほど、たくさんつくものです。
信頼残高とて同じこと。
信頼残高が多ければ、
困っているときに助けられたり、
人を紹介されたり、
優しい言葉をかけていただき、励まされたり、
いたします。
ご縁をいただくということは、まさにこういうことだと思います。
私も10年の時間の中で、
たくさんのご縁をいただいてきました。
感謝です。
ありがとうございます。
これからも、もっともっと信頼残高を積んでいけるように、精進してまいりたいと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年12月20日
平成30年の税制改正は・・・
毎年税制は変わります
税金ってどう決まっているのか、ご存知でしょうか。
「税は国家なり」とも言われ、国家運営では税金はとても重要な役割を果たします。
日本は民主義国家で、国民主権(=国民が主人公)と定められています。
憲法は全ての法律が従わないといけない「最高法規」として位置づけられています。
その憲法84条にはこう定められています。
「あらたに租税を課し、
または現行の租税を変更するには、
法律または法律の定める条件によることを必要とする」
これを租税法律主義といいます。
法律に書くことで次の二つが確保されると言われています。
課税の要件が簡単に変わらない
政府の解釈が簡単に変わらない
政府が、今年は税金が足りないからこれだけ集めよう、とか
去年は税金をかける収入は1000万からだったけど、今年は500万からにしよう、とか
簡単にされたら困りますよね。
だから法律にちゃーんと書くんです。
その法律は年明けの通常国会で毎年審議され、決まることになります。
与党の税制大綱
ではその原案はどう作られるのでしょうか。
法律作りは通常国会が始まる新年1月の前年、秋から準備されます。
原案を作るのは税制調査会ですが、
実は税制調査会には「政府税制調査会」(=政府税調)と「自民党税制調査会」(=与党税調)の二つが存在しているのです。
分かりにくいですね。
政府税調は財務省と総務省が主体となり、与党税調は自民党(与党)が主体となり作られます。
お互いが意見交換され調整され出てくるのですが、今までの政治では与党税調で定められたものが優位になっているようです。
その意味でも与党税調でまとめられる税制改正案が最も重要となるわけです。
例年12月に与党の「税制改正大綱」が周知されるのですね。
後出しじゃんけん
数日前に与党の来年度税制改正大綱が決まりました。
内容は新聞やニュースなどでご存知の方も多いと思いますが、「
しかも高所得者だけではなく、広く多くの国民が増税になるのです。
所得税の増税だけではなく、たばこの増税、
新たに国際観光旅客税、それから森林環境税など、数えたらきりがありません。
これほどの増税がでてくるなど思っていませんでした。
しかも意外なのは富裕層や儲けを出している法人への課税が棚上げになっていること。
私は現在の日本の財政状況から、将来の子どもたちのことを考えれば
増税はいたしかたないとは思っていますが、
一方で税金の大切な思想である
「弱者保護」の観点が疎かになっている気がしてなりません。
取りやすいところから取る。
しかも選挙が終わってからの、後出しじゃんけん。
ワタクシ、かなり怒ってます!
次の選挙まで、国会議員の先生方が決めることは、しっかりチェックしていきたいと思います。
皆さんも、選挙は終わってからが大事、そう思っていただきたいです。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年12月5日
会社の歴史はバランス・シートにあり
利益はどこで見ていますか
事業主の皆さん、税理士から渡された決算書を隅から隅まで読んでいるでしょうか?
決算書と言えば、貸借対照表と損益計算書、この二つがメインです。
税務申告書や科目の内訳書、注記やキャッシュフロー計算書までを広い意味での決算書と言えるかもしれません。
経営者の気になるところ、それはもちろん利益ですよね。
では利益はどこから読み取りますか?
はい、損益計算書ですね。
損益計算書には、上から「売上」、続いて「原価」があり、その差引きで「粗利益」が表示されます。
そして続いて「経費」があって、粗利益との差額が「利益」となります。
だから経営者、事業主の皆さんは損益計算書を必ず見ているのですね。
貸借対照表でわかること
ではもう一つの貸借対照表。
こちらも一生懸命読んでるよ、という方。素晴らしいです。
実際は多くの方が、貸借対照表は損益計算書ほどじっくり見ていないようです。
この貸借対照表、銀行はしっかり見ています。ご存知でしたか。
損益計算書は、一年間の経営成績を表していますが、それは一年限り。
貸借対照表は、開業してからの経営の結果が表されているのです。
つまり、
貸借対照表は会社の歴史である
といっても過言ではありません。
貸借対照表は、書いてある字のごとく対照に表示されています。
左側に「資産」、
右側に「負債」と「資本」。
資本を見てください。
「利益剰余金」という勘定があります。
これは今余っているお金、という意味ではありません。
ときどきこれを見た社長から
「ウチはこんなにお金は余っていないよう」
なんて言われます(苦笑)。
この利益剰余金は、今まで会社がたたき出してきた利益の総額を表しているのです。
ここを見れば、その会社が
長い間かかって利益を出してきた、
短時間で元手の数倍の利益を出してきた、
最近は利益は少しだが、長く堅実に利益を出してきた、
今年は利益が出ているが、過去は振るわなかった、
などが分かるのです。
そして、資産に目をやれば、
その会社がどこにお金を投資しているか、
お金に余裕があってリスクに強いか、
資金繰りが良いか、
が分かります。
負債に目をやれば、
利益を出すためにどれだけお金を調達しているのか
利益の効率はいいのか
短期的に資金がショートする恐れがないか、
などが分かるのです。
つまり、会社経営の意思決定が読み取れるのです。
奥は深いです。
いや~
いつも損益計算書しか見ていなかったわ、
そんな事業主様、経営者さん、
税理士と一緒に貸借対照表を味わってみませんか。
会社の歴史を振り返ると、来た道がはっきりしてうれしくなりますよ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年11月17日
子どもたちへの税金の使われ方
昨日私の住む学区で防災訓練に関する講習会があったので参加してきました。
この地域では南海大地震がかなりの確率で近々起こると言われており、
その時どうするのかは自治会では大きな関心事です。
時代は自助・共助の流れ
講習会では
「自助・共助・公助」
のお話があり、大きな地震が起きたときには、
まず自分自身で身を守る「自助」が大切であり、
そして地域、自治会や町内会でしょうね、が連携して行う「共助」が大切であると言われました。
なんと、行政からの「公助」はあてにしないでくださいと、消防の方からはっきり言われてしまいました。
新しい社会的養育ビジョン
先日、愛知県の子ども子育て会議に委員として参加したのですが、
「公助」を行政が行っていくのは大変だとの流れをそこでも感じたのです。
介護など例にとると顕著ですが、家族のことは家族で、施設でなく在宅で、との流れです。
確かに社会保障費の急激な増加は日本の財政をひっ迫させています。
児童養護施設に入る子どもたちは、戦後の時代は親が亡くなって孤児となって施設に入ったのですが、
今は虐待などで親と離れて生活をする必要があるとされている子が多いのです。
子どもの虐待は年々増加し、施設では量的に対応できなくなってきました。
これらは新聞やニュースなどでご存知の方も多いかもしれません。
そこで平成28年度に児童福祉法が改正され、
「新しい社会的養育ビジョン」が示されたのです。
施設から里親へ
ビジョンでは、今まで施設に預けられた子どもたちを
「里親制度を利用して
在宅で、家庭単位での養育を原則として行う」
とし、
原則として就学前の子どもは施設への新規措置入所を停止
する取組みを目標としたのです。
これには大変びっくりしました。
愛情が不足したりしている子に温かい家庭環境で育ってもらおう、という意図は分かります。
少子化の時代、自身の子育てでも大変なのに引き受ける家庭があるのかどうか、
(里親になるには年齢制限や所得制限があります)
施設なら関わる人の目も多いですが、家庭となれば密室ともいえます。
また施設で預かる子どもたちの生まれた環境から、子育てにも特別な配慮が必要となります。
欧米とは宗教的背景も違います。
はたしてどうなんだろう?と思いました。
子どもたちの養護と教育が最も大きな課題として共有されていれば良いのですが、
財政や予算の話でこのように決まってきたのなら心配です。
同じ日の新聞には
トランプ大統領の訪日で安倍首相はミサイルをたくさん買うことを約束との記事がありました。
税金をどう使っていくか
子どもたちが生きていく未来をどうするのか
考えさせられます。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年11月3日
そろばん合って銭たらず
ウチの事務所の得意なところとして起業支援があります。
かく言う私も、税理士ジュニアではなく、資格を取ってイチから事業を起こした起業家でもあります。
その意味でも起業する大変さや、こうしたらよかったことがアドバイスとして活きてくると思います。
赤字と債務超過
先日も起業を考えているある方からご質問がありました。
「赤字=債務超過と考えて良いですか?
その場合、銀行等から借り入れしていると、返せないって事になるのでしょうか?」
経営をされている方なら、即座に回答ができることでしょう。
まず「赤字」とは何でしょうか。
事業では売上と経費をまず認識します。その差額が利益ですよね。
これは損益計算で表されます。
売上から経費を引いて、マイナスだったら赤字となるのです。
次に「債務超過」ですが、こちらは何でしょう。
会計では持っている財産をプラスとマイナスの財産としてとらえます。
プラスの財産を「資産」と呼び、マイナスの財産を「負債」と呼びます。
債務超過は、資産<負債の状態を指します。
資産を全部お金に換えたとしても、負債を返しきれない状態、それが債務超過です。
もしここで銀行から借入れをしていたら、返せない状態にあるということですね。
つまり赤字=債務超過ではないということになります。
赤字が出たから、即債務超過で倒産!なんてことはないのです。
ただ赤字が続くことは債務超過になる原因とはなります。
黒字を継続的に出していかないと大変ですね。
収支計算と損益計算
赤字があるといってもその中身の検討が大切になります。
例えば、減価償却費。
会計では減価償却費は支出を伴わない費用となります。
損益計算書で営業利益が300万円赤字だとしても、以前設備投資した資産の減価償却費が400万円あったらどうでしょう。
損益計算上では赤字なのですが、資金は余裕があります。
収支計算の観点から見ると黒字になるのです。
逆に、今期に設備投資を2,000万円した年だとしたらどうでしょうか。
会計上は支出した金額全部が経費とならないので、
支出>経費となり、収支計算の観点からも赤字となります。
このように事業をしていく上では
収支計算と損益計算の二つの見方
で判断していかねばならないのです。
中小企業はやっぱり資金繰り
建設業や見込み販売などのように、
先に経費支払いが来る業種は、資金繰りをしっかり考えないといけません。
建設業は仕掛った仕事が出来上がり、引き渡した時に初めてお金になります。
しかし完成までに材料費や大工さんへ先にお金を支払っています。
卸売りや小売りでも見込み販売であれば、先に仕入れをしてお金を払っています。
しかも損益計算の売上や経費の認識は、
お金が動いた時ではなく、取引が発生した時に行うとされています。
つまり、お金が入ってきていないのに売上がたって利益が出ます。
しかも期間損益計算といって、決算の年にもれなく計上し、
利益が出ていると税金を支払うことになっているのです。
売上の回収が来年だったら大変です。
税金を支払うお金もない!!なんてこともあるのです。
だからこそ
中小企業は資金繰りが命!!
売上が上がってもお金になるまで時間がかかります。
損益計算上は黒字でも、収支計算では赤字(これを会計ではキャッシュフローと言います)だと
事業は立ち行かなくなります。
それを
「そろばん合って銭足らず」
といいます。
日ごろから会計処理はため込まず、
建設業なら前受け金をもらう
販売業なら見込み販売から注文販売にシフトする
銀行には予め資金繰りを相談しておく
ことが大切になっています。
お金の回し方については
会計の専門家である税理士にぜひ相談してくださいね。
明確な指標をもって、予算管理を手伝ってくれると思いますよ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!