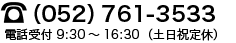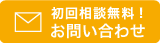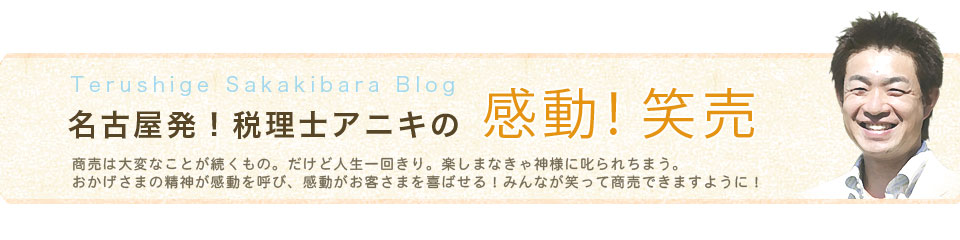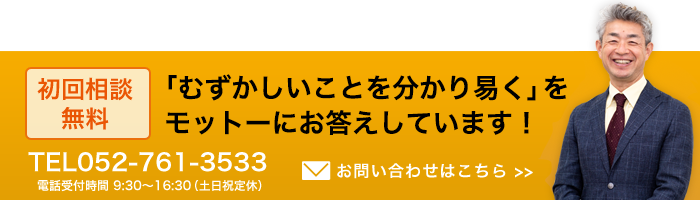2017年10月20日
なんだか難しい配偶者控除。判断基準はナニ?
選挙カーが事務所の外ではひっきりなしに走っています。
まもなく衆議院選挙です。清き一票を~
税をどうしていくのか、代議士の先生方には大いに議論していただきたいところです。
配偶者控除が変わりました
さて
平成29年度の税制改正では配偶者控除の見直しがされています。
これも代議士の先生方が議論して決めたことの一つです。
それで、どう変わったの?ということですが
103万円が150万円に引き上げられた
これが世の中の皆さんの共通認識でしょうか。
しかし視点がずれてしまうと
「え?そんなことだったの」
と間違えてしまいそうなんです。
ややこしや~
説明しますね。
この改正で誰の税金がトクになるのかを考えると分かりやすいです。
モデルケースとしては専業主婦のいる家庭、
夫が主な稼ぎ手として働き、妻は補助的にパート収入を得ている、そんな家庭です。
10月を過ぎると、世の中のパートで働いている主婦の皆さんは、働く時間を調整し始めます。
それは103万円を超えないようにするためなんですね。
なぜでしょうか。
妻の収入が103万円を超えると税金が増えてしまうからです。
では、誰の税金が増えるのか、この視点が大切です。
103万円を超えると
夫の税金が増える
これが答えです。
わが国の所得税は累進課税と言って、所得が多い人の方が税金が高くなります。
ですので、世帯収入で考えれば夫の方が高い税率ですから、
妻の収入を抑えて、夫に配偶者控除してもらう方がトクということになるのです。
この金額の上限が103万円から150万円に引き上げられたのです。
妻のパート収入が150万円なら今までと変わらず、夫の税金は増えません。
さらに、配偶者特別控除としては200万円までなら夫の税金は安くなる設計となっています。
つまり、パートで働いている主婦に皆さん、もうちょっと働いてください、
ということです。
夫の税金は増えない線引きが150万円にあるのですね。
でも私の税金はどうなるの?
しかし視点を変えます。
妻である自分の税金はどうなるのか?です。
いままでは103万円までなら税金はかかりませんでした。
正確に言えば国税はかかりませんでした。
住民税は市町によって課税される金額が90万円から100万まで様々です。
だから103万円までにしたからと言って税金がかからないわけではありません。
住民税がかかるようになると、介護保険料がどんと増えたり、市町の行政サービスを受けることに影響が出ますので注意してくださいね。
それで話を元に戻します。
答えは。
103万円を超えたら私本人(妻)には税金がかかってきます
えええ~
そうなんです。夫の税金は助かりますが
私本人(妻)にはちゃんとかかる(苦笑)。
130万円の壁と世帯収入の壁
社会保険はサラリーマンの妻であれば、パート収入が130万円までだったら
夫の扶養となり保険料も年金も支払わなくても良いことになっています。
これを「130万円の壁」なんていいます。
130万円を超えるとどうなるか。
社会保険は夫の扶養から外れ、健康保険と国民年金を自分で支払うことになります。
また今回の改正では
世帯収入が多いと控除額が減額されます。
つまり減税効果が薄まるということです。
まぁ、高所得の方は税率が高いので減税効果も高くなりますから、金持ち優遇といわれるのを避けたのでしょうね。
ということで、ホント分かりにくいというか、
で結局どう判断すればいいのと思ってしまいますね。
個人的には全部の壁を取っ払ってしまって
税金も社会保険も個人単位で負担してもいいのかな、と思います。
とはいえ考え方や生き方も様々ですから
選挙の時くらい、じっくり考えてもいいかもしれません。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年10月6日
年末調整、その前に!点検してください
ひと雨ごとに秋が深まっていきます。
朝晩は涼しくなりました。あっという間に年末が来ちゃいますね。
年末調整って?
年末といえば、税務会計での一大お仕事、年末調整です。
経理の方は忙しくなりますね。
年末調整とは、サラリーマンの確定申告です。
日本は源泉徴収制度が導入されています。
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払う側が、あらかじめ所得税を差し引くことを指します。
いわゆる天引きですね。
差し引いた税金は、支払い側、つまり会社や事業主様が税務署に納付することになっています。
これは所得税の仮払いですので、年末に確定申告を会社(事業主)が本人の代わりに行って税額を確定させます。
日本の源泉徴収制度の特徴は
多めに天引きしている。
だからほとんどの方が還付になる。
還付だから「やった~、お小遣いが増えた!」と喜んでいるあなた。
もともと手元にあって自由に使えたお金なのですよ。
利息をもらわないかんでしょ(笑)。
外国で源泉徴収制度を取り入れている国は意外と少ないです。
ヨーロッパではフランスがそうですが、ほとんどが申告をして追徴で納めるようです。
徴収の仕方は2種類
さて徴収する側である法人様や事業主様に注意してほしいことがあります。
徴収は2種類あって(正確には3種類ありますが実務的には2種類です)、
ひとつが「甲欄」課税、ひとつが「乙欄」課税です。
「甲欄」と「乙欄」では、同じ給料でも徴収する税金額が違います。
乙欄はかなり高い金額となります。
「甲欄」は特別に安くなる、そう覚えてください。
調査では甲欄と乙欄が見られる
法律では「甲欄」に該当するのは主たる事業所から給料をもらう、
「乙欄」に該当するのは従たる事業者から給料をもらう場合となっています。
正社員なら「甲欄」、アルバイトやパートさんなら「乙欄」と考えていただければ良いです。
税務調査では調査官は「甲欄」になるか、「乙欄」になるかしっかりチェックしていきます。
もし追徴されると加算税(10%)や延滞税が遡って事業主さんにかかってきます。
他人の税金であっても容赦ありません(トホホ)。
甲欄になる要件
だから従業員さんが「甲欄」に正しくなっていれば安心です。
ここがポイントになるのですが、「甲欄」になるためには要件があるのです。
それは
扶養控除申告書(通称マル扶)が会社に備えおいているか
例え正社員だとしてもマル扶がないと「乙欄」になってしまいます。
調査で指摘されたら後の祭りです。
差額分は会社が納めなければならず、かといって従業員から徴収しなおすのも要らぬ軋轢を生む可能性があります。
従業員が在籍しているならまだ徴収し直しもできるでしょうが、もう退職していたら泣き寝入るしかありません。
また兼業の場合(アルバイトさんやパートさんの場合)、マル扶は一か所しか有効ではないので、念のためにもらっておこうというわけにもいかないのです。
もし誤って二か所に出ていると「先に」もらっていた事業者が優先的に認められますので注意が必要です。
流動性の高い職場、アルバイト、パートさんが多い職場は気を付けて下さいね。
実務的には年末調整の袋が届いてから、マル扶を書いてもらっているところもあるようです。
年度を間違うと、既にやめてしまった人の分が足りず、調査で「乙欄」で追徴なんてことになりかねません。
日ごろからしっかり準備しておいてくださいね。
思い立ったら吉日、マル扶を従業員からもらっておいてくださいね。
「おや?」
そう思ったら信頼のおける税理士にぜひお尋ねください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年9月21日
ビジネスとは?
ビジネスとは?
事業をされている皆さまにご質問です。
ビジネスとは?
ぱぱっと、言葉で、簡潔に答えられる方、素晴らしいです。
では、
あなたは何屋さんですか?
出来れば一言で。
これもぱぱっと答えられたら素晴らしいです。
オールクリアー、パチパチ(拍手)。
でもやってみると意外に「う~~~ん」となったり、
「いや、ひと言で表せないよ」「商品を説明したらいいわけ?」
など簡単じゃなかったりしますね。
私ですか?
ビジネスとは、お客様の不安や問題を解決することで喜んでもらって、感謝をいただくこと、だと思います。
だから「あなたをこうしたい」「社会をこうしたい」という一方通行の思いはビジネスでないのですね。
まずは目の前の「あなた」の感謝をもらうこと、その感謝が増えて社会が良くなっていけば最高ですね。
私は何屋かと問われれば・・・。
ビタミン注入屋!!
社長を元気にします!
なんや、それ(笑)
税理士は税金の申告書を作ったり、会計の処理のお手伝いをしたりします。
でも榊原輝重は社長や経営者を元気にするのが仕事だと思っています。
実はこの言葉は関与先様から頂いた言葉で、
「榊原さんは税金だけでなく、経営やプライベートのことまで訊いてくれます。
話をし終わるとなんだかすっきりして、ビタミン剤をもらったような気がするのです」
うれしいですね~
事業はすべて定義づけから
事業をしていく上で、事業主様や経営者様にしていってほしいことは
定義づけを常に意識して言葉にすることです。
「~とは?」
ビジネスとは?
商品とは?
お客様とは?
お客様の要望とは?
売上とは?
利益とは?
全てを言葉で表してみてください。できればひと言、簡潔に。
これらを決めていくことは事業領域(ドメイン)の輪郭をはっきりさせることです。
輪郭がはっきりすればお客様からあなたがはっきり分かります。
何屋かがわからないと頼めませんよね。
私たち税理士は事業をしている皆さまのおそばに常にいる者たちです。
ご自身の事業ドメインをお話しください。
「わかっているようで一番わからない自分」
私の大好きな相田みつをさんの言葉です。
自分では気づいていなかった素晴らしい輪郭の答えをもらえるかもしれません。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年9月1日
固定資産台帳の管理は宝の山?
固定資産の台帳は作っていますか
事業を行うには様々な固定資産を購入して利用しますね。
営業に回るなら、自家用車。
工場で製品を作るなら、ラインに配置された機械。
事務所なら、OA機器。
これらを会計では固定資産といいます。
使っていくうちにその資産価値が下がっていくものを特に減価償却資産といっています。
皆さま。固定資産は台帳を作ってしっかり管理していきましょう。
税務では宝の山?なんてこともありますよ。
固定資産は税務と会計で取り扱いが違う
固定資産は税務上と会計上とでは違う取り扱いがなされたりします。
その税務上においてでさえ、国税と市税では取り扱いが違ったりするので要注意です。
税務では政策誘導がしやすいため、毎年のように特別措置がなされたりするんですね。
減価償却費の計上は会計では毎年しなくてはなりませんが、
法人税法では、あえて「しない」という選択も認められています。
例えば、工場経営をしているような法人様で、
今期は赤字が出ているからあえて減価償却費の計上を控えて黒字決算にする、なんてこともあります。
除却損を計上して節税
固定資産をたくさん持っている会社では、
何年も経つと、もう使わなくなったよ、という固定資産も増えてきます。
そんな時は「除却損」を計上しましょう!
利益が減り節税効果が得られます。
注意してほしいのは、そのタイミング。
使わなくなった、廃棄した、その事実を確認できるようにしておくことが重要です。
税法では、除却があった事実が認められないと経費として認めてくれないのです。
今年は利益が出ているから、「え~~い」とまだ動いている機械まで除却!!なんてしても後で困ったことになります。
税務調査の時に「恣意的に資産を除却して利益を減らした」と言われないようにしてくださいね。
お客様から相談があったら、
スクラップにしたときに写真を撮ったり、
廃棄業者に廃棄証明書を書いてもらったりすることもあります。
その意味でも固定資産台帳でしっかり管理しておくことは大切なんですね。
数年前に廃棄してしまったけど、会計の処理を忘れてしまって
まだ貸借対照表に資産として残っている・・・。
使わなくなって倉庫に入れてる・・・。
こんなケースは専門家に相談してください。
簡単に「除却損」としてその年の経費にしてしまうと、問題になってしまう可能性があります。
税理士なら丁寧に相談にのってくれると思いますよ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年8月7日
奥様はみなし役員?
日本の多くの会社が同族会社
日本の多くの会社が中小零細会社です。
企業数でいえば99.7%。
従業員数でいえば66.7%
が中小零細企業です。
中小零細企業では、家族経営、いわゆる同族会社であることがほとんどです。
奥様が役員の会社も多いことでしょう。
法人にするメリットにする一つに、奥様が役員であれば報酬額が自由に決められることがあります。
(とはいえ、月に●百万などあまりに高額だと問題になる場合もありますけどね)
所得税では累進課税方式ですので、給料の額が上がれば税率が上がります。
つまり社長ひとりに月額100万円の給料を出すより、
社長と奥様に50万円ずつお給料を出した方が、家庭が負担する税金は減るということです。
役員賞与は課税対象
注意してほしいルールが法人税にはあります。
それは、
役員のお給料は経費です。
しかし、賞与は経費として認めません。
どういうことかというと、役員への賞与は会計上は経費だけれども、税務上は経費として認めれれないので税金計算するときに所得を増やすのです。
役員は登記をすることになっています。
「ウチの奥さんは役員に登記をせず、単なる従業員扱いにしておこう」
そう考える社長さんもいらっしゃいます。
税務調査の時にはこんな質問がなされます。
「奥様の給料が他の従業員と比べてとても高いと思うのですが、なぜですか?」
「彼女は私の仕事をとてもよく理解してくれている。
会社の経営や従業員の処遇など、いろいろ相談して決めている。
だから当然給料は高いんだ」
「賞与も出していますよね」
「ああ、従業員と同じように出しているよ。
役員でもないしね。それが何か?」
みなさん、ここ大切なポイントです。
実は、税務上アウトになる可能性が高いです。
従業員よりかなり高い給与部分や、賞与が役員賞与として認定され、税金がかかってくる可能性があります。
みなし役員だと課税
法人税法では、「みなし役員」の規定があり、
いくら登記されていないと言っても家族従業員が役員とみなされるケースがあるのです。
以下の4つのケースにすべて当てはまるとみなし役員になってしまうのです。
1.50%基準
株主グループの所有割合が大きいものからグループ分けしていきます。同じ家族だとグループになり、おじさんやいとこだと違うグループになります。
そのグループ分けで第1順位から第3順位まで集めた株式の所有割合が50%を超えていること。
小さい会社や創業間もないとこのケースが多いですね。
2.10%基準
所属するグループの所有割合が10%を超えていること。
メインの株主に近いグループですね。
3.5%基準
本人と配偶者の所有割合が合わせて5%を超えていること。
お父さんが先代社長で、跡取りの子どもたちやそのお嫁さんが株式を分散させてもっているケースがこれにあたります。
4.経営に従事している
ちょっと判断に迷っていましますね。
賞与認定を受けないポイントは
社長の配偶者や子どもは重要な意思決定には参画させない
所有割合を判定する場合は、配偶者の持ち分も加算して判定
とはいえ、やはり専門家に相談したほうが良いですね。
登記していないから奥さんにボーナスを出しても大丈夫だよね、
ちょっとお待ちください。
転ばぬ先の杖、まずは税理士に相談してからにしましょうね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年7月20日
会社設立。資本金の金額はご注意ください。
会社を設立する場合、元手となるいわゆる「軍資金」が必要となります。
会社を最初に設立するときに用意する元手となるお金。
それが資本金と呼ばれるものです。
では資本金はいくら必要なのか。
会社法が2006年に改正されました。
それまでは有限会社なら300万円、株式会社なら1,000万円が必要でしたが、
いまは
1円!でも会社設立!
することができます。
とはいえ1円ではパソコンすら買えません。
もし私が銀行なら、「この会社はナニ?ペーパー会社?怪しい!」
と思ってしまいます。
現実的には、しばらく会社を運営するに足りるお金が資本金として準備することになります。
だから経営計画を立てて出資する金額を決めていくことがほとんどです。
最初の出資は自分で用意する自己資本と呼ばれるお金と、
他人資本と呼ばれる銀行融資があります。
とはいえ融資も望む金額を無尽蔵に貸してくれるわけではありませんので、
ある程度は自分で用意しなければなりません。
その過程の中で金額が決まってくるわけです。
税務上にはポイントは二つあります。
これをうっかり忘れてしまうと
節税になったのに~
と後で後悔してしまいかねません。
それは
資本金は1,000万円と1億円。
ここが要注意です。
まずは1,000万円。
設立するときに資本金が1,000万円に満たないと
原則最初の2年は消費税が免税となり支払う必要はありません。
時々質問を受けるのですが、「免税事業者なので消費税をかけずに売るのですか」と聞かれます。
それは誤りで、消費税はちゃんとかけて売っていただくことになります。
ただ、納める必要がないので、
その預かった税金は「益税」といって手元に残るのです。
(課税の考え方からは困るのですが、法律上はそうなっているのです!)
999万円だとキリがよくないから、じゃ昔の株式会社と同じように1,000万円で、
なんて軽々しく行うと消費税を支払うことになります。
次は1億円。
1億円のラインは
中小企業だけど「あなたはそこそこ優良ね!」
だから大企業並みに頑張れるよねと判断されるのです。
つまり、1億円以下の中小企業だと、メリットがあるのです。
1. 法人税を計算する際に、軽減税率を利用することができます
➡ 法人税が所得800万円まで低い税率で計算されます
2. 交際費は800万円まで、全額を損金にすることができます(平成26年4月1日以降)
➡ 交際費は使っても全部が経費にならない、これが常識。だけど小さい会社なら全部経費として認められちゃいます
3. 30万円以下の少額減価償却資産が年間300万円まで損金として認められます
➡ パソコンや事務機などお金を使ったときは税金も抑えたいもの。使った分が全部経費となればありがたいですね
4. 特定同族会社の留保金課税が免除されます
➡ 同族会社特有の税金です。内部留保といって会社にお金を残しても税金をかけるよ、というまさに中小企業に厳しいルールですが、これも免除!
5. 欠損金の繰り戻し還付が受けられます
➡ 赤字が出たときに、過年度の支払い税金を戻してくれる制度です。
6. 法人事業税の外形標準課税が免除されます
➡ 大きな会社はその外見に応じた税金を負担しなさい、というもの。中小ならこれも免除です。
7. 法人住民税の均等割税金が安くなります
➡ 住民税は雇用している人数や資本金に応じて、均等割りが上がっていきます。
節税目白押し!!
会社が大きくなってくると資本金を増やして(これを増資といいます)いく場合も多いですが、
家族経営や同族で経営する会社なら、このあたりの節税も注意しておいてくださいね。
うっかりがないよう、専門家に確認を取りながら会社設立や増資は進めていきましょう!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年7月2日
オーナーさんからの借入金、どうすればよいのでしょう
会社経営をしているとよい時も悪い時もあります。
資金が足りないときは、
経営者は役員報酬を未払いにしたり、
逆に会社へお金を貸し付けたりします。
小さい会社では、銀行が経営者の個人財産をも与信としてとらえていますので、
経営者の会社への貸付金は一つの方法として考えられています。
とはいえ、返してもらわないと事業している意味もありません。
中小零細会社では、
多くの会社がオーナーさんからの借り入れが多大となり、
そのまま残っているということもしばしば。
親から子へ事業が移っているけど、親が存命なので何も手を付けていない、なんてことも。
親からすれば、余力ができてから返してくれればいいから、そんな親心があるのかもしれません。
しかし、いざ相続となると大変です。
会社へ貸したお金は「債権」として相続の財産としてみなされ、
相続税がかかってきてしまうのです。
相続をする息子からしては会社から返してもらうだけになりますが、
その権利を取得するのに税金を払うなんて納得いきませんよね。
だからオーナーさんからの借り入れは、税務上の対策をしておく必要があります。
オーナーさんからの借り入れ対策は二つ方法が考えられます。
「もうそのお金は返してもらわなくていいよ」と諦めてもらって債権放棄をする。
または
負債ではなく出資したものとして資本金に振り替える。
今回取り上げるのは債権放棄です。
オーナーさん、それも先代の親から会社へ貸し付けている場合は、
相続財産になるくらいなら、あきらめていいよ、という方も結構いらっしゃいます。
そんな時は債権放棄をしていただくのが有効です。
債権放棄をすると、会社側では返すべきお金を返さなくてもよくなりますので、
トクをしたことになります。
これは「債務免除益」といって税務上は所得としてみなされ課税対象にされます。
とはいえ、オーナーさんから借り入れているような会社は大きく赤字である場合がほとんどです。
つまり、青色申告者であるなら繰越欠損金が残っているはずです。
その繰越欠損金と相殺することで、債務免除益の税金は納める必要がなくなります。
会社では法人税、個人では相続税が助かるというわけです。
ただ注意するところもあります。
会社の資本金が1億円を超えている、
かつ
特定同族会社(半分以上の株をオーナさんが持っているような会社)であると、
留保金課税という別の税金がかかってくる可能性もあります。
また、あまり安易に行うと税務署とトラブルになる可能性も否定できません。
再建計画など会社で検討しておくことをお勧めします。
役員の貸付金がたくさんあって、
しかも先代からの借り入れで、
赤字の会社で欠損金もそこそこあるのなら
考えてみるタイミングですよ。
もちろん、専門家である税理士に相談して慎重に行ってくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年6月17日
税理士と公認会計士の違いって?
よく聞かれることの一つに、
「税理士さんと公認会計士さん、何が違うんですか?」
という質問があります。
一昔前には
「ウチは税理士ではなく会計士に顧問を頼んでいるんだ」
「会計士の方がグレードが上だよね」
「税理士さんて経理士さんでしょ」
などよく耳にしました。
そういうことを聞くたびに、意外と皆さんには違いが伝わっていないんだな~と思ったものです。
たしかに文字だけ見れば、税理士は税金のことに詳しくて、会計士は会計に強いと思うかもしれません。
ですが税理士でも「○○会計事務所」と名乗っているところもあり、
お願いしている業務も記帳や経理のお手伝いなど会計の範囲だったりしますので、とても分かりにくいのでしょう。
実は税理士と会計士、活躍するフィールドが全く違います。
説明しますね。
証券取引法に上場会社は会計監査人の監査を受けなければならない、と規定されています。
この会計監査人としてオシゴトできるのが「公認会計士」なのです。
上場会社を相手にするので、個人でやっている方はほとんどいなくて、監査法人にお勤めしている方がほとんどです。
その監査法人も国内では4大監査法人が幅を利かせています。
税理士は、主に税務申告書を作ることがオシゴトとなります。
したがって中小零細企業では自分自身で作るのは難解で手間でもあるので、税理士に委託するケースが多いのです。
会計士は上場会社を相手にし、
税理士は中小零細企業を相手にする。
そんなところから、会計士は税理士よりグレードが上だとおっしゃる方がいるのかもしれません。
しかし内容は全く異なります。
試験でいうと会計科目である簿記と財務諸表については共通ですが、
会計士の試験には税法がありません。
そして税理士の試験には監査論がないのです。
得意とする分野が違うのですね。
しかし会計士さんは監査法人から独立して税理士会に登録すると、税理士として仕事ができることとなっています。
だから税務申告や税務会計のフィールドで税理士とともにオシゴトしているのです。
事業をされている皆さま。
会計士さんも、もちろん私たち税理士も日々研鑽しております。
だからどちらに頼んでもきっちり対応してくれると思いますので安心してください。
大切なのは、いかに親身になってお客様の経営の悩みや相談に乗れるかだと思います。
コミュニケーションをとってベストのパートナーを選んでくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年6月10日
繰越欠損金は節税効果がすごいですね
会社経営をしていると、残念ながら赤字がどうしても出てしまうときがあります。
赤字が出るときは資金繰りも当然苦しくなります。
例えば、
今年赤字が1,000万円でてしまいました。
所得税は所得にかかるので今年の税金はゼロです。
翌年は頑張って利益を1,000万円だしました。
中小企業の実効税率は1,000万円の所得だと25%くらいです。
250万円を税金として納めなくてはなりません。
前年は1,000万円赤字で税金ははらってませんが、キャッシュは社外へ出て行ってしまっています。
今年1,000万円利益が出たとしても、税金を支払ったら手元には750万円しか残らないことになります。
ちょっと辛いですよね。
だから法人税法では繰越欠損金制度で、
過去の赤字と今年の黒字を相殺して税金計算をしていいよ
となっているのです。
そうすれば今年の利益1,000万円は去年の赤字1,000万円と相殺、所得はゼロとなり
税金は今年もなし、儲かったお金は丸々残る、というわけです。
いや~助かりますね!!
中小零細企業にとってはキャッシュが最も大事ですからね。
ただ要件があります。
会計経理がしっかりしていることと
青色申告者であること
税務署からすれば、そりゃそうだと思います。
税金が大きく節税となるので、しっかり会計経理をしてね、ということです。
この繰越欠損金制度ですが、
中小企業を前提にお話しさせていただくと、繰越期間が昔から比べてどんどん伸びています。
私がこの業界に入ったときは5年でした。
それが平成13年には7年に延び、
平成20年からは9年に延びているのです。
だから過去に大きな赤字を出すと最長9年まで税金を支払わなくてよい、なんてことも。
しかし注意しないといけないこともあります。
いろんな会計の帳票や証憑類(レシートや領収書など)の保存期間も延びているのです。
この保存期間は会計法上と法人税法上でそれぞれ定められています。
会社法上10年間の保存期間と定められている書類
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
- 売掛金元帳
- 買掛金元帳
- 売上帳
- 仕入帳
7年間の保存期間と定められている書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 契約書
- 注文書
- 請求書
- 領収書
- 通帳
- 棚卸表
ただ実務では繰越欠損や税務調査が及ぶ最長期間の9年保存をお勧めしています。
(税務調査があったらそれ以前の分は片づけちゃうという事務所もありますね、笑)
とはいえ書類を保管する地面のお金も(事務所や倉庫代)もばかになりません。
悩ましいところですね。
紙の保存が原則となりますが、
マイクロフィルムやCD、スキャニングしたデータでの保存も認められます。
ただ税務署への届け出や管理方法の確立などが必要となってきます。
詳細はまたの機会にしたいと思います。
このあたりはお付き合いのある税理士に聞いてみてもいかもしれません。
いいアドバイスがもらえることと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年5月18日
お商売で奥さんにお給料を出したいんだけど
お商売を始めると、人手が必要になってきます。
そんなとき頼りになるのがやっぱり家族。
夫婦で一生懸命やってます!
ステキですよね♡
儲かってくればそんなパートナー(配偶者)のためにお給料でも払ってあげたい、そう思うのが人情でしょう。
しかし税法では原則的にはパートナーへ支払ったお給料は経費としてみなしません、となっているのです。
「え~~~そんなぁ」
でもご安心ください。
専従者と言ってもっぱら事業のお手伝いをしている家族なら、お給料を経費として認めてくれるのです。
家族ですからパートナーでなく、親や兄弟、子どもだってかまわないです。
ただ生活を一緒にしている方に限られますけどね。
経費として認められる方法は二つあります。
それは青色専従者給与と白色専従者控除。
青と白!
単なる色違いですが内容は全く違いますのでご注意ください。
個人でお商売するときは自分で確定申告しないといけません。
確定申告の方法は青色申告か白色申告かを選択することになっています。
青色申告は税務署に届けを出せばOK。
青色専従者給与で経費に認められたいなら、まず青色申告の届を出すことから始めましょう。
でも青色申告の届けを出せばいいかといえばそうではありません。
青色専従者給与の届けが別に必要です。
うっかりすると忘れそうですね。
その届けにどれくらい給料を出すよと書いて初めて経費として認められます。
白色の専従者控除は青色と違って事前に届けを出す必要がありません。
支払った金額ではなく一定額まで経費としてみなす、いわゆるみなし規定になっています。
ただ金額に上限が決まっていて、アルバイト程度の金額しか経費しか認めてくれないのですね。
こんなことがありました。
クリーニング業をしていたある事業主様が、青色申告の届けを出しました。
毎月15万円、一年で180万円のお給料を支払いました。
しかし青色専従者給与の届け出を出すのを忘れていたことに確定申告の時になって気づいたのです。
残念ですが、支払った180万円は経費になりません。
しっかりと本人さんに利益として税金がかかってきます。
そこで白色専従者控除の「みなし規定」で経費にならないかと考えたのですが、
やはり青色申告の方はそれもできません。
原則通り経費にはならないのです。
こうなって今手は後の祭り。悔しいですね。
つまり、
届け出を出しておかないとえらいことになってしまうのです。
税の世界では、届出を出しておかないとダメよがけっこう多いのです。
税務署も最近は丁寧になりましたが、個別の相談はこちらから尋ねなければ教えてくれません。
気づけばよいのですが、今回のケースでも青色の届け出を出したから安心、そう思っているとうっかり落とし穴にはまってしまいます。
やはり税の専門家に確認してからが、よさそうです。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!