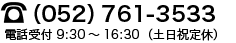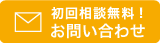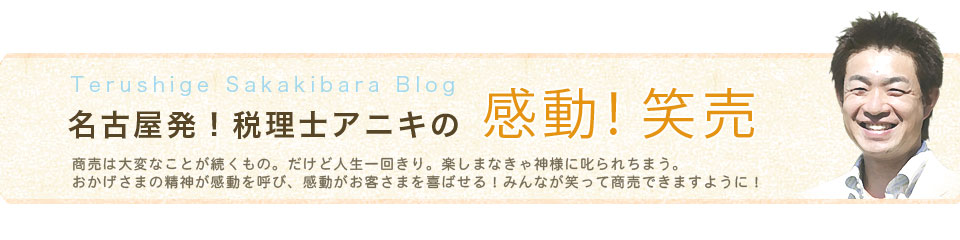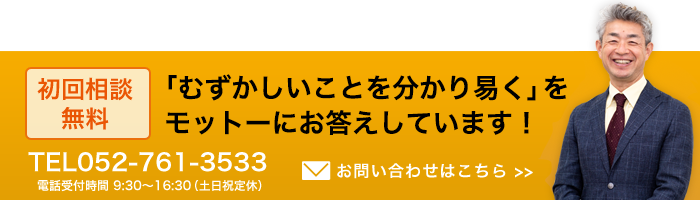2017年5月10日
日本国民の義務ってたったの三つです。
この記事はGWさなかに書いています。
5月3日は憲法記念日です。
憲法について考える日だと思います。
でも、憲法って堅苦しいとか面倒くさいとか思っていませんか。
私は名古屋税理士会の租税教室の講師としてお話をする機会がよくあります。
租税の観点からは憲法は避けて通れないのですね。
いざ話をしてみると子どもたちはおろか、大人の方でも意外と知らなかった~と感想をいただくので面白いです。
憲法はすべての法律の上位に位置し(従うべき基準というのでしょうか)、
全部で103条からなっています。
この103条の中で、
国民の義務として定められているのは、たったの3つ
なのです。
あとは権利(笑)。
憲法は、
立憲主義(りっけんしゅぎ)
に基づいています。
コレ、意外と知られていないんです。
憲法は「国民が守るべきルール」ではなく
「国家(政府)が国民に対して守るルール」とされています。
国民主権が憲法の大原則なんですね。
お上の言うとおりに。。。なんて
それは昔のお話しで、今は国民が主人公なんです。
さてその義務ですが何だと思いますか?
ひとつは
働くこと。
勤労の義務と言って27条に書かれています。
そして
税金を納めること。
納税の義務と言って30条に書かれています。
つまり、
国民は働いて税金を納めんといかんのじゃ~~
ということです。
面白いのは外国では納税の義務だけというところも多いのです。
働いてお金を稼がなければ納税できないんだからと、当たり前に考えるのでしょう。
わざわざ勤労を義務としているのは、日本ではお金をもらわないけど、人のために働く文化があるのかもしれません。
働くのが美徳。
「はたらく」は漢字では人偏(にんべん)に動くですから、「人のために動く」と言えますし、
「端をラクにする」なんていう方もいます。
あともう一つの義務は教育です。
子どもたちには大人になることは権利と義務の両方を果たすことだよと伝えています。
では勤労と納税の義務とセットになる権利は何でしょうか。
それは選挙権だと思います(15条)。
国民の皆さんが一所懸命働いて、そして納める税金。
その使い道を決めているのが議員さんたちです。
使い道をしっかりチェックして、みんなが豊かに生活できるように、しっかりと議員さんを選ぶのです。
5月3日。
日本の国家予算は100兆円です(とはいえ税金はおよそ半分ちょっとですけど)。
しっかりと使われているかなぁと考える日でもあります。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年4月26日
「生産性の向上」で助成金が割増しになる制度が始まりました
「生産性の向上」。
最近よく耳にします。
労働生産性の国際比較をデータで見ると
日本はなんと18位!
これだけじゃ分かりにくいのですが
西ヨーロッパやアメリカなど経済的に豊かな先進国と比べると
ほぼ最後位になり(まだ韓国がいました)、
後に続くのが東ヨーロッパ諸国。
ちなみに経済破綻をして借金を返さないと宣言したギリシャより一つ下になります(アレー)。
日本では一生懸命働くのは美徳とされますが、
体を壊すほど働くのはまずいですよ。
過ぎたるは及ばざるがごとし。
しっかり成果を出すように働くが
時間はほどほどが良い、そうなるといいですね。
さて、榊原税理士事務所は社会保険労務士事務所を併設しています。
助成金を多く扱っているのですが、社会保険労務士の榊原陽子からこんな質問が。
「今年から生産性が上がると助成金がぐっと割増しになるんですけど、何を見ればいいのか分からないわ。
会計の知識がないと難しい!」
手引きをみると、なるほど決算書の数字を転記していけば生産性が上がったかどうかが判定できるようになっています。
「そんなに難しくないよ~」
とはいえ畑が違うと分からないものなんですね。
おなじくシャインズの社会保険労務士である金澤に聞くと、
「社会保険労務士事務所単独ではちょっとできませんね」とのこと。
ちなみに生産性が上がると割増しになる助成金はこんなにたくさん!
ぜひ会計情報を織り込んで割増しで支給を受けてくださいね。
・労働移動支援助成金
・地域雇用開発助成金
・職場定着支援助成金
・人事評価改善等助成金
・建設労働者確保育成助成金
・65歳超雇用推進助成金
・両立支援等助成金
・キャリアアップ助成金
・人材開発支援助成金
・業務改善助成金
割増率は、おのおので違いますが
30~50%割増しで支給
されるとのことです。
魅力的ですね~。
お客様にとったら、社会保険労務士と税理士とワンストップですめば便利ですよね。
すでに助成金を社会保険労務士さんに頼んでいる方、
念のため「割り増し支給ができますか」
とお尋ねくださいね。
きっとネットワークで調べてくれると思いますよ。
もちろん、ウチの事務所でも対応してます(笑)。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年4月3日
実感。クラウド会計のメリット
この記事は確定申告を終えたばかりで、ほっとしているさなかに書いています。
確定申告といえば個人事業主の申告をさすことが多いです。
期限は3月15日。
税理士事務所も税務署も猫の手を借りたいくらい忙しいですね(汗)。
実は法人も確定申告というのですが、その申告時期は自分で決められます。
しかし個人は一律3月15日。だから業務が集中してしまうのです。
私どもの事務所では平成27年からクラウド会計ソフトを導入しており、
お客様にもお使いいただくようお勧めしております。
今年はクラウド会計ソフトを使い始めて2回目の確定申告でした。
昨年はどうしても慣れないことも多くて気づけなかったのですが、
あらためて思ったのです。
お客様にとっても
私たち税理士事務所にとっても
とっても便利!!
経理専属のスタッフがいらっしゃる事業主様ならまだよいのですが、
多くの事業主様はご自身か配偶者が経理をしていることが多いです。
お金のことなのでスタッフに任せられない、と思っている方も多いのですね。
銀行での記帳、そしてソフトへ入力するのだって大変な時間を要します。
「ああ、もっと時間があればいいのに」
期限が決まっている確定申告時期、そんなため息をよく聞きます。
私たちも「なんとかしてあげたい」そう思いつつ、
「早く資料は出してください!間に合いません!」
なんて言ってしまいます(ごめんなさい)。
ですがクラウド会計のソフトを使えば、そこがすべてワンボタンで済んでしまいます!
インターネットバンキングで提携している銀行なら(たぶんどこの銀行でも)
キーボードでポーンとキーを押せばあらら自動で連携、科目まで入力されてしまうのです。
すごいですね~
しかもそのデータは、どの端末からでも見ることができます。
事務所のパソコン
ノートパソコン
はおろか
スマホやipadでも。
つまり!税理士事務所の私たちも同じものが見られるのです。
しかも事務所にいながら私たちが修正もできる!!
いままでなら
お帳面をチェックして修正事項があったとしても
お客様に連絡して修正してもらって、
それから再度データを送ってもらって・・・と何度もやり取りが必要でした。
いまや同じ画面を見ながら離れた場所であっても、修正作業がその場で完了。
今回の確定申告では、時間短縮に大いに役立ちました。
お客様にとっても確定申告だからといって、そればかりに時間をかけるわけにもいきません。
時間は有限、できれば営業に時間を使いたい。
その通りだと思います。
クラウド会計はお客様、税理士事務所双方にメリットが多いのです。
こんなIT化の流れを加速するように、この春から経済産業省から補助金が用意されています。
その名も
「IT導入補助金」
ITツールを導入する事業者に対してその費用の3分の2を補助(
いま 二次公募が始まっています。
交付申請期間は平成29年3月中旬〜平成29年6月30日まで。
今がチャンスです。
ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。
私たちは、
クラウドの会計、給与ソフトだけでなく
勤怠管理や予約システムのソフト、
社内インフラとしてチャットワークスなどを組み合わせて
お客様の事務合理化を図るお手伝いをしています。
もちろん、ウチの事務所でも導入済みです。
「働き方改革」にも寄与していますよ(笑)。
税理士事務所でも取り扱っているところが増えているようです。
興味があればお問い合わせしてみてくださいね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年3月17日
土地を売ると支払う消費税が増える!?
今回取り上げるのもまたまた消費税です。
消費税は知っていないと損をするものが多数あります。
今回は「土地を売ると消費税が増えるかもしれない」話です。
まず消費税法では消費税が課されない取引、非課税取引が定められています。
税金計算上、課税取引なのか、非課税取引なのか、はたまた不課税取引なのか区別しなければなりません。
非課税取引と不課税取引、この違いも分かりにくいですよね。
(税理士でなければピーンとこないものです)
ともに消費税がかからない点では一緒なのですが、
取引の実態から消費税をかけないでおこうというのが非課税取引、
そもそも消費税がかかるにはふさわしくないのが不課税取引とされています。
たとえば税金を支払ったらさらに消費税はかかりませんよね。これが不課税取引です。
土地を売ったときはどうでしょうか。
土地を売ったときは消費税は非課税取引とされています。
なんだ、税金はかからないじゃないか。
いえ、ちょっとお待ちください。
税金計算上、土地を売ったときは影響が大きいので注意が必要なのです!
不動産業や医療業ではない一般的なサービス業や製造業の方は取引は売上は課税取引になることがほとんどです。
たまたま土地を売ったりして収入があると、収入のうち非課税取引の割合がぐっと増えることになります。
この非課税の割合が5%を超えるようでしたら、要注意です!
消費税は収入として受け取った消費税から、支払った消費税をマイナスすると納める税金が計算されます。
実は非課税の収入が全体の5%を超えるときは、消費税の規定があって、支払った消費税の一部が税金計算上マイナスにできないのです。
この場合「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の選択で税金を計算するのですが、
選択するということは税金の額が二つあるということです。
つまり選択を誤ると税金を納めすぎることにも!
たいていの場合「個別対応方式」を選択すると税金が安くなるケースが多いのですが、
経理事務が煩雑で、税金の知識が必要になってきます。
事務手数を取るか、節税を取るか、そこは事業主様からすれば悩ましいところです。
さらに個別対応方式を採用していても、非課税取引の割合が高いと計算上マイナスできるものがどーんと減っていく可能性があるのです。
その計算方法は複雑なので割愛します(苦笑)
そこで土地の売却があった年には、
「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」
を出すことで計算上マイナスできる消費税の減少を緩和することができます。
もちろん要件もあります。
また
その年に出しておかなければ節税が可能になりません(←ここがポイント)。
計算は複雑なので税理士に依頼したとして、
事業主の皆様にお願いしたいことは、
土地を売ったときは届けを出しておけば節税になる、かも
と覚えておいてほしい。
もし売ったときは、すぐ専門家に相談!!
(不動産仲介の方も相談するようアドバイスしてあげてくださいね)
知らなかった。
届けを出すのを忘れてしまった。
それで税金を納めすぎることがないよう、
信頼のおける税理士にすぐに相談してくださいね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年3月3日
確定申告!借りている事務所は経費と聞いたけど消費税はどうなの?
確定申告も後半に入り、いよいよ佳境です。
事務所に入ってくる日差しが眩しくて春を思わせます。
3月15日にはすっきりとした気持ちで春を迎えたいものです。
頑張りますよ~
さて
個人事業主様の確定申告では様々なことをご質問いただくのですが、
やはり経費性の有無、すなわち
「これって経費になるの~?」
がダントツです(笑)。
みなさん領収書だけはしっかりと集めていらっしゃいます。
利益の計算では、売上から経費を引いて求めるのですが、
税務会計の考え方として、「企業の営業活動による成果を獲得するために支払われるもの」が費用とされています。
簡単に言えば売上に貢献する支出、となりますね。
事務所を借りて事業をされる方は多いと思いますが、
ビジネス仕様の事務所は保証金などが高かったり、求める場所になかったりして、
マンションの一室を借りて使うなんてこともよくあります。
では支払家賃は経費になるのでしょうか?
答えはYES!
たとえ、自宅として一部を利用していても経費となります。
つまり住宅として貸し出されているような物件でもOK。
住居部分と事業部分が合理的な理由で区別できれば経費として認められるのです。
(どの程度まで経費となるかは税理士に相談してくださいね)
なるほど、事業所得を計算するうえでの経費にはなるのですが、
では消費税の計算ではどうなるのでしょうか?
消費税の計算は売上と経費の関係に似ています。
受け取った消費税から支払った消費税を引いた残りを納めるのですね。
さて、ご存知でしょうか。
消費税ではその性格から税金をかけないものが決まっているのです。
そういうものを
非課税取引
と言います。
そのひとつで問題になるのが借りたアパート。
住居用のアパートを借りたときは非課税取引となっています。
しかし
事務所を借りたときは課税取引になるのです。
「ん?それってつまり??」
住居用のアパートを借りれば納める消費税が増える、ということなんです。
先ほども申し上げた通り、消費税の計算は受け取った消費税から支払った消費税を差し引き、その差額を納めます。
なので支払った消費税が少ないと、つまり非課税取引だと、納める消費税が増えるということなんです。
いやちょっと待って。
たしかに住居用かもしれないけど、ウチは事業としてしか使ってないんですよ、それでも非課税扱いなんですか?
残念ながら、そうなってしまいます。
税金の世界で大原則に「実質課税の原則」があります。
このケースで何を「実質」とみるかですが、
賃貸借契約書の「用途」に「事務所用」と記載されていることとなっています。
もし納める消費税を少なくしようと思うなら、契約書から検討しておかねばなりません。
難しいところです。
消費税は私たち税理士にもなかなか手ごわいです。
知らないと大けがのもと、信頼のおける税理士にしっかり相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年2月7日
医療費控除は確定申告ですよ!
2月になりました。
確定申告です。
この時期の税理士は「ちゃんと終わるか心配で夜も寝られません」なんて言う人が多いです(苦笑)。
申告の期限が3月15日です、もう申告はできますからね!
ちゃっちゃとやっていきましょう。
サラリーマンなら確定申告は不要ですが
医療費がたくさんあるときは、確定申告をすれば納めた税金が還付されます。
多くの方が医療費控除は「10万円」と記憶されていますね。
さてこの10万円ですが、医療費が10万円あったら全額が控除になるわけではありません。
10万円を超える金額が控除されます。
もし年間の医療費が15万円だとしたら5万円が控除額になります。
控除には「税額控除」といって税金から引くケースと
「所得控除」といって所得から引いて、
そのあと税率をかけて税金を計算するケースの2種類があります。
医療費控除は後者の「所得控除」になります。
ウチは10万円ないからな~。
いえ、ちょっと待って!
所得が少ない方は10万円を下回ったときでも引けますよ。
所得が200万円を下回っているときはその5%を超える金額が控除できることになっています。
例えば150万円の所得の方なら
150万円×5%=75,000円
75,000円を超える金額が引けることになるのです。
とはいえ、医療費が10万円を超えることなどなかなかありませんね。
実は平成29年、今年から新制度が始まりました。
確定申告は残念ながら来年分からとなってしまいますが、
領収書は取っておかねばなりません。
ぜひ知っておいてくださいね。
それは
スイッチOTC医薬品
平たく言えば市販薬です。
今回の医療費控除の特例は
年間の医療費が10万円でなく12,000円を超えたら引ける
これなら活用できる人がぐっと増えますね~
月額1,000円以上使ったら引けることになりますね。
処方箋のある治療薬でなく市販薬も対象になる
今まで医療費控除とならなかったものでも
メタボ検診
人間ドック
予防接種
定期健康診断
がん検診
などをうけていれば市販の薬も控除の範囲に含まれるんです!
ただ申告には要件もありますよ。
セルフメディケーションのための薬でないといけないわけですから、一定の診断書などの添付が求められる可能性もあります。
また従来の医療費控除とダブルでは使えません。
10万円を超えるなら従来の医療費控除、超えないようならスイッチOTC控除と考えておけばよいかもしれません。
なにより、
しっかりと領収書は集めておきましょう!
お医者さんでもらったものだけでなく、ドラッグストアでもらった領収書も捨てないでね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2017年1月19日
一年の計は元旦にあり
少し遅いですが、年の初めのメルマガなので
明けましておめでとうございます!!
今年もどうぞよろしくお願いします。
さて、
一年の計は元旦にありといいますが
皆さんは計画などは立てられましたか?
どうぜ計画通りいかないから私は立てない!
そういう方も結構いらっしゃいますね。
かく言う私も得意ではない・・・
私もなかなか腰が重く、慎重なたちなので、計画通りに行くとは思ってはいません(苦笑)。
(名前も輝重と重いのですし・・・)
ですが計画は方向性を決めるのに役立ったり
深層心理に働きかける効果もあるかと思います。
今年はマザーリーフでも人材開発でご一緒させていただいている
原田教育研究所、原田先生直伝の
「原田式長期目的・目標設定シート」を使って
今年の目標と決めてみました。
もともと原田先生は中学の先生ですので
シートの最初の欄が面白い観点で始まります。
それは目標達成のための奉仕活動。
奉仕活動から決めるんですね。
自分のためだけに頑張るのではなく、人のために働き、人から応援されることでさらに頑張れる、
そんな原田先生のお考えがうかがえます。
社会人は家庭と会社、二つの領域での奉仕活動を決めていきます。
私は家庭では実家で一人住んでいる母親のケアにしました。
まだ老け込む歳ではないのですが、
一人でいると病気の時は心細いだろうし、
健康であってくれることが私たち子どもにとっても大変ありがたいですらね。
元気であるときに親孝行しておきたいと思います。
子どもたちを強制的に送り込んでは「孫の世話はつかれた~」とは言いつつも
まんざらでなさそうなおばあちゃんをみるとなんだかうれしいです。
会社では税理士会の会務です。
私は名古屋税理士会の租税教育部会に所属しているのですが、租税教育には思いがあります。
お金には入り口と出口があります。
税金の世界では国がどう集めるかが入り口で、どのように使うかが出口です。
出口にこそしっかりチェックをして賢い市民になってほしい、常々そう思っております。
だから小中学生だけでなく高校大学、そして新社会人まで、
税金についてしっかり学んでいただけるよう活動していきたいと思います。
原田式では心・技・体・生活についてそれぞれ目標を立てます。
目標を立てるにあたり成功分析と失敗分析をそれぞれイメージしておきます。
どんなときに成功したか、成功しているときはどんな状態か。
失敗したときはどうであったか。
そして問題点と解決策もあらかじめ想定しておきます。
両方をしっかり見つめながら行動を起こし、常に点検していくのです。
そうすることでより目標達成を確実にしていこうとするのです。
出来上がったシートは透明のソフトクリアファイルに入れて手帳に挟みました。
どこでもいつでも確認できるように!です。
一年後、どういう成果を出せるか、楽しみです。
事業をする人なら、ぜひ手を動かして紙に書いてみることをお勧めします。
意外と効果がありますよ!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2016年12月19日
法定調書の準備も同時並行。今年はマイナンバーの収集が大変!
年末調整とほぼ同時に進めていくのが法定調書の作成です。
こちらは1月末まで提出するものですが、年末調整と同じ封筒に資料が入って送られてきますし
今年はマイナンバーの収集もあるので同時に行うのが合理的です。
さて、法定調書ってなんでしょう。
法律で定められた書類。
はい、その通り!(当たり前)
税務署への提出が法律で義務づけられている文書(法定調書)は、全部で46種類あります。
主なものは以下のとおりです。
①給与所得の源泉徴収票
②退職所得の源泉徴収票
③報酬、料金、契約金、賞金の支払調書
④不動産等の使用料等の支払調書
⑤不動産等の譲り受けの対価の支払調書
⑥不動産等売買・貸付の斡旋手数料の支払調書
⑦公的年金等の源泉徴収票
この辺りはご存知の方も多いですよね。
また、法定調書は税務署だけでなく市町村に送られたりもします。
給与の源泉徴収票などがそれにあたります。
市町村に送られた源泉徴収票は、これをもとに住民税が計算されます。
そして、お勤めの会社に5月ごろ納税額が送られてくる仕組みです。
住民税の納付は、自分で納める普通徴収という方法と
会社が給料から天引きして納める特別納税という方法があります。
法律には特別徴収が原則とあるので、会社が天引きして納めることになります。
なんだか特別が原則で、普通がイレギュラーなんて変ですね(笑)。
これがマイナンバーで紐づけられて、夜のアルバイトなど副業をしていると
会社に税金額と所得が通知され、
「あれ?うちの会社はこんなにお給料払っていないのに」
とばれてしまうかもしれないのです。
マイナンバーの収集で大変なのが
「報酬、料金、契約金、賞金の支払調書」
「不動産等の使用料等の支払調書」
ではないでしょうか。
私たち税理士などのサムライ業や、広告業や原稿、講演などを頼んで年額5万円を超えて支払っているケース
が該当します。
一回の報酬が3万円だったりしても年に2回頼めば該当しちゃいますね。
マイナンバーは平成27年秋ごろ住所のある場所へ書留で送られました。
この時おくられてきたのが「通知カード」と呼ばれるもの。
人によっては平成28年、今年になってからですね、区役所等で個人カードに変更した方もいると思います。
これが「個人カード」とよばれるもの。
違いは身分証明の機能があるかどうかです。
通知カードは身分証明機能がないので、本人確認のため免許証などの提示が必要になってしまうのです。
だから
士業や大家さんの支払調書を提出するときは、この本人確認が大変。
そうそう、大家さんの支払調書も作る対象範囲が定められていますから知っておいてくださいね。
家賃や地代を支払っているからといって、全員分のマイナンバーを集めなければならないかといえばそうでもないのです。
でも、この判定はややこしいです。
もし支払うあなたが、個人事業主なのか法人なのかで変わってきます。
個人事業主なら、その事業が不動産業であるかどうか、また仲介業かどうかで変わってきます。
そして一年に15万円を超えて支払ったか、その金額は消費税込みかどうか、でも変わってきます。
支払った相手が法人か個人かでも変わってきて、その内容が家賃か権利金かでも変わってきます。
まぁ、とにかくややこしや~(苦笑)
ということで
やっぱりこういう時は専門家である税理士に聞いてみてください。
頼りになると思いますよ!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2016年12月3日
年末調整。今年はマイナンバーの収集がありますよ!
会社では年末調整の準備が始まっています。
事業主様、総務・経理の担当の方、お疲れ様です!
今年はマイナンバーの収集とその取扱いが初めての年で、いろいろと大変だと思います。
お勤めの方の場合、
「平成28年分 扶養控除等申告書」にご自身のマイナンバーと、
扶養家族のマイナンバーをすでに書いて、会社にご提出したかと思います。
この「平成28年分 扶養控除等申告書」、平成28年1月に書くことになっています。
実務では、意外とこの時期に書いていたりしているようですが(苦笑)。
だから、
今回の年末調整で税務署から送られてくる封筒に入っている「平成29年分 扶養控除等申告書」を使わないようにご注意くださいね。
というのも、新規の人以外は「平成29年分 扶養控除等申告書」にマイナンバーは書かなくてよいことになったのです。
当初はどこもかしこもマイナンバーを記入することになっていたのですが、
それではあんまりにも事務の方がつらいというわけで、
一度集めてちゃんと管理しているなら「もういいよ」となったのです。
「平成28年分 扶養控除等申告書」にはご自身のマイナンバーと、扶養家族のマイナンバーが書かれています。
大切な個人情報ですから、預ける側からすれば取り扱いが心配ですよね。
取り扱いを行う法人や事業主様には安全管理措置が義務付けられています。
もし、漏らしたりして犯罪に使われたら一大事ですから、しっかりと対応することになっているのです。
とはいえ、紙で預かれば鍵付きのキャビネットや金庫などに保管しなければなりません。
何年もたつとそのボリュームも膨大です。
ウチの事務所ではクラウドシステムを使って、紙ではなくデータベースで保管をしています。
これなら退職したり、法定の期限が来たときにワンタッチで削除ができるのです。
担当者が忘れないようにとアラームで知らせてくれる機能なんかもついています。
便利ですよね~!
マイナンバーの管理で様々なところでビジネスが創出されているようです。
もし、はて?
そう思ったら身近な税理士や社会保険労務士に聞いてみてくださいね。
専門的な見地から的確なアドバイスをくれると思いますよ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2016年11月24日
家や土地を買ったら、しっかりと残しておかないと。。。
突然ですが!
わが国では家が余ってきています。
私は子どもが生まれてからすぐに、中古ですが、マンションを購入していまに至っています。
では親世代はといえば、「いつかはマイホーム」の世代ですから、こちらも郊外に一戸建てがあって住んでいます。
つまり同居していない親子世代が別々に不動産を所有しているということです。
ということは、この先を考えると家が余ってくることは必至。
いえ、もう余ってきているのです。
時が過ぎ、親が亡くなり、私もこの世から去るでしょう。
その時残された家や土地はどうなるのでしょうか。
いったん相続されることが多いのですが、住む人がいなければ
家は使いませんので、では売ってしまおうかとなることもしばしばです。
不動産を売ったら、税務では譲渡するなんて難しく言うのですが、
利益が出ます。
これに税金がかかります。
その利益のうち、およそ1/4を税金として納めなければなりません。
結構な金額ですね。
ポイントですが、税金がかかるのは売った金額全部にかかるわけではありません。
利益にかかるのです。
では利益はどう計算するのでしょうか?
もともと買った金額や買うときの諸費用(こういうのを取得費用というのですね)、売った金額から取得費用を引いたものが利益となります。
建物など使って古くなると価値が落ちてくるものについては、減価償却といってさらに減らしていきます。
例えば、
土地が3,000万円、家が2,000万円、合わせて5,000万円で買った不動産があります。
これを7,000万円で売りました。
土地は減価しないので3,000万円、そのままです。
家は減価していますので、その分をさしい引いた残りが500万円
土地と家を買ったときに使った費用、不動産仲介や登記にかかる費用ですね、こちらが100万円
だとします。
そうすると
売れた金額7,000万円 - (3,000万円 + 500万円 + 100万円) =3,400万円
3,400万円に税金がかかります。その税金はおよそ850万円です。
ですが次のようなケースだと問題発生!
それは
土地や建物は先祖代々のもので相続でもらったもの
買ったけどその時の資料が紛失してわからない
こういう場合だと取得費用が分からないので、どう計算するかというと
売った金額の5%を取得費用にする、ことになっているのです。
そうすると
7,000万円 × 5% = 350万円
7,000万円 - 350万円 =6,650万円
これが差し引き利益になり、6,650万円に税金がかって、その金額はおよそ1,660万円となります。
大きく差が開いてしまいました。
覚えておいてください。
家や土地を買ったとき、残しておかねばならないのは買った時の資料一式です。
不動産は長い間動きません。だから不動産というのです。
だからこそ買ったときの値段や資料を取っておかねばなりません。
相続を経るとなおさら、分からなくなります。
いま親と同居している方、
将来相続が予定される方、
親が元気なうちに資料を集めておいてくださいね。
もちろん、自分が買った不動産も同じです。
将来のことを考えて、分かるようにしておかねば思わぬ税金がかかることもありますからね。
人間のアタマは忘れるようにできているそうですよ(苦笑)
このことは忘れずに、準備だけしておきましょうね。
取得費用の範囲や売却時の特例など専門的な要素で税金の額も大きく変わってきます。
そういう時こそ税理士の出番です。
信頼のおける税理士に相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!