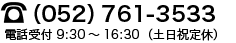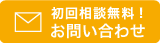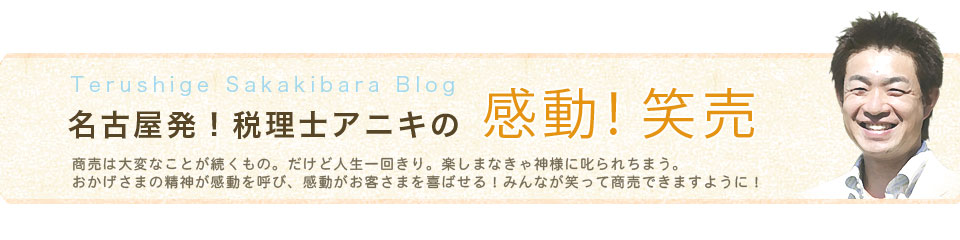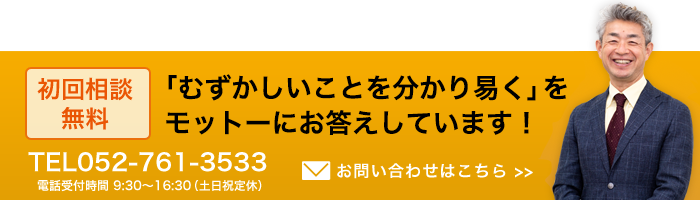2015年5月16日
賃上げ、新採用の会社さん、減税になります。忘れないで!
最近の新聞に『トヨタ自動車、純利益が2兆円超』との見出しが出ていました。
すごいですね!国家の税金歳入がおよそ50兆円ですからその25分の1ですよ。
利益が出たら、もちろんお給料も上げないと!
賃上げも政府主導で大手企業から始まっています。
もちろん税制も賃上げをする企業をあと押ししていますよ。
主なものは二つあります。
所得拡大促進税制と、雇用促進税制
と呼ばれるものです。
所得拡大促進税制は、前年より従業員への給料を増額したら、中小企業ならその増加分の10%の税金控除となります。
例えば、昨年の従業員へのお給料が総額で1億円だったとしましょう。
今年は1億500万円になりました。500万円の増額です。
そうすると500万×10%=50万円の税金が節税になります。
雇用促進税制は、前年より従業員数を増やしたら、増やした人員につき一人あたり40万円の税額控除となります。
例えば、昨年より3人従業員増やして新たに雇ったとすると、
40万円×3人=120万円の税金が節税になります。
要するに
給料を増やしたら…所得拡大促進税制。
人を増やしたら…雇用促進税制。
を使ってくださいということです。
雇用を増やせば、給料も増える、だから両方とも使えるんじゃない?
そんな疑問点、ごもっともです。
ただ注意する点ふたつあります。
まずは一つ目。
実はこの税制は、どちらか有利な方だけ選択して使うことになっているのです。
だから有利判定をして、どちらかしか使えません。
残念ながら「一粒で2度おいしい」とはならないのでした。
注意点の二つ目。
雇用促進税制を使いたい場合は、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに出しておかないといけないのです。
出しておかなければいけないのは前期の決算申告期限まで、
つまり、今期の最初の2ヶ月以内に提出しておく必要があるのです。
後になってでは遅い!
転ばぬ先の杖なので要注意です。
それから、新設法人であっても所得拡大促進税制は使えることになっています。
前年度は営業活動をしていないわけですから、新設法人ならほぼ100%対象になってきます。
ありがたいですね~
人を採用したい、お給料を増やしたい、
そう思った社長様、まずは税理士に事前に相談してくださいね。
いろいろと条件や上限額も付いているので、専門家に尋ねて活用していただければ大きく税金が減ると思いますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年5月1日
固定資産税が上がってる!?払い過ぎにはご注意を。
区役所からわが家のマンションの固定資産税の通知が来ました。
皆さんのところにも届いていることでしょう。
中身をじっくり見ました?
私は…見ましたとも!だって専門家ですから!
「去年よりも上がってる~!?」
名古屋市では3年おきに不動産評価の見直しを行っており、
今年はその評価替えで土地の価格が上がったのです。
うん納得。
しかし少し前に話題になったニュースが頭をよぎります。
去年の6月ごろです。
埼玉県の新座市で、老夫婦がお金の都合をつけるために自宅を売ったら、なんと27年間も固定資産税を払い過ぎた事実が判明しました。
しかし払い過ぎた税金は全部が戻らないと分かったというニュースです。
新座市ではこの事件をもとに知らべたら、なんと8億円も市民に返還しなければならないほど誤りがあったのです。
驚きです。でも極端な例ではあります。
税理士さんは何やっているんだ~。
固定資産税については、正直に申します。
実は私たち税理士も明るいわけではありません。
というのもわが国では申告課税方式と賦課課税方式の2種類で納税しています。
申告課税方式は、自分たちで計算をして、税額を計算して納めます。
税理士は会社や事業を営む方の申告をお手伝いをしているのです。
賦課課税方式は、役所がこれだけ納めてくださいね、と通知が来て納めます。
税理士はここに直接関係はしていないのです。
言い訳っぽいですが、普段あまり接する機会がない・・・。
とはいえ、新座市のニュースは非常にセンセーショナルですね。
誤って税金を請求したケースは総務省の発表によると0.2%。
およそ500件に1件の割合だそうです。
多いのか、少ないのか。
それは皆さんのご判断に任せます(苦笑)。
払い過ぎは困ります。
なぜこんなことが起きるのか。
最近こそITが普及し情報管理がしっかりしていますが、
少し前までは担当者からの申し送りで紙の資料で管理をしていました。
市町村合併などもあり、前任者の前任者までさかのぼっていき正誤を確かめるということは困難です。
また、相続があると
名義の変更、住まなくなったり、立て壊したり、新たに建て替えたり
などがあるため評価が変わってくる可能性があります。
通知が来たら、ぜひご確認ください。
まず税金がかかる不動産の名義、対象物は合っていますか。
面積は正しいですか、地目はどうなっていますか。
そしてその用途は合っていますか。
意外かもしれませんが、税の世界では基本思想は「弱者保護」です。
したがって実際住んでいる家と、ただ所有している家では税金は違います。
もちろん住んでいる家の方が安くなります。
小規模宅地の特例といって税金が軽減されているのです。
新座市のケースもこちらだったようです。
ですがこちらから直してね、と申告しないとそのまま放置されちゃいます。
「おやっ?」
そう思ったら、信頼のける税理士に相談してみてくださいね。
一緒に調べてくれたり、アドバイスをくれると思いますよ。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年4月16日
起業する方、事業準備している方に必要なこと~後篇~
皆さん、お花見は行かれましたか。
雨が多くてタイミングが合わなかった…そんな方も多いですね。
葉桜のこれから緑が増していく様も、また良いものです。
経営も一緒です。
さて前回からの続きです。
今回は最終回。まずは前号までのおさらいです。
起業する方、事業を始める方がやることは
自分ドメインをしっかりと立てる!!
ことでした。
事業を一本の木に例えてみて、その土壌は何なのかを言葉で表すことでした。
土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」
幹・・・会社のコンセプト
枝葉・・・経営のオペレーション
ここで土壌である思いや経営ビジョンを言葉で語ることができました。
次に行ったのがSWOT分析です。
自社(自分)の置かれている環境を「内部環境分析」と「外部環境分析」に分けて考えました。
これで自分が進む方向が整理されたと思います。
さて、SWOT分析が終わったら、いよいよ最終ステップ。
自分ドメインを言葉で表す
ことを今回は考えます。
私のバイブルである、
『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』
(光文社新書・海老根智仁著)
を参考に見ていきましょう。
海老根さんは、SWOT分析から3つの要素を明らかにせよといます。
1,対象となる市場はどこか(お客様となるのは誰?)
2,その市場(顧客)のニーズは何か
3,自社(自分)の強みは何か
これを言葉でつなげることが「幹」づくりになります。
幹づくり=会社のコンセプトづくり。
とても分かりやすい例があります。
コンビニ最大手のセブンイレブン、キャッチフレーズは・・・
そう!
「開いてて良かった」
この一言にセブンイレブンの会社の幹である事業ドメインが集約されています。
1,対象とする市場はどこか
⇒ ひとり暮らしの若者
2,その市場のニーズはなにか
⇒ 時間が節約できる、距離が節約できる
3,自社の強みは何か
⇒ 日用必需品に絞った徹底的品ぞろえ
まとめてみます。
『時間的利便性、および距離的利便性を充足させる
ひとり暮らしの若者のための
日用必需品に絞った徹底的品ぞろえのお店』
セブンイレブンを一言で表すとこうなるのです。
それが「開いてて良かった」のCMのキャッチフレーズとなりました。
ため息が出るほど見事ですね。
セブンイレブンがこ「開いてて良かった」というキャッチフレーズで世に出たとき、
日用品をそろえるのは個人商店とスーパーマーケットしかありませんでした。
個人商店は距離的には身近だが、商品の品ぞろえが限られていて、欲しいものは他店も回らなければならない。
スーパーマーケットは、品ぞろえは満足できても、遠かったり、開いている時間が日中だけで、自身の活動時間と合わない。欲しいとき開いていない。
こんな若者のニーズをびしっとわしづかみです。
それからのコンビニの成長は周知の通り。
いまや若者だけでなく、すべての人に利用されて大成功です。
さあ、いかがでしょうか。
自分の思いの詰まった「土壌」に自分らしい「幹」をたてられそうでしょうか。
簡単に言葉が出てくるわけはありません。
SWOT分析から何度も何度も、書いては消し、書いては消し、
じっくりと取り組んでください。
この準備をしておくと、どうなるでしょう。
事業の説明が明確にできます。
あなたの価値を相手にまっすぐ伝えられます。
自分のなすべきことが分かってきます。
自信を持って行動できます。
税理士はそんな経営者の傍らで、一緒になって力んでくれます、一緒に悩んでくれます。
税金の専門家ではありますが、経営者とともに歩く決意を持っています。
ぜひ、そんな場面ではお声かけくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年4月1日
起業する方、事業準備している方に必要なこと~中篇~
新年度が始まりました。
日本人としては元旦に一年の計を考えるかもしれませんが、
税務ではこの4月1日が新年度の始まり。
今年もさらに成長をしていきたいものですね。
さて前回からの続きです。
起業する方、事業を始める方がやることは
自分ドメインをしっかりと立てる!!
ことでした。
そこでまず考えること、確認することは
事業を一本の木に例えてみて、その土壌は何なのかを言葉で表すことでした。
おさらいをしましょう。
土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」
幹・・・会社のコンセプト
枝葉・・・経営のオペレーション
土壌である思いや経営ビジョンは言葉で語ることはできたでしょうか。
次に考えるのが環境分析です。
具体的にはSWOT分析を行います。
環境分析は大きく分けてふたつに分類されます。
それは「内部環境分析」と「外部環境分析」です。
内部分析は何をするのか。
それは
自社(自分)の強みと弱みを書きだすこと
強みと弱み、それぞれの要素をひとつずつ書きだしていきましょう。
ポストイットなどを用意して、一枚に一つずつ書くのもよいでしょう。
頭の中で考えているより、実際手を動かしてどんどん書いていくのが大切です。
強みとは、自社(自分)の持っている要素の中で、目標達成に役立つものです。
弱みとは、自社(自分)の持っている要素の中で、目標達成の障害となるものです。
次に外部分析です。
それは
自社(自分)にとって追い風と向かい風を書きだすこと
ビジネスで成功するには、タイミングや世間、社会の動きも重要です。
追い風とは、自社(自分)たちの取り巻く環境で、目標達成に役立つものです。SWOT分析では機会と呼んでいます。
向かい風とは、自社(自分)たちの取り巻く環境で、目標達成の障害となるものです。SWOT 分析では脅威と呼んでいます。
さあ、書けたでしょうか。
初めのうちは、一気に4項目を書くのは混乱するので、一日に一項目をつぶしていくのもよいでしょう。
SWOTとはそれぞれの英語の頭文字をとっています。
強み・・・Strength
弱み・・・Weakness
機会・・・Opportunity
脅威・・・Threat
分析の仕方ですが、縦軸に内部環境と外部環境をとります。
横軸に追い風と向かい風をとります。
縦横2つに項目をとり、クロスするように(十字を切るように)マトリックスを作ります。
そして
それぞれのクロスする部分で分析を行うのです。
強みと機会が重なる部分
自社(自分)の強みで取り組むことができる事業機会はないか
強みと脅威が重なる部分
自社の強みで脅威を回避できないか、他社には脅威でも自社の強みで事業機会にできないか
弱みと機会が重なる部分
自社の弱みで事業機会をとりこぼさないためには何が必要か
脅威と弱みが重なる部分
脅威と弱みが重なって最悪の事態を招かないためには
それぞれで具体的に、ぐぐ~~~っと深く考えるのです。
事業を始めるときは、
強みと機会が重なる部分を絶対に外さないようにしてください。
逆に脅威と弱みが重なる部分は撤退です。
SWOT分析が終わったら、次のステップに進みます。
私がバイブルのように使っている
『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』
(光文社新書・海老根智仁著)
では、これらの分析をまとめて一文にして表現するとあるのです。
これがまた素晴らしい!
いよいよ自分ドメインを言葉で表すことにチャレンジします。
それは次回にお話しをすることにします。
SWOT分析はぜひやってみてくださいね。
税理士は経営について税務だけでなくいろいろ勉強しています。
SWOT分析をするときも一緒に行えば必ず強い味方になってくれると思います。
「一緒にやってくれませんか」
お願いすれば
「はい、喜んで!!」
そうお返ししてくれると思います。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年3月20日
起業する方、事業準備している方に必要なこと~前篇~
確定申告も終わり、事務所の業務は「ほっ」と一息といきたいところですが、次の仕事へシフトチェンジです。
さ、がんばりますよ~
税務では税制改正が毎年行われます。
その施行日は年度始まりと決まっています。
つまり4月1日から始まるものが多いです。
春はすべてが新しく生まれ変わっていく季節。
新しいことを始めようと気持ちも切り替わります。
今年こそ起業をしよう、独立するぞ。
そう思われている方、素晴らしいですね。ぜひ応援させてください。
今まで税理士として、たくさんの方の開業、独立支援をしてきました。
そのなかで成功する人に共通していたことがあります。
それは
自分ドメインがしっかり立っている!!
事業を始めるとき、どんなきっかけ、目的で始めますか?
お金が儲かりそう、やってみたかった、夢をかなえたい、などいろいろです。
しかし成功している人は起業するときに、ちょっと立ち止まって自分と向き合い、
しっかりと「自分ドメイン」を作ってスタートしています。
なんとなくこんなふうにしたいではなく、言葉で自分の事業の価値を説明できるのです。
では自分ドメインの立て方を一緒に考えていきましょう。
自分ドメインを立てるのに参考になる本を一冊ご紹介しましょう。
この本は私も教科書として何度も何度も読み返し、起業しようとする方には必ずおススメしている一冊です。
『会社を替えても、あなたは変わらない~成長を描くための「事業計画」~』
(光文社新書・海老根智仁著)
まず「事業計画」を考えることから始めます。
事業計画は単にプランニングをするものと考えてはいけません。
「所詮計画でしょ」「実際はその通りいかないよね」
はい、その通りです。事業は失敗続きです。思ったように進むはずがありません。
だからといって、計画をおざなりに考えていいとはならないんですね。
いいですか、計画は、必ず実現するためにあると強く念じてくださいね。
ここが成功する人が違うところなのです。けっして計画倒れにしないのです。
海老根さんはその著書で事業計画を一本の木に例えています。
太い幹があり、そこから枝葉が伸びています。その根元には気をはぐくむ土壌があります。
ひと言で説明すると次の通りです。
土壌・・・経営者の「思い・経営ビジョン・企業理念」
幹・・・会社のコンセプト
枝葉・・・経営のオペレーション
まずはしっかりとした土壌があり、その上に幹がしっかりと立っています。
そして水をやり、太陽に当てることで枝葉が伸びていく。
まさに事業もその通りです。
順番を間違えてはいけません。
幹である会社のコンセプトがあやふやなのに、枝葉である商品開発、販促活動を議論しても意味がありません。
いかがでしょうか。
皆さまが事業をしていくなかで、
土壌はしっかりとしていますか。
「思い」は言葉で伝えられるでしょうか。
土壌がしっかりと整ったら、いよいよ幹づくりです。
幹づくりでは、しっかりと太いものを立てたいですね。
はい、ここでしっかりとした幹づくりをするためにしておかなければならにことがあります。
それが「環境分析」です。
もしあなたが木をしっかりと育てたいなら、どこに植えますか。
日当たりのよいところ、水はけのよいところ、空気の流れがあって風当たりはさほどでもないところ。
そう考えるでしょう。
事業でも同じことがいえます。
具体的に行うのがSWOT分析です。
事業を営んでいる方なら一度や二度はしたことがあるかもしれません。
では具体的には・・・。
それは次回にお話しをすることにします。
あなたの事業で
土壌はなんですか。
思いは何ですか。
ビジョンは何ですか。
言葉にして近くにいるビジネスパートナーにお話ししてみてください。
税理士はそんな時もしっかりそばで聞く準備をして、楽しみに待っていますよ。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年3月3日
住宅資金の贈与。順番を間違えないで。
確定申告も折り返しました。
泣いても笑ってもあと半月、2週間です。
がんばりますよ~。
さて、相続税の税制改正が27年よりはじまりました。
相続税対策をいろいろされている方がいるかもしれません。
今回の税制改正は増税も目的ではあるのですが、もうひとつ別に目的があります。
それは
お年寄りの財産を若い世代に渡すことを加速させる!
わが国では医療技術の発展、国民皆保険制度もあってお年寄りの寿命が延び、
一方で少子化が進んで人口ピラミッドがいびつになってきています。
財産を若い世代に移すことで生活を安定化し、
若い人に国を支えてくれるような仕組みに変えていきたいのです。
そこで若い人が住宅を取得しやすいようにと
親から子へ、祖父母から孫へ、住宅を買うための資金の贈与が非課税になっている特例があるのです。
贈与税の税率は高いですから効果は大きいですよ!
実は贈与の年によって税金のかからない金額は違っていて
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成27年 1,000万円
税金額にすると
231万円 ~470万円
も節税できることになります。
すごいですね~
利用しない手はないです。
しかし注意を要することがあります。
それは・・・
お金を贈与するタイミング!
たとえば次のケースでこの特例が使えるのか考えてみましょう。
① お金をもらった年に家を建てて住んだ場合
② お金をもらって翌年以降に建てて住んだ場合
③ ローンを組んで家を建て、住宅用にと親からもらったお金でローンを返した場合
いかがでしょう?
①~③のもらったお金は、住宅を建てるためにと、もらったお金です。
さて答えです。
① ◎
もらったお金には贈与税はかかりません。
② ×(△)
もらったお金には贈与税がかかります。ただある条件を満たしていればかからないこともあります。
③ ×
もらったお金には贈与税がかかります。ローンの返済は住宅を建てるための資金と税法は見ていないんですね。
え~~
住宅を取得するためのお金じゃーん。
そう言っても後の祭り。
早合点や自分判断は間違いの元。
贈与を考えている人は事前に、税理士に相談することをお勧めします。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年2月17日
アベノミクスで恩恵を受けた方!株の譲渡は確定申告で得することも。
2月16日から確定申告書の受付が始まりましたね。
すでに作成しちゃった方、さぁこれからという方、様々だと思います。
私たち税理士もこれからが本番、忙しい時期となります。
さてアベノミクスで株価が上がり、儲かった〜とおっしゃる方もたくさんいますが、納税はどうされていますか?
特定口座だから源泉税でもう納めちゃたよ、いや損したから関係ない、そんな方いらっしゃいませんか。
チョットお待ちください。
ご存じでしたか?
株は儲かったり損したりするものですが、確定申告をすることでその損を儲けで相殺できるしくみがあるのです。
基本的なお話しをします。
個人の所得税の計算は、総合課税といっていろいろな所得を合算して計算します。
所得はいろいろ種類があってそれぞれで計算して損得を判明させます。
生活資金を稼ぐものについては、総合課税の方法で損と得を相殺して計算するのが税法の考え方となっています。
ところが株の売買の儲けは生活資金を稼ぐためのものではないと考えられています。
モチロンこれで生きてますよ!というツワモノがいますけど・・・。
それはさておき
この時、税金は分離課税といって他の所得と切り離して計算することになっているんですね。
計算の仕組みとしては、株の売買取引は合算して正しい税金を計算することになっています。ひとつの特定口座では完結していても、別の口座を持っていて損失が出ていれば相殺することができるのです。
それでも
損が多い時は向こう3年間その赤字が繰り越せる!
のです。
ありがたいですね〜。
どんなケースかちょっと考えてみましょう。
例えば
A口座では100万円儲けが出ました。しかしB口座では300万損が出ました。
差し引き200万円の損です。
もちろん今年の税金はゼロです。
A口座で納めていた税金は還付されます。
さらに次の年に、A口座で50万円、B口座で100万円儲かったとします。
ところが前の年からの繰り越された赤字が200万円あるので、黒字が150万円だとしても税金はゼロ。
それぞれの口座で納めた税金は還ってきます。
そのときのポイントは2つ。
ひとつは確定申告をすること。
もうひとつは連続して確定申告をすること。
確定申告をしないと戻ってこないんです。
うわー、そんなこと知らなかったよ。
ご安心下さい。期限が過ぎていても遅れて提出すれば大丈夫です。
一般口座と簡易口座であれば期限後の申告でも、またやり直し申告でも大丈夫です。
一方、源泉税で納めている口座は期限後の申告は大丈夫なんですが、やり直し申告は受け付けてくれないんですね。
要注意です。
とりあえず、
株で損を出したら確定申告!!
信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年1月31日
子ども子育て新制度が今春から始まります
先日、愛知県知事より、認定こども園、認可保育園の審議をする諮問委員にダブル拝命されました!
税理士という資格を活かし、財務視点から申請事業をチェックするのが仕事です。
平成27年春から法律が変わって新制度が始まります。
それに伴い、県の職員さんたちと準備をしていきます。
よりよい保育環境を整えるために!
しっかりと役割を果たしていきたいと思います。
子どもたちは日本の未来を担う宝です。
すくすくと育ってほしいと強く思います。
さて、2015年度の予算が発表されました。
常々言っていることですが、
お金には「入口」と「出口」がある!
国の税収は「入口」。
どう使われるかが「出口」。
しっかりとチェックしていきましょうね。
予算総額は96.3兆円。
想像もつかないですねぇ。
「入口」である歳入。
そのうち税収は54.5兆円で、56.6%。
借金が36.8兆円で38%。
なんと4割近くを借金で賄うというのです・・・。
「出口」である歳出。
社会保障が31.5兆円で32.7%。
借金の返済に23.5兆円で24.4%。
借金を返すより13兆円も多く借りています。
どんどん雪だるまのように増えていくんです!
この借金を返すは誰でしょうか。
子どもたちです。
社会保障は31.5兆円と巨額ですが、そのうち7割は年金や介護、医療に使われています。
多くは「お年寄り」に使われている、といえるでしょう。
つまり・・・
子どもたちからお金を借りて、お年寄りを支える。
色々思うことがあります。
戦後の焼け野原から今の日本を作ってきた先輩には敬意と感謝をしています。
だから「今」がある。
でも・・・なんだか複雑です。
こんなことがありました。
消費税が10%に上がるのが先延ばしになり、
当てにしていた保育予算の原資がなくなってしまいました。
保育の現場では大騒ぎでした。
大臣の決裁が下りて予算が付けられ、ほっとしましたがその金額は5,100億円。
未来を担う子どもたちへの投資としては、あまりにも少ないと思いませんか。
子どもたちの未来を作る。
それは今を生きている私たち大人です。
なにかしら役割を果たしてきたいものですね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年1月17日
ひとり暮らしのおばあちゃんの相続税は要注意!
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。
皆様に「ほ~なるほど」「そうだったのね」「知らなかった」
少しでもお役にたてるような記事をご紹介していきますね!
さて年が明けて新しい相続税がスタートしました。
数年前からと変わる変わると言われながら、先延ばしとなっていましたが、
ついに実行されました。
非課税になるボーダーラインが下がるのですが、いままでより
4割!も引き下がる
のです。
相続税を支払う人は、100人いたら4人と言われていました。
今回の税制改正で6人に変わります。
100人のうち2人と考えればたいしたことない気がします。
しかし1.5倍!
に増えるときいたらびっくりしますね。
たかがふたり、されどふたり。
相続税がかかってくるのは都会に住んでいる方が多いと予想されます。
私の事務所のある名古屋市千種区、千種税務署管内では12~15人となりそうです。
そして要注意なのは、ひとり暮らしをしているおばあちゃんなのです。
「え!?」
年金暮らしでつつましく生きているんだよ。
税金なんてかかるはずないじゃん。
おじいちゃんが亡くなったとき税金はかからんかったがね。
ちょっと待ってください。
みなさんは次のケースに当てはまりませんか。
ひょっとしたら思わぬ税金がかかってくるかもしれませんよ!
・おばあちゃんは都会(大都市)に住んでいる
・おじいちゃんはすでに亡くなっている
・おじいちゃんが亡くなったとき相続税はかからなかった
都会に住んでいると、土地の値段は高く評価されます。
同じ50坪の家でも田舎に比べれば何倍にもなります。
配偶者から相続する場合は、配偶者特別控除といって1億6千万円までの財産なら税金がかからないことになっています。
人生を共に歩んで、共に支えあって財産を築いてきた夫婦なので、財産は共同で築いてきたと税法は考えるのですね。
だから、おじいちゃんからおばあちゃんへ相続があったときは税金がかからない場合が多くなるのです。
しかし、今度おばあちゃんが亡くなるとそういうわけにはいきません。
子どもが相続するとなれば、前述の共同で財産を築いてきたと考えられないため、その意味での税金の恩恵はありません。
おばあちゃんと同居していれば、小規模宅地の評価減といって税金の恩恵を受けることができるのですが、
所帯を持って転勤などで一緒に住んでいないとそれも使えません。
いや近くに住んでいるけれど奥さんや子どものことを考えて同居はしていない、なんてことも良くありますね。
亡くなったおばあちゃんに子どもが2人いたとすると、
基礎控除3,000万円
相続人2人で600万円×2=1,200万円
合わせて4,200万円までが非課税の範囲となります。
都会に住宅を持っていて
1坪60万円の土地が50坪で3,000万円
おじいちゃんが亡くなったときにもらった生命保険が1,000万円
自身の貯えが500万円
これですでに4,500万円。相続税がかかってくることになるのです。
いやいや、ありがちですよね!
相続対策は生前対策。
この機会に、親が元気なうちにこそ、一度財産評価をしておくことをおススメします。
税理士だけでなく、不動産鑑定士、司法書士、行政書士、専門家がチームになってワンストップで連携しているところなら安心ですよ。
私たちもそういう体制を整えています。
いつでも相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年12月17日
年末調整ですね
12月は師走です。
衆議院選挙が終わりましたね。
前半は国会の「センセイ」たちが走りました。
後半は私たち税理士の「センセイ」が走る番です(笑)。
私たち税理士事務所の仕事でこの時期にご依頼があるのが『年末調整』です。
年案調整を一言でいえば
サラリーマンの確定申告。
お勤めの方の税金は、源泉徴収と言って毎月給料から天引きされています。
しかしその金額は決められた一定額なので、
個人個人に合った正しい税金計算を行うのです。
源泉徴収は少し多めに天引きすることになっているので、多くの方が還付といってお金が戻ってきます。
戻ってくると、なんだかお年玉みたいでチョット嬉しかったりする人もいるんじゃないかなぁ。
さて、その源泉徴収制度ですが、日本では太平洋戦争の始まる直前、1940年(昭和15年)に導入されています。
政府からすれば、事前に、もれなく、税金を徴収することができるので、願ったりかなったりの制度なのです。
戦後の税制でも引き継がれ、現在に至っています。
今の法律では法人に源泉徴収する義務が課されているので、
サラリーマンの確定申告は、勤め先の会社がやらなければなりません。
政府はその事務手続きまでも省略できちゃっているんですね。
いちいち全員の分をやっていたら大変ですものね。
だから私たちのような専門家がいるのですけれど。
年明けの確定申告では
「あなたの今年の税金は36万円です。3月15日まで納めてください」
とお客様にお伝えすると
「えっ、そんなに」
とびっくりされたりするのですが、
サラリーマンの源泉徴収なら、毎月3万円の天引きなら実感として薄くなります。
年末調整をしたら源泉徴収票を発行します。
ここには1年間の納めた税額が書かれています。
一度じっくりながめて確認してみてください。
意外と支払っていますよ!
あなたが一生懸命働いて納めた税金です。
しっかり使われているか、点検してくださいね。
点検して納得がいかない、そういうときは選挙で意思表示してくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!