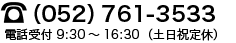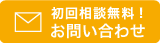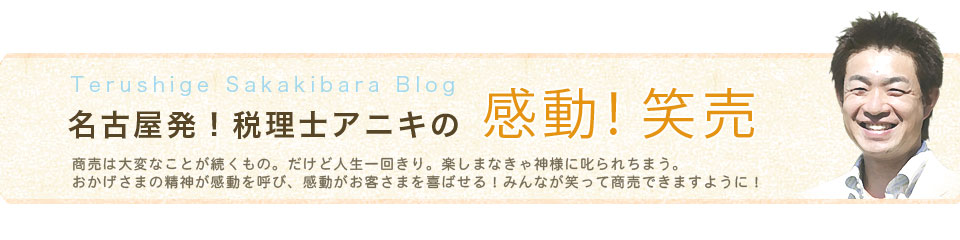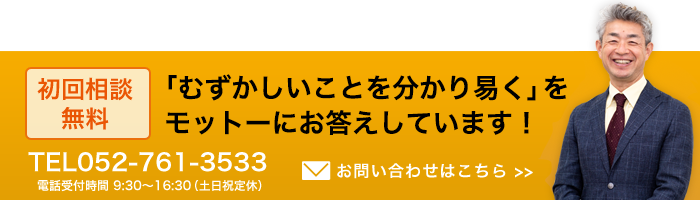2014年12月5日
あなたは、解けるかな?子ども税金クイズ
先日、税理士会の会務で区内にある大型スーパーにて「子ども税金クイズ」を行ってきました。
税理士会では子どもたち向けに税金の啓蒙活動として、子ども税金クイズ、租税教室などを行っているのです。
子どもたちがお小遣いでおもちゃを買ったとしても消費税はかかっており、子どもたちだって税金を納めているのです。
当たり前といえばそうなのでしょうが、市民が税金について正しく学ぶことはとても重要だと思っています。
今回のイベントは小学生相手で、事前にレクチャーをしてその後クイズを出す形式でしたが、なかなかの理解度でしたよ!
ちなみに出した問題を紹介しますので、一緒にやってみましょう!
さぁ、できるでしょうか。もちろん大の大人なら常識ですね!
では第1問。
Q.日本で消費税が始まったのはいつですか?
①明治 ②昭和 ③平成
続いて第2問。
Q.日本で救急車を利用した人はいくら払うでしょう?
①無料 ②ガソリン代実費 ③一律3万円
第3問へ行きますよ。
Q.国の税金についての法律を作るのは誰ですか?
①内閣総理大臣 ②裁判所 ③国会議員
それでは最後の問題。
Q.次のうち税金がかかるのはどれでしょう?
①ノーベル賞 ②宝くじの当選金 ③拾ったお金
いかがでしょうか。
全問スラスラ~っと解けましたか?
答え合わせをしましょう。
消費税が始まったのは、平成元年4月1日。
もう26年目なんですね。
最初の税率は3%でした。
救急車に乗ることはなかなかありませんから、ん?と考えちゃった人がいるかもしれません。
モチロン答えは無料。
すべて税金で賄われています。
ときにタクシー代わりに使うような人がると耳にします。それはちょっと困ったことですね。
税金の法律を作るのは、そう国会です。
子どもたちは「総理大臣!」と言うかと思ったのですが、いやいやしっかり答えていました。
間もなく衆議院の選挙ですね。
大人はしっかり権利行使をして、国会議員を選びたいものです。
さて、最後の問題は意外と引っかかったかもしれません。
税金がかかるのは、拾ったお金です。
宝くじにはかからないのですね。
というか、拾ったお金はまず警察に届けないと~!
イベントでは子どもたちと楽しく学んできました。
税金のことを学ぶのは、子どもだけではなく大人にとっても大切。
そして税金で考えてほしいことは、
「どう集めるか」ではなく「何に使うか」
だと思います。
この子どもたちによりよい社会をバトンタッチしていけるように、市民が賢くなって税金の使い道を決めていかねばなりませんね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年11月21日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その2
寒くなってきましたね。
わが家でもストーブを出しました。
前回は生命保険を支払ったときの税金のお話をしました。
今回は生命保険をもらった時のお話です。
生命保険をもらうときはどんなときでしょう。
・病気をしたのでもらった
・契約期間が満期になったのでもらった
・年金としてもらった
・お父さんの相続でもらった
こんなとき、税金のかかり方はいろいろです。
病気をしたのでもらったとき、税金はかかるでしょうか?
答えは「NO]。
税金は弱者保護の立場ですので、病気で苦しんでいるようなときにはかかりません。
契約期間が満期になったのでもらったときは、税金がかかります。
一回でもらうので「一時所得」と呼ばれます。
税金は「儲け」にかかります。
だから
もらったお金 - 支払ったお金(保険料) の差額にかかります。
しかしその差額に税率がかかるのではなく
そのうち50万円までは非課税なんです。
おトクですね~。
しかも確定申告でお給料と合算して計算するときは、さらに半分が非課税になるんんです。
すごい節税です。
年金で受け取ったときはどうでしょうか。
年金として受け取ったときは「雑所得」となります。
こちらはもらった金額と支払った金額の差額に税率をかけます。
一時所得と比べると、おトク感はないですね。
お父さんが亡くなったときにもらった生命保険は、ちょっとややこしくなります。
どういうことかというと
生命保険の保険料を支払った人
生命保険の対象になる人
生命保険をもらう人
この組み合わせで変わってくるのです。
オーソドックスなケースで説明しますね。
お父さんが自分が死んだら保険が出るようにと、自分で保険料を出していて
その後亡くなったとき家族に保険金が支払われます。
このときかかる税金は「相続税」です。
このとき相続財産を受け継ぐ家族(法定相続人と言います)ひとりにつき500万円までは税金がかからないのです。
例えば奥さんと子どもが二人いたのなら
500万円 × 3人 = 1,500万円
1,500万円までなら税金はかかりません。
どんなもらい方をしても、税金の話がついて回ります。
保険セールスマンと直接話すのは気が引けるわ~と言う方なら一度ご相談ください。
お気軽に相談してくれればきっといいことがありますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年11月4日
生命保険と税金のお話。そもそも基本編その1
朝晩は冷え込むようになりました。
季節は少しずつ冬に向かって移ろいでいきますね。
そろそろ保険会社さんから、あなたのお手元に、封筒やハガキでお知らせが届いていないでしょうか。
それは年末調整や確定申告に必要な資料となる
生命保険控除の証明書です。
支払った生命保険の額に応じて
税金計算のときに最高12万円まで除いてあげますよ、というものです。
「控除」ってのは、馴染みがないですよね~
なんか小難しいっていうか。
税金計算上の「控除」には2種類あって
所得控除と、税額控除とがあります。
所得控除は、税金計算のときに除いてあげますよ、というもの。
税金控除は、税金そのものをおまけしますよ、というものなんです。
税金計算の構造を説明しますね。
税金は「儲け」に対してかかるものなんです。
だから赤字のときにはかからない。
お給料だって「儲け」の一種なんです。
その儲けに税率をかけるんですね。
この税率は税金の種類によっていろいろです。
でもこの儲け全部に税金がかかるのではなくって
その人その人に応じて変わります。
例えば、お給料が同じで、独身の人と扶養家族が5人の人がいたとします。
その税金が一緒でいいでしょうか。
税の考え方として「弱者保護」がありますので、
扶養家族が多い人の方が税金は安くなるんです。
そのときに税金計算上、扶養家族の分だけ調整して税金を減らしてあげます。
その減らすのが「所得控除」となるのですね。
生命保険は、所得控除にあたります。
例えば100万円儲けがあった場合、
生命保険控除が12万円使えるとしたら、
100万 - 12万 = 88万円
この88万円に税率をかけて税金の額が決まるということになります。
今回は生命保険を支払った時の税金のお話でした。
次回はもらった時の税金のお話をしたいと思います。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年10月15日
ふるさと納税はしていますか?いま静かなブームのようです!
10月も半ばですね。
平成26年も残すところ3カ月を切りました。
子どもたちはもうクリスマスの話をしています。
年が明ければすぐに確定申告がやってきます。
節税は年内にしっかりと行っておきましょうね。
あなたは「ふるさと納税」をしたことはありますか?
ふるさと納税は、「ふるさと」に寄付をしたら、その寄付金額分の税金をおまけします!というもの。
2,000円は自己負担となるのですが、
「ふるさと」は自分で選べる
ことになっています。
え~~~、ふるさとを選ぶ?
変な感じですが、ここがいまのふるさと納税ブームのミソとなっているのです。
地方自治体が寄付を募ろうと、あの手この手で
寄付をした方へ、お礼の品を提供してくれているのです。
どんな商品があるのかしら、興味あるわ~というあなたのために
なんと商品が一覧となったポータルサイトもあるのですよ。
コチラ↓↓↓
http://www.furusato-tax.jp/
見ているだけで楽しくなっちゃいますね。
税金は国と地方公共団体に同時に行います。
その時に、今住んでいる場所へ納税するのではなく
自分の生まれ育った「ふるさと」を応援する、
これが本来の趣旨でした。
しかし
「ふるさと」を選べることにしたおかげで、
自分とは縁もゆかりもないところへ納税するケースも出てきました。
これには賛否があるようですが
税金の仕組みや納税に興味がわくという点は、税理士の立場からは評価してあげてもいいと思います。
それから
子育て世帯の方へ。
ふるさと納税で保育費が安くなるかも?!
地方の税収を上げるための「ふるさと納税」ですが、
税収を上げるためには消費税の配分も考えるといいかもしれませんね。
消費税は上がったといっても
その税収は国が多く持って行ってしまい、地方への配分は少ないのです。
ふるさと納税の情報はコチラ↓↓↓
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
あ、やっぱり!
所轄は財務省ではなく総務省だったのですね。
国会議員と財務省の皆様、地方への消費税の配分は思い切って逆になりませんか~。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年9月30日
印紙税でも節税
領収書にペタっと張る印紙。
お商売している人も、そうでない人も、おなじみですね。
平成26年4月から印紙税は減税になっていることはご存知でしたか?
いままで3万円以上支払ったときに貼っていたのを、
5万円以上になりました。
お店をやっている人は大丈夫ですか?
知らなかった~で払いすぎないように!
また
不動産の売買や、建設業の請負のときの契約書に貼る印紙税も軽減されています。
ところで、なんで税金を払うんだろう、て不思議に思ったことはありませんか。
印紙税が作られたのはかなり昔にさかのぼります。
いまから400年ほど前にオランダで始まったとされ、日本では1873年(明治6年)から始まっているのです。
へぇ~、古いですね。
歴史を感じます。
課税の趣旨としては、
商取引を行うのは、事業に伴うさまざまなインフラが整っていないとできませんから
(たとえば道路とか水道とか、ガスとか、電話線とかです)
お商売ができているということは、すなわちそういったものを間接的にサービスを受けているということになるわけです。
こういうのを難しい言葉で、経済的利益の享受なんていいます。
そうしたことから
ショバ代的な意味で、税金を支払ってください、と考えられています。
ショバ代的な意味といえば、法人住民税の均等割なんかが代表的なものですね。
利益が出ていなくても、事業主さん全員が支払わなくっちゃいけない。
現在では振り込みによる支払いが多くなりました。
実は現金で支払ったときは印紙を貼るのですが、
銀行で振り込んだときは印紙は不要です。
つまり税金は支払わないのです。
あら不思議。
ここは税理士としては悩ましいところ。
法律ができたときは想定していなかったのかもしれません。
時代に合わせて変えていってほしいところです。
でも印紙税が廃止なんて霞が関はしないだろうなぁ。
さらに
印紙税は契約書など文書に貼るのですが、
内容によって金額が変わったり、
貼らなくてよかったりします。
税務調査のときはけっこう指摘されます。
小売店で間違うと、追徴が結構な金額になったりするときもしばしば。
文書の書き方や、不用意な知識で税金を支払いすぎないように、信頼のおける税理士に相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年9月15日
金融・保険・不動産業の方、お急ぎください。節税の締め切り間近です!
消費税と言うのは本当にややこしい。
未来を予想して
あらかじめ届けを出すと節税できる!!
消費税には一般(原則)課税と簡易課税の方法があることは、以前にご紹介したところです。
消費税の計算は
売上にかかる消費税
経費にかかる消費税
その差額を計算して納めます。
ですが、そんなん面倒くさいわ~
という方、大丈夫です。
簡易課税という方法もあります。
なにより計算方法が二つあるということは、税金額が違ってくるのです。
簡易課税方式は経費にかかる消費税を、決められた割合で計算していきます。
たとえばサービス業の事業をしている方を考えてみますね。
売上 3,000万円 人件費を除く経費(人件費は非課税です)が 1,000万円 だとすると・・・
一般課税方式で計算します。
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費1,000万円 × 8% = 80万円
消費税は 240 - 80 = 160万円
簡易課税方式ですと、割合が50%と決められているので
売上3,000万円 × 8% = 240万円
経費3,000万円 × 50% ×8% = 120万円
消費税は 240 - 120 = 120万円
税金が大きく違ってきますねぇ。
ここからが本題です。
この割合を「みなし仕入れ率」というのですが、平成27年4月以降から変わることになっているのです。
まだ先やないか、ダイジョーブ。
とんでもない!
金融業・保険業 60% ⇒ 50%
不動産業 50% ⇒ 40%
影響を受けるのはこの方たちです。
優秀な保険営業マン、不動産の仲介業をしている方は要注意!
マイナスできる消費税が減るので
つまり増税になります!!
しかし、なんと抜け道があるのです。
この9月30日までに「消費税 簡易課税制度 選択届書」を出すと、
3月決算の法人なら、29年3月までいまのみなし仕入れ率でいいよ、となっているのです。
提出期限が迫ってます!
届をうっかり出すのを忘れたら、2年間の消費税を払い過ぎることに!!
ただこの届けを出せるかどうかは、ややこしいので
信頼のおける税理士に相談してくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年8月30日
贈与税が1,500万円までかかりません!?
さて今週で長かった夏休みも終わり、来週から子どもたちは学校へ通います。
ほっとするママたちも多いことでしょう。
わが家にも小学6年生と2年生の子どもがいます。
6年生になった娘は女子中学へ行きたいと目下塾通い。
夏休みだというのに毎日勉強に頑張っています。
親ができることといえば、見守ること、そしてお金を出すこと(苦笑)。
日々の生活で学校や塾に支払った教育費は、もちろん税金の対象にはならないのですが、
一気にまとめて渡すと要注意!
贈与したものとして贈与税がかかってしまうんです!
なんで~と思うでしょうが、税務署は家族の間でもまとまった資産の移動には税金をかけるのです。
贈与税は累進課税といって、上げるものが多くなるにつれ税率が高くなり、支払う税金が多くなります。
うっかり大きな金額を動かすと、びっくりするような税金を納めないという羽目に。
くわばら、くわばら~
たとえばおじいちゃんが高校、大学進学をまじかに迫った孫のためにと、
貯金を取り崩して1,200万円をあげたとします。
するとお孫さんに、贈与税が320万円かかってしまいます。
せっかく1,200万円もあげたのに実際に手に渡るのは880万円なんて、納得いかないですね。
ということもあって
昨年(25年)の税制改正で、子や孫に教育費として一気にお金をあげても税金がかからないことになったのです。
その金額はなんと
1,500万円!!
税金にして475万円も節税になります。
ではその対象になる教育費はどんなものがあるのでしょうか。
学校への
・入学金
・授業料
・入園料
・保育料
等のほかに
・修学旅行費
・教科書などの学用品
・学校給食費
もOKです。
さらに
塾や習い事など学校以外で支払うものも対象になります!
学校以外への支出は500万円までという上限はありますが、総額で1,500万円までは変わりません。
おじいちゃん、おばあちゃんがいるご家庭の皆さま、
たとえ離れて住んでいても、家族仲良く過ごすことが大切ですね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年8月20日
子育て給付金はじまっています
今年の4月に消費税が上がりました。
同じ給料であれば使えるお金が減る訳ですから、子育て家庭には大きな痛手と言えます。
給料が上がればいいんですけどねぇ。
たとえば40万円の月給でしたら、正味の使えるお金(可処分所得と言います)はいくらになるかというと・・・
消費税が5% → 可処分所得は38万円
消費税が8% → 可処分所得は37万円
なんと1万円も減るのです。
ということで、政府は臨時的に子育て世帯にお金を給付することにしたのです。
正式には「子育て世帯臨時特例給付金」と言います。
中学生以下の子ども1人につき現金1万円が支給されます。
2人お子さんがいれば2万円、3人いれば3万円となります。
お住まいの市区町村に申請すればもらえますので、
ぜひお忘れなく申請をしてくださいね!
ここで知っておいてほしいことが一つあります。
市町村の課税はその年の1月1日を基準にして判定しています。
固定資産税や住民税が代表的な例です。
中学生以下が対象とされていますが、
お子さんが現在高校1年生でも支給されます。
それから注意してほしいことは
今年になって引っ越した
事情があって現在別のところに住んでいる
この場合は前の住所地での申請になります。
申請の締め切りがは早い自治体だと9月のところもあるようです。
申請を忘れてもらい損ねた~ってことがないように!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年8月13日
葬儀費用は相続税計算のときどうなるの?
皆さまはお盆はいかがお過ごしですか。
私は実家に子どもたちを連れて過ごすことにしています。
父は66歳で8年前に他界しました。
小学校6年の娘は少しだけ記憶の残る3歳、小学校2年生の息子はまだママのおなかの中でした。
愛情豊かな父でしたから、孫たちが遊びに来てくれて大いに喜んでいるのではないかと思います。
お盆は久しぶりに家族が集う時期でもあります。
家族がそろうと相続の話が出ることも。
相続は亡くなった時始まります。
相続税はその方(相続人といいます)の亡くなった時、お持ちの財産に税金がかかります。
しかし相続財産全部にかかるわけではありません。
かからない部分もあります。
お葬式の費用は相続税計算のときにどうなるの?
答えは
「相続財産からマイナスできる」
ではマイナスとなるものは次のうちどれでしょう?
・お葬式の会場費
・お通夜やお葬式で出したお弁当やお菓子、お茶
・お手伝いいただいたご近所さんへの心付け
・お葬式に来ていただいたお寺さんに支払ったお布施
・戒名料
・火葬費用
・納骨の費用
・ご遺体の運搬にかかった費用
・会社で行った大規模な葬儀代
・初七日の法事
・49日の法事
・香典返し
・お墓の費用
さて、いかがでしょう。
マイナスの対象にならないのは
初七日の法事
49日の法事
香典返し
お墓の費用
この4つです。
大規模な社葬でもマイナスになるのです・・・意外ですねぇ。
もちろん領収書などもらえない、お寺さんへのお支払いやご近所さんへの心付けはしっかりメモすることで認められます。
では個人が受け取る香典は相続財産にプラスするのでしょうか。
税法の基本理念に弱者保護があります。
香典は「死者の霊に手向けるお香の代金」であり
「葬儀を出す家庭への経済的負担減」の意味合いもありますので、
税金はかかりません。
最後に、
お墓は亡くなってから建てるとマイナスにはならないのですが、
生きているうちに建てると財産マイナスになります。
とはいえ、そんなこと家族からは言いにくいでしょうから
気の置けない税理士に代わりに言ってもらうよう頼んでみましょう(笑)
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2014年8月6日
簡易課税方式は税金が安くなる?
消費税計算は二通りの計算方式があります。
一つは「原則(一般)課税方式」。
もう一つは「簡易課税方式」。
さて、計算方法が二つあるということは、どういうことでしょうか?
答えは
「支払う税金の額が違う!!」
ということなんです。
驚きですねぇ。
ぜひ安い方を選択したいものです。
一般課税は売上にかかる消費税から、経費にかかる消費税の差額を支払う消費税として計算します。
簡易課税は差し引く消費税を、実際に支払った経費ではなく、業種に応じた概算経費から計算するのです。
たとえば、売上が3,000万円、経費が2,600万円(うち人件費が1,600万円…人件費は非課税です)の美容院を考えてみましょう。
一般課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
経費で支払った消費税 (2,600万円-1,600万円)×8% = 80万円
支払う消費税 240万円-80万円 = 160万円
これが簡易課税ですと
売上で預った消費税 3,000万円×8% = 240万円
ここまでは同じです。
サービス業の概算経費率は50%なので
支払ったとみなされる消費税 (3,000万円×50%…これが概算経費)×8% = 120万円
支払う消費税 240万円-120万円 = 120万円
なんと40万円も差が出てしまいます。
これはびっくり、大きいですね!
駄菓子菓子(だが、しかし)
税法は以前にもお話ししたように弱者保護ですから、どの事業主様でもいいわけではないのです。
売上が5,000万円以下の事業主さんだけが簡易課税を選択できるのです。
ここにさらに落とし穴があります。
一般課税にするか簡易課税にするかは、前の年の間に税務署に届けを出した時に限られるのでご注意を。
決算のときに、「今年はこっちの計算方式にするわぁ」と決められないのです。
あら、残念。
しかも簡易課税を選択すると最低2年間は簡易課税方式で計算しなさい、と縛りもつくのです。
消費税を節税しようとするなら、向こう2年をしっかりシュミレーションが必要となります。
払いすぎにご注意です。丁寧に説明してくれる税理士と相談してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!