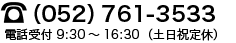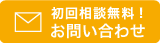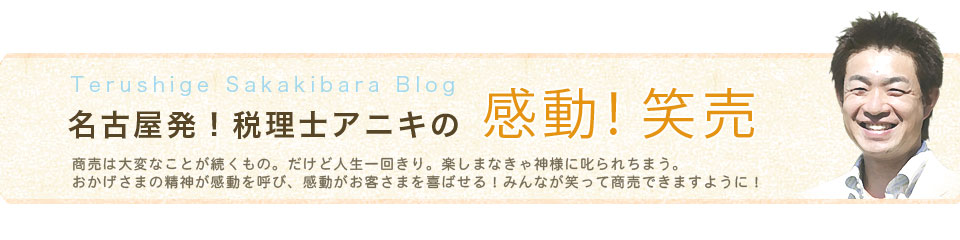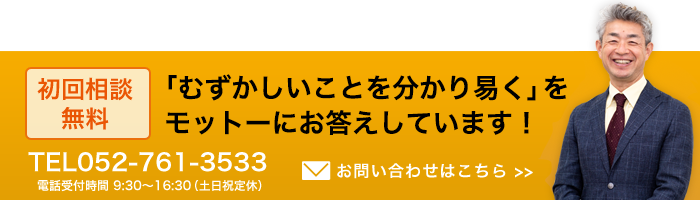2021年7月16日
カードでたまったポイントで買い物したら
コロナ禍で新しい生活様式が徐々に進んでいるかと思います。
その中で買い物へ行かず、配達やネットショッピングで済ませることも多いでしょう。
ネットでカードを使ってショッピングするのが不安で、引き渡し時に現金払いを選んでいたのが、今は昔ですね(笑い)。
クレジットカードで買いものをすると様々な特典が付きます。
今回はその得点の一つ、ポイント還元についてです。
ポイントをもらった時、使った時の会計処理は
事業をしている方のケースでお話しします。
会社で作ったカード、事業専用で作ったカードで、様々な買い物をした場合ポイント還元がされます。
その時の会計処理ですが、もらった時とポイント還元を使った時に分けて考えます。
ポイント還元をもらった時。
ここでは会計処理はありません。そのままにしておきます。
ポイントを使った時。
会計処理が必要になります。
11,000円(税込み)の消耗品を買って、5%分、550円分のポイントを使ったとしましょう。
考え方はふたつあり、ポイントを「収入」としてとらえるか、
「値引き」としてとらえるかに分かれます。
前者が原則的、後者が例外的となります。
①ポイントを収入とする場合
消耗品11,000円(税込み)を購入し、550円分のポイントは雑収入として処理します。
仕訳では
消耗品11,000(消費税課税)/現金預金10,450 雑収入550(消費税仕入対価の返還)
となります。
「雑収入」については、消費税法上、「仕入の対価の返還等」に該当します。
つまり、消費税の計算では課税仕入のマイナスとして取り扱われます。
②ポイントを値引きとする場合
消耗品10,450円(税込み)を購入したとして処理ます。
仕訳では
消耗品10,450(消費税課税)/現金預金10,450
となります。
税務では
「ポイント支払(キャッシュレス還元)」なのか
「ポイント値引き」かで取り扱いが異なります。
つまり、税込み11,000円からマイナスするのか、
原価である税抜き10,000円からマイナスするのか、
区別しているのです。
ポイント支払(キャッシュレス還元)であれば、ポイントは収入として取り扱い、
ポイント値引きでれば、値引きとして取り扱います。
消費税計算に影響があるため、ここは要注意です。必ずレシートや証ひょうで確認しましょう。
ややこしいですね。
(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_02.pdf
ポイントがたまったからタダで買える?
もし買い物が10,000円で、ポイント10,000円分を使ったら、お金を支払うことはないです。
その意味では「タダ」ですね!
とはいえ、会計の処理は原則的には雑収入で取り扱うため、経理処理は必要です。
一方で、
例外的処理も認められているため、そちらを採用すれば記帳は必要がないことになりますが、
それが認められるには、同じ会計処理を継続して行う必要があります。
記帳されないからといって、私用のものを買ってはいけません。
ポイントは会社のものですから「業務上の横領」となります。
これぐらいならいいだろう、はダメですよ。
もちろん役員であっても同じです。
経営者の皆さんはポイント制度の利用については、コンプライアンスをしっかりとしてくださいね。
面倒くさい処理ですし、コンプライアンスの問題もはらんでいます。
専門家である税理士に確認しながら、適切な会計処理をしていきましょうね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年6月11日
開業時の支出、それは経費(その②)?
前回の記事では、開業時の支出について、
そもそも「経費」とは、会計上の「費用」と税務上の「損金」に分けて考える必要がありますよ、
とお伝えしました。
そして会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げました。
今期は「開業費」を取り上げてまいります。
開業費は、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合とで取り扱いが変わります。
開業費とは
個人で事業を始める場合は、
開業費は「開業するための費用」でありますが、
「開業前の支出」で「事業開始するために必要な支出」となります。
例えば、次のような費用です。
- 切手など通信費
- 消耗品や水道光熱費
- 名刺やチラシ
- HP作成費用
- 打ち合わせの費用
- 移動のための交通費
事業開始のため必要だと証明できれば「開業費」となります。
法人と違って、その範囲は緩く、経常的に発生する費用も対象となります。
ただ、開業前といっても、1年も2年も前までさかのぼって経費になるわけではありません。
所得税の申告は暦年基準でもあり、おおむね3~4か月、長くて半年くらいまでなら損金として認められるでしょう。
事業経費として明瞭であり、支出の時期が合理的なら、一年前くらい前まででも損金となる可能性もあります。
一方、会社を設立して事業を始める場合は、
開業費は「設立してから事業を開始するまでに、特別に支出した費用」となります。
会社を設立するには、箱作り、つまり登記をしてから事業がスタートしますので、
登記後に発生する特別な費用が「開業費」となるのです。
開業準備のために特別に支出した費用のうち、
事務所家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、
開業準備のために特別に支出した費用と認められないため、開業費とせず、
経常的に発生する費用として処理します。
そのほかの経費
創立費や開業費に分類されない経費もあります。
例えば、販売するための商品購入なら「仕入」
車や機械などであれば「固定資産」
として経理します。
損金となる時期
創立費や開業費は、会計上では繰延資産として、
発生した年度から5年以内で一定額を費用として経理することとなっています。
これを「償却」といいます。
しかし、税務上は中小企業なら、任意の時期に損金経理すればよいことになっています。
つまり、設立当初の利益があまり見込まれない年度においては費用化せず、
徐々に利益が増えていったタイミングで償却すれば、利益を圧縮でき節税となります。
開業時は知識不足で、処理を誤ってしまい
節税できたのにかなわなかった、なんてことにならないよう
信頼のおける税理士さんに相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年5月11日
開業時の支出、それは経費(その①)?
よし!一念発起、サラリーマン人生ではなくて起業しよう。
準備を始めてみたものの、開業前にも、いろいろお金もかかります。
「これって経費になるのかなぁ」
そんな疑問もわいてきます。
開業にかかる費用については、個人事業主として始める場合と、会社を作って始める場合で、取り扱いが少し違います。
そもそも「経費」とは
「これって経費になるよね?」
と何気なく使っているこの「経費」という言葉は、会計上と税務上で分けて考える必要があります。
「経費」は会計上では「費用」、税務上では「損金」として取り扱います。
売上-費用=利益(儲け)
これを税務上で考えると、言葉が変わります。
益金-損金=所得(税務上の儲け)←課税されます
で、何が違うの?
費用になるけど、損金にならない
ものがありますよ。
つまり、会計上は費用だけれど、税務上は損金になりませんので、税金はかかります、ということです。
「え~~~っ!?」そんなアホな。
実務上はこんなことが起こりえますので注意してくださいね。
事業を始めるのですから、皆さん儲けを出したくて行うわけですが、
費用になるのはもちろんのこと、税務上でも損金になるかどうか、必ずチェックしておいてくださいね。
そこで、事業を始めるときにかかった費用のお話です。
開業費を考えるとき、個人で事業を始める場合と、会社を作って事業を始める場合と区別して考えます。
事業を始めるときにかかる費用は「開業費」のほかに「創立費」、「それら以外」に分けられます。
今回は、会社を作って事業を始める場合の「創立費」を取り上げたいと思います。
創立費とは
会社を設立するには、司法書士さんに頼んで、登記を行って初めて事業ができる状態になります。
創立費とは、会社の設立前の支出で、設立のために要した費用をいいます。
つまり箱作りにかかる費用です。
だから、個人事業で始めるときは発生しません。
例えば、次のような費用です。
- 定款の作成のための代行手数料
- 定款の認証手数料
- 印鑑証明書の発行手数料
- 設立登記時の印紙代
- 設立前の事務所賃借費用
- 銀行の口座開設手数料
- 事務用消耗品(名刺、印鑑、封筒作成など)
- 打合せ費用や交通費
創立前の支出は
会社を設立する場合、設立する前の支出はどうなるのでしょう?
法人税基本通達2-6-2にこのように規定されています。
「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、
当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。
ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益
又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない」
ホント、税の条文は本当に分かりづらいですね。。。
どういうことかというと、
「設立前なので、主体がないため経費はありえんけど、
最初の年度の損金として特別に認めるよ」
だけど、
「特例だから常識的に考えてね」
それから、
「個人で事業している方が法人成りする場合はダメよ」
と言っているのです。
常識的に考えてとなれば、設立前1~2か月くらい前までなら損金として認められるでしょう。
もちろん、事業との関連性が認められないと経費ではありません。
実際に税務署の調査が入ると、経費である事を証明するすべての証拠が必要となります。
そのため、経費として申請する場合はしっかりと事業に必要な費用だったと正しく証明できる必要があります。
領収書があればよい、ということではあませんから、くれぐれもご注意願います!
開業時は、税務について無知なことも多いでしょう。
インターネットなどで情報を得るだけでなく、
信頼のおける税理士さんに相談してみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年4月13日
コロナ禍での人材戦略を応援する税制
暖かくなって春爛漫ではございますが、相変わらず新型コロナは収まりそうにもありません。
さて、税制は年明けから春の国会で決まります。
コロナ禍の税制ということで、多くの制度が盛り込まれました。
国会と税制
税制は、毎年春の国会で審議されます。
日本国憲法第84条に、
「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」
と規定され、必ず法律にすることになっています。
為政者が、解釈変更や勝手な思い付きで、税金を変えることはできません。
国民にとって、税は「公平」でなくてはなりませんから、必ず国会で審議して法律として実施されます。
これを租税法律主義といいます。
とはいえ、時の経済状況などを反映して、政策誘導がなされるものでもあります。
令和3年度の税制改正は、コロナ禍における影響で、国民の生活を維持するため、
- 失業しないこと
- 職を得ること
- 給料をしっかり保証すること
を目的に設計されています。
企業が行う人材確保や雇用、お給料の引き上げに関して、かなり優遇される制度となりました。
人材を確保したら税金をおまけします
従来あった所得拡大税制の見直しで、新たにできたのが、「人材確保等化促進税制」です。
これまでは、継続して雇用している方の賃上げをすると税金をまけるよ、
としていました。今回の税制改正では、
新たに雇用を増やしたら(新卒・中途問わず)税金をおまけします
に変わります。
具体的な要件として
「継続雇用者のお給料が、前年より3%増加」
が
「新規雇用者のお給料が、前年より2%増加」
に変わります。
給料上げたら税金をおまけします
こちらは従来からあった税制になりますが、
要件緩和により、今まで以上に使える方が増える可能性が高いと思います。
「継続雇用者のお給料が、前年より1.5%以上増加」
が
「企業全体の給与の総額が、前年より1.5%以上増加」
に変わります。
いまの社員さんのお給料をアップした場合
または
ベースアップしなくても、新たに人を採用した場合
が、該当しそうです。
人材を人財に
コロナ禍の前までは、企業さんは即戦力を求めてきました。
特に中小企業では、採用数も限られますし、即戦力はありがたいところです。
でも、もう一度考えてみましょう。
中小企業では、採用数が少ないからこそ、
- 長きにわたってお勤めいただき
- 社長の大切にする価値をしっかり理解して
- わが社のお客様を大切にする
こんな人材が欲しいですね。
人材を育てて、人財にする。
これぞ、社長の仕事ではないでしょうか。
税制改正で優遇が受けられるこのときが、
人財戦略を新たに見直す時期かもしれませんね。
詳しい情報は、信頼のおける税理士さんと相談して、
これからの人財戦略に役立ててくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年3月10日
専従者給与と、青と白
榊原事務所では確定申告も追い込みです。
最後のラストスパートに入りました!
とはいえ、世の中では緊急事態宣言の影響で、申告期限が一か月延長され4月15日、
振替え納税の手続きをしていれば、納税期限は5月末日、と余裕はあります。
少しホッとしますね。
専従者給与って
個人の事業をしている方ですと、家族経営をしてる方も多いです。
男性の事業主なら妻や兄弟、時には母に仕事を手伝ってもらう、こともありますね。
しかし個人事業だと、原則、
家族に支払う給与は経費になりません
え~~!?
私は無償で働いてるわけじゃないよ!
社会に出て同じ事すればお給料もらえるのに!
そうですよね、なんだか納得いきません。
ですので、税法上も一定の要件さえ満たせば、経費として認められます。
15歳以上の生計を同一にしている家族従業員であって、もっぱらその事業に従事していれば、
専従者として経費対象になるのです。
ポイントは、
- 生計が同一(どういつ)であること
- もっぱらその事業に従事していること
生計が同一とは、お財布が一緒の家計で生活していること、とお考え下さい。
仕送りで生活している大学生なんかは生計同一となりますよ。
もっぱらとは、専従者の漢字を見て分かるように、ほぼその事業に従事していることです。
ですから、家族でも、
アルバイトをいくつも掛け持ちしている、
週に一日だけ手伝っている、
では要件を満たさないことになります。
少なくとも事業期間の半分を超えて働いていることが必要です。
青と白の違い
個人の確定申告は、青色申告と白色申告の二つに分かれています。
専従者給与も青色と白色では、異なった取り扱いになっているので注意してくださいね。
青色の場合、「青色専従者給与の届出」を出す必要があります。
うっかり間違いやすいのが、
「青色申告の届出」を出していても
青色専従者給与に自動的になるわけではないのです。
「青色の届出を出したから~」
ではうっかりになっているかもしれませんよ。
その代わり、青色専従者であれば、支給する金額は、
従業員さんと同様に、自由に決められます。
ただし、あまりにも特別扱いの金額だと、
税務署から「ちょっと待った」がかかるので気をつけましょう。
白色の場合、届出を出す必要はありません。
申告書に金額を記入するだけでよいです。
しかし、金額の上限が決められていて、
配偶者(夫または妻)なら86万円、
それ以外の家族なら50万円、
となります。
そして白色の場合は、事業期間の半分を超えてではなく、6か月を超えて働いていることが必要です。
例えば、4月オープンの事業であれば、12月まで9か月あります。
青色なら半分の4.5か月を超えて働いていれば専従者となりますが、白色だと6か月を超えて働いていないと専従者になれないのです。
また、専従者としてお給料を渡すと、その金額いかんにかかわらず、
配偶者控除や扶養控除ができないことになります。
ダブルで控除ができないということです。
いろいろとややこしいですね。
個人の事業主さんだとご自身で申告されている方も多いでしょう。
とはいえ、うっかりで税金を払いすぎたり、追徴をもらわないように
信頼のおける税理士に相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年2月12日
節税ってどういうこと?
確定申告の時期がやってまいりました。
すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、
緊急事態宣言が出されておりますので、申告期限が一か月延長され、
4月15日、となっております。
とはいえ、榊原事務所では、従来の3月15日を目標に申告を終わらせますよ!
お客様の節税のイメージ
確定申告するお客様は、なぜ税理士に依頼するのでしょうか。
専門用語がよく分からない
面倒くさい
計算が合っているか不安だ
損をするかもしれない
など、いろいろあると思います。
そのなかで、よくお願いされるものは、
「節税したい」
です。
税金を払い過ぎたくない、
よ~~~く、分かります。
私だって、払い過ぎたくない一人です(笑)
でも、ちょっと待ってください。
「節税」って何?
そもそもの定義やイメージが、お客様と私たち税理士と違っているかもしれません。
お客様の節税イメージは、
「少しでも支払う税金を少なくしてほしい
だから、税理士さん、頼むよ~」
では、ないでしょうか。
はい、仰せのとおりに!と景気よく返事をしたいところですが、
できることと、できないことがあるのです。
榊原の考える節税とは
私の考える「節税」は、
正しく税金計算をすると、節税になる
でございます。
税金計算は、法律で決まっています。
そして、その解釈も通達で示されています。
どう取り扱うかは、ほぼ決まっているのです。
もちろん、実務では、そのものズバリとならないケースもあるので、
裁判例や法令の読み方、解釈で判断することになります。
よく新聞で、著名な会社で税務調査があって、
「見解の違いで、税額が違っていたので、修正をしました」
記事をよく見ますね。
法律を読み解き、特例や措置法など、
細かな法令まで検討して、税額を計算する、
これが、「正しい税金計算」です。
もし、「無知」が原因で税金計算したら、税額が増えてしまった。
これは、「正しくない税金計算」なのです。
払い過ぎは、もったいないですよね!
特例や措置法を使おうとすると、
申告時期(すでに決算が終わっている時期)では、後の祭りとなるケースもあります。
決算の進行している年度内、もしくは始まる前に、
いろいろ手を打っておかないといけないこともあるのです。
ですので、申告時期に計算した税額に対して、
「先生、これは多すぎる~
もう少し安くならないの~」
と言われても、できないのです。
そう言って、もし安くなるとしたら、それは「節税」ではなく
「ごまかし」や「嘘」
あってはならないのですが「脱税」
となってしまうかもしれません。
これらは、けっしてやってはいけないことです。
どの税理士でも、「正しい税金計算」をして、
少しでもお客様の税金を払いすぎないように、努力されています。
その辺をよ~~く理解して、あまり無理をおっしゃらないでくださいね(苦笑)。
信頼のおける税理士に頼んで、「正しい税金計算」で
払いすぎないように、してくださいね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年1月14日
中小企業の皆さん、固定資産税の減免申請が間近です
明けましておめでとうございます。
皆さまが、少しでも前向きに、おかげさまの精神で、経営に取り組んでいけるように、
頑張っていきたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
とはいえ、年末から毎日のように新型コロナウイルス感染の数が更新され続けています。気分的に晴れやかになれません。
固定資産税とは
固定資産税が課されるのは、大きく分けて二つです。
一つ目は、不動産、いわゆる土地や家屋ですね。
土地は、田、畑、山林、牧場などです。
また、建物は住宅、店舗、工場、倉庫などになります。
もう一つは、償却資産です。
償却資産とは、土地や家屋以外で、
会社で使用しているパソコンやコピー機、備品など、
時間の経過とともにその価値が減少していく物をいいます。
ほかに、各種製造設備や医療機器、航空機、船舶なども該当します。
償却資産に含まれないものとしては、
自動車税の対象となる自動車、
特許権など無形固定資産などです。
固定資産税はその年の1月1日に所有する不動産や、設備などの評価額に対して課税されます。
そう、所有しているだけで課税されるため、たとえ業績が悪化し赤字となっても税金がかかってしまうんですね。
家屋や設備を多く保有する事業では、金額も大きくなって納税が大変です。
固定資産税の減免が受けられるのは
新型コロナウイルスの影響で、大きな影響を受けた中小企業の皆様には、今年度の固定資産税の減免が受けられます。
ただし、この制度は令和3年度の固定資産税・都市計画税のみ減免されることとなっています。
今のところ、今年限りの特例となります。
対象になるのは、
①中小企業者であること
-
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
-
資本又は出資を有しない法人で、従業員1,000人以下の場合
-
個人で従業員1,000人以下の場合
多くの会社や事業主さんが対象になりそうです。
ただし、大企業の子会社等は、残念ながら含まれません。
②売上高が大幅に減少していること
2020年2月~10月までの、任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、
対前年同期で比べて30%以上減少
(減免額)
売上の減少比が
30%以上50%未満 半分減免
50%以上 全額減免
(減免対象)
-
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
-
事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません
手続きで押さえておいてほしいこと
固定資産税はその年の1月1日に所有している資産に課税されます。
したがって、年明けの今が市町村へお伝えする最終のタイミングとなっています。
今回の申告期限は、今月末までとなります。
申請するのにも、書類を整えなければなりません。
ご自身ですぐ書けるものもあれば、
法務局に行って謄本を発行してもらったり、
認定経営革新等支援機関から認定の書類を書いてもらうものもあります。
現在は、締め切りが迫っているため、
認定経営革新等支援機関以外の機関や、税理士など有資格の方からでも
それらの書類を書いてもらえます。
いずれにしても時間的余裕が必要です。
該当しそうだな、そう思ったらすぐに
信頼のおける税理士に相談してみてください。
焦る必要はありませんが、
お急ぎくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2020年12月11日
消費税 1,000万円の落とし穴
消費税申告には、気づきにくい落とし穴が結構あります。
その中で、今回取り上げたいのは「1,000万円」の落とし穴です。
新しく事業を始める時、世間一般で広く知られているのは
最初の2年は消費税がかからない
実は、このことが広く行きわたっているがために、うっかり落とし穴に入ってしまうことがあるのです。
会社設立時の1,000万円
消費税がかかるのは1,000万円。
金額ばかりにとらわれると、うっかりが生じやすいのです。
確かに、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の課税事業者になりません。
基準期間とは、現在の進行期の2年前の年です。
だから設立したばかりの会社であれば、売上がないので消費税課税事業者にはなりません。
しかし、以下のケースのいずれかに当てはまると、最初の年から消費税の課税事業者となるのです。
注意するのは売上高だけではありません。資本金も注意してください。
-
資本金が1,000万円以上
-
合併・会社分割等があった
-
特定新規設立法人である
平成18年に会社法が施行されるまでは、株式会社の最低資本金は1,000万円とされていました(平成14年から条件付きで最低資本金は1,000万円でなくてもよくなっていました)。
その名残でしょうか。
「株式会社をつくるなら、資本金は1,000万円いる」
「会社の信用を高めるには1,000万円」
「キリがいいから」
とうっかり1,000万円にして登記してしまうことも。
会社設立は、司法書士の主たる業務なので、税理士が関わらずともできます。
まずは箱を作ってから、事業が軌道に乗ってきてから、と税理士に関わらない方もいらっしゃるでしょう。
一度登記してしまえば、もう後の祭り。
最初の年から消費税課税事業者となってしまうのです。
落とし穴は、売上か資本金か。
以下か未満か。
売上に注目すれば1,000万円以下が免税。
資本金に注目すれば1,000万円未満が免税。
同じ1,000万円でも大きな分かれ目ですね。
ふたつ目と三つめは、イメージとして、
大きな会社ですでに事業をしていて、その一部を分社・分割して新たに会社を作って、
その子会社としてスタート。
実態を見れば、すでに実績等もあるため、課税事業者となってね、ということです。
税金は弱者保護の視点が背景にあります。
新しく立ち上がったばかりの、よちよち歩きだから、おまけしてくれるのです。
基準期間の1,000万円
消費税の課税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた年ではありません。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていた時です。
ここで落とし穴。
課税売上高ってナニ??
消費税法ではこのように規定されています。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)
いわゆる税抜きの金額で判定します。
しかし、基準期間において免税事業者であった場合は、基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていない、とみなすため、税抜処理を行っていない金額、つまり税込み金額で判定することになっているのです。
通常は、免税事業者であっても、税込価格で販売しているはずです。
しかし会計基準では、「税抜処理方式」が原則とされているので、決算書の売上高は税抜になります。
免税事業者だった場合は、上記のように「税込価格」で判定をすることになるため、
決算書では950万円と売上高が表示されていても、税込みになおすと1,045万円。
うっかり課税事業者だと気付かないこともあるのです。
このことが、どういう結果となるのでしょうか。
消費税法では、課税売上高が5,000万円以下の事業者なら、
一般課税方式と簡易課税方式が選択できます。
選択できるということは、税額が違ってくる、ということです。
しかし、その選択届出は、前の期に出しておかねばなりません。
もし自分の会社が課税事業者にならない、そう思っていると、届出を出すことを忘れてしまい、
結果、多くの税額となってしまうこともあるのです。
また、課税売上高は「課税される取引」と思い込んでいると、うっかり落とし穴にはまります。
国税庁のHPで、
売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)
(参考) 申告や納税について知っておきたいこと
のなかに次の記載があります。
「ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます」
税金は課税されるものと非課税のものに分けられる。
それは正しいです。
課税売上高の定義をもう一度、見てください。
「課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、・・・」
輸出品は消費税はかかっていません。
だから輸出売上は「非課税」だと思い込んでいませんか。
輸出売上は課税売上高に含めます。
輸出は消費税率が0%
の課税売上高になるのです。
ウチは輸出売上がメインだから、消費税の課税事業者にななってないよ、
それは要注意です。
開業2年目の1,000万円
会社設立、事業を開業した最初の2年間は、消費税はかからない。
平成25年の消費税改正までは、そうでした。
しかし、いきなり業績絶好調、事業も軌道にのりました、
そんな会社には、2年目でも消費税は支払ってもらいましょう、となったのです。
1年目の最初の半年で、
課税売上高が1,000万円または、給与の支払いが1,000万円を超えたら、
2年目は課税事業者となり、消費税を支払うことになります。
だから最初の2年は、消費税は払わなくていいもんね、
そう思っているとうっかり落とし穴にはまります。
いかがでしたか?
消費税の落とし穴。
起業しようと考えている方、
事業を始めて間もない方、
うっかりがないように、信頼のおける税理士に、
事前にいろいろ相談してくださいね。
損をしないアドバイスをしてくれると思いますよ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2020年11月13日
ひとり親と年収850万円超の方、年末調整が変わります
朝晩が冷え込むようになりましたね。
年末調整の封書が、税務署から届き始めました。
ウチの事務所へも、お客様から問い合わせが来ています。
今年の年末調整で、注意していただきたい方がいます。
それは
お給料をもらって働いている方で、
-
ひとり親の方
-
大学生までの子どもを扶養している、年収850万円超の方
ひとり親の方は税額が変わるかもしれません
今年から所得控除にひとり親控除が創設されました。
従来の寡婦・寡夫控除の不足分を補う形で設計されています。
扶養する子どもがいるひとり親は、男性でも女性でも、等しく控除を受けられるようになりました。
そして、事実婚が無かった親、いわゆる未婚の母でも、税金が少なくなります。
ひとり親控除の金額は35万円で、これまで特別の寡婦が受けられた金額と同じです。
子育てと仕事を頑張っているシングルパパ、シングルママに優しくなりますね。
さて
今までの税金計算では、所得控除として、
寡婦控除
寡夫控除
がありました。
男性と女性で(パパかママか)で取り扱いが異なっていました。
あなたが女性なら、寡婦控除を検討します。
① 夫と死別または離婚している(再婚はしていない)
② 扶養家族、または合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる
③ 合計所得が500万円以下
この3つの要件で判定します。
全部が該当し、②のうち子どもがいる、という方は特別の寡婦と言って、
35万円が所得から差し引かれて税金計算されます。
シングルママで所得も多くないので、税金は助けよう、という主旨です。
③だけ該当しない
例えば、離婚して子どもを引き取り、バリバリ仕事をしている母子家庭のキャリアウーマン
①と③が該当する(死別の場合)
例えば、夫と死別をしたのだが、子どもは独立したので、多くを稼ぐ必要がなく暮らしている女性
全部該当するが、②のうち子どもでない扶養家族がいる
例えば、離婚して、年老いた母を扶養しながら暮らしている女性
これらの方々は寡婦控除として27万円が差し引かれます。
条件の組み合わせで控除額が決まってきます。
しかし①だけ該当しない、つまり未婚の母で収入が多くない方は、
これまでは寡婦控除が受けられなかったのです。
いわゆる「シングルマザー」と呼ばれるような方をイメージしてください。
未婚の母は、事実婚が無い方と定義されています。
今回のひとり親控除が創設されたことで、未婚の母も税金が少なくなりました。
一方で、今まで女性は所得制限を受けずに、寡婦控除を受けられたのですが、
合計所得が500万円超だと控除を受けることができなくなりました。
ここは男女とも同じ条件に合わせたと言えますね。。
あなたが男性なら、寡夫控除となります。
① 妻と死別または離婚している(再婚はしていない)
② 合計所得が38万以下となる生計同一の子どもがいる
③ 合計所得が500万円以下
男性の場合、全部を満たしている場合のみ、寡夫控除27万円が差し引かれます。
アレ?男性女性で比べると、違いますね。
男女不平等!?と思われるかもしれません。
税金には、弱者保護の思想が背景にあります。
つまり、これは女性の方が男性に比べて不遇とされている社会の裏返し、
ともいえるのではないでしょうか。
離婚して年老いた母を扶養しながら暮らしている男性は、所得が少なくても、女性のように税金は助からないのですね。
なんだかね~
要するに、これまでの「特定の寡婦」「寡夫」が無くなり、
- 未婚の母は減税
- 男性のひとり親は減税
- 所得が500万超の女性は増税
となるのです。
事実婚や内縁関係である場合には、これらの控除の適用はありませんからね!
ごまかしはいけませんよ。
そして再婚をすると、適用されなくなりますから心得てくださいね。
所得が850万円超のお給料をもらっている
もうひとつ年末調整で注意したい点があります。
それは、給与収入が850万円を超える高サラリーの方です。
今年から給与所得控除の上限が引き下げられました。
給与所得控除とは、サラリーをもらう人の非課税枠と言えるものです。
その上限が下がるということは、高サラリーの方にとっては増税だということです。
しかし、子どもを扶養している方々については、税金は少なくしますよ、
これが所得金額調整控除と呼ばれる制度です。
実は勘違いしやすい点があります。
もし子育て家庭で、夫婦ともに年収850万円を超える家庭であれば、
夫婦それぞれで、所得金額調整控除が受けられる、ということです。
扶養家族を控除する場合は、パパかママ、どちらか一方から控除となるので、
それと混同しやすいのです。
このケースの方は、年末調整時に「所得金額調整控除申告書」を書いて、会社に提出することになります。
お忘れのないように。
年末調整は、ご自身で行わず、会社が行います。
出すものが出していない、申告をしていない、
そんなこと税金計算が高くならないように、納税者として
しっかりと押さえるべきところは押さえてくださいね。
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2020年10月12日
持続化補助金(コロナ特別対応型)へチャレンジ
新型コロナウイルスの影響で、事業計画の変更を余儀なくされている経営者様も多いと思います。
私は税理士稼業をメインとしていますが、妻と共に研修とコンサルティングの会社も経営しております。
メインとなるサービスのひとつが研修ですので、新入社員研修や対面研修のキャンセルが続き、大きな影響を受けました。
こんなときこそ、前を向き、いろいろ手立てを講じるのが経営者の務め!
そこで、持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請にチャレンジすることにしました。
持続化補助金(コロナ特別対応型)とは
持続化補助金とは、正式名称を「小規模事業者持続化補助金」と言います。
小規模な事業者が、販路の開拓や、生産性の向上などに取り組む場合、
そのかかった費用の一部を補助するものです。
あくまで補助金なので、費用を使うことが前提になります。
その意味では、「給付金」とは違います。
持続化給付金とネーミングが似ていて、間違いやすいですね。
コロナ特別対応型は、持続化給付金の中で、新型コロナウイルス感染症を受けた事業主向けに、特に準備されたものです。
- サプライチェーンのき損への対応のための経費
- 非対面型ビジネスモデルへの転換のための経費
- テレワーク環境の整備のための経費
これらが対象となります。
補助率も3/4まで引き上げられ、補助上限は100万円です。
130万円の経費を使ったなら、97万5千円が補助されます。
助かりますね~!
今回の申請で私たちは、
研修を対面からWEB会議システムを活用(zoomやteamsなど)することとし、
新たに専用のHPを作成、
そこから自動的に、手続きを一気通貫で行える、システムの導入をすることにしました。
申請様式を作るのは難しい?
書いてみたのですが、意外とスムーズに作成できました。
事業計画は、慣れていないと面食らう内容ですが、
商工会議所を利用されるなら、そのモデルケースの例示がいただけるので、
それを参考にイメージして書くことができます。
金額も事前に業者から見積もりを取っておけば、安心ですね。
事業の計画をじっくりと検討できるので、ご自身で書いてみることをお勧めします。
おおむね、手引きに沿って書いていけば、出来上がります。
大丈夫!ちゃんと書けます。
注意するのは、事業主様が、対象になる「小規模事業者」に該当するか、です。
経営主体は、法人でも個人でも対象になります。
小規模判定は、業種にもよりますが、常時使用している従業員の数が、5人から20人以下が対象になります。
しかし、役員や事業主様は除きますし、
パート従業員も条件によればカウントされないので、
意外と多くの事業者様が対象になるのではないでしょうか。
事業再開枠というオプションも
今回はコロナ対策として「事業再開枠」の名称で、
衛生に関わる費用が、別枠で補助されることになりました。
その金額は50万円。補助率は100%です。
マスクやフェイスシールド、消毒液や消毒設備(空気清浄など)に加えて
換気設備やクリーニング外注まで、幅広く対象が指定されています。
さらに、
屋内スポーツジム、バー、カラオケ、ライブハウス、接待を伴う飲食店は、
それぞれ上限額が50万円上乗せされます。
事業再開枠で補助される衛生に関わる費用は、遡って経費認定が行われますので、
こういった業種の方は金額も相当だと思うので、
ぜひチャレンジしていただけたら、と思います。
ただ、事業再開枠のみでの受付はできません。
あくまでメインの補助金申請のオプションになります。
採択されるかどうかは分かりませんが、
明日を信じて、前向きに取り組みをしていこう、という事業主様には
ぜひチャレンジしていただきたいですね。
コロナ特別対応型の第5期申し込みが始まっています。
これが最終申込となります。
締め切りは2020年12月10日。
この機会をお見逃しなく。
もし不安があるのなら、商工会議所でも構いませんし、
信頼のおける税理士にお尋ねください。
多くの税理士が、補助金の相談に乗れる認定機関となっています。
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!