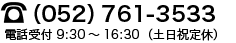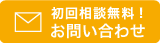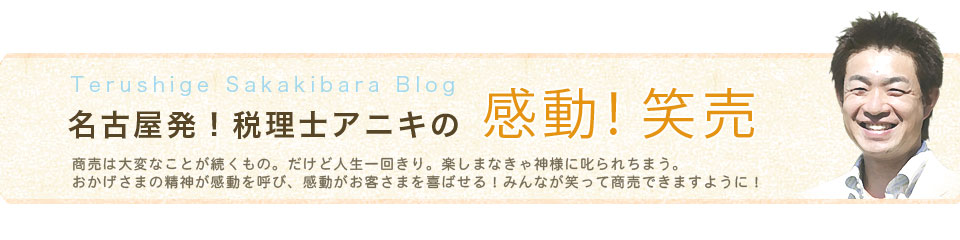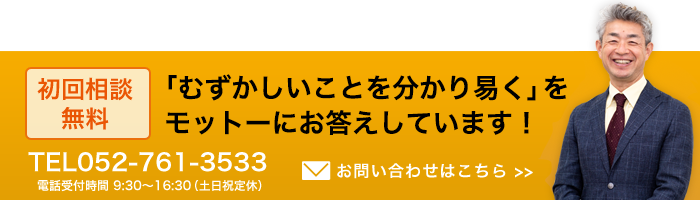2022年5月12日
顧問税理士を頼もうと考えている方へ
先月の記事では起業の方向けの内容を取り上げました。
今回も同様に起業向けのテーマです。
もちろん事業をされている方でも、そもそものお話かもしれませんが、ご興味があればお読みください。
税理士との契約は必要なの?
実は税理士しかできない仕事が3つ法律に定められています。
お客様にはこの仕事を基本的に税理士と契約していただいてるのですね。
➊ 税務代理
❷ 税務書類の作成
❸ 税務相談
税務代理とは、本人に代わって申告書を税務署へ提出したり、税務調査の時に立会いをしたり説明をする仕事です。
あなたが税務調査官だったら、税務署へ提出された申告書に税理士のハンコがあるのとないのと、どちら調査へ行ってみようと思いますか?
調査の時、一人で調査官に説明するのを想像してみてください。心細いですよね。
税務書類の作成は、税務申告書をはじめ、各種届出などになります。
選択がいくつかあったり、期限があったり、失念したり誤ったりすると損をする可能性があります。
税務相談とは、まさに税金に関する相談です。相談料の有無にかかわらず、資格がない方がこれを行うと税理士法違反となってしまいます。
もちろん、私はネットや本で調べて大丈夫!という方は税理士と契約しなくても良いのです。
税理士を探すには
では税理と契約しようと思ったら、どこで出会えるのでしょう。
昔からスタンダードなのは知り合いに紹介してもらうことですが、最寄りの税理士会で紹介してもらうことも可能です。
ネットで検索するということも最近は一般化してきました。
税理士紹介サイトなるものもいっぱいありますね~
自分に合いそうと思ったらメールや電話をしてお話を聞くと良いでしょう。
事業を始めてから税理士を頻繁に変えることは大変だと思うので、
面倒かもしれませんが、あらかじめ複数の税理士に話を聞いて決めることをお勧めします。
税理士と会う時には
事業を始めている方であれば、最初に持参していただけると、私たち税理士が話やすく助かるものは以下の書類です。
- 過去の決算書と申告書【3年分くらい】
- 過去に提出した税務関係の届け出
- 事務所の賃貸借契約書、その他事業に関する契約書等
- 法人であれば定款や謄本【履歴事項全部証明書】
これらは重要書類でもあるので、必ず保存版としてファイリングしておいてくださいね。
お困りごとが明確であればあるほどありがたいですね。
税理士の報酬は
一番気になるのは、税理士の報酬ですね。
相場はどれくらい?と尋ねられても正直お答えするのが難しい質問でもあります。
税理士の考え方や地域、依頼する内容によって変わってきます。
一般的には年間の売上高などの規模感、経理などのボリューム、従業員の人数、依頼する業務の内容、税理士とのかかわり方などで決まってきます。
同じ業務でも記帳を自分でするのか、任せるのか、会計事務所の担当者が開業税理士本人か、資格勉強中の社員なのか、でも変わってきます。
内容の説明が不十分なまま「顧問料はいくらです」だと、あとでトラブルになってしまいます。
顧問料で何をしてくれるのかを最初に根掘り葉掘り(笑)聞いておくことがポイントです。できれば書面だとはっきりしていいですね。
確認してすり合わせておくことは次のふたつです。
➊ 報酬金額
❷ その報酬金額で具体的に何をしてくれるか
報酬は安くしたいという方には
「ご自身で会計ソフトなどを使って決算書を作成し、税理士は年一回の打ち合わせをし、それに基づいて申告業務だけ請け負う」
という提案がなされます。
しかし事業主様から「税金の提案がない」「節税対策がない」「会計の仕訳チェックがされていない」「フォローも少ない」と不満が出てしまうのはよく聞くケースです。
これはお互い残念な結果です。
だから契約時にしっかりすり合わせしておくことが大切です!
また連絡手段の違いも気になります。
開業している税理士の平均年齢は高いのです!
メールのみならず、チャットなどSNSを駆使していらっしゃる方もいれば、一方で直接電話かFAXという方もいらっしゃるのです。
何より、直接事務所へ訪問して、税理士と会ってお話して、事務所のスタッフの雰囲気や空気感を感じていただくのが一番だと私は思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2022年4月12日
旗を立てる
四月になりました。
外を見ると桜が満開です。
新しい気持ちで、新しいことを始めよう。そんな時期でもありますね。
事業を始めることを「起業」と言います。
起業を目指す方は「起業家」といい、私どもにも起業家の相談が舞い込みます。
私どもの仕事は税務会計の専門となりますので、
起業家の方からの問い合わせは、経理のこと、税金のこと、そしてお金のことが多いです。
また最初の窓口としてドアノックされる方もいらっしゃいます。
補助金の話や会社設立など法務的なことも相談されます。
とはいえ、いきなりお金の話から説明しないようにしています。
起業家の方には、
事業をしていく思いをコトバにして語っていただく
ことにしています。
つまり創業の動機、そして理念です。
起業するというのは
旗を立てる
ことです。
その旗を見て、
「ああ、いいな」
そう感じてお客様が商品やサービスを買っていき、
「ここで仕事したいな」
と感じてスタッフが集まってくるのです。
旗を立てるには、しっかりした土台が必要になりますよね。
それが創業の動機、理念となるのです。
起業家の思いの強さは、事業を成功させるための大きなエネルギーになります。
思いが強ければ強いほど、成功に近づくと思います。
思いは内面から泉のように沸きでてくるもので、
聞かせていただくと私も愉しい気持ちになります。
思いを語っていただくときは、思う存分自己陶酔して、夢物語として語っていただくのが最高です。
できる、できないはここで考えません。
稲森和夫さんは著書「成功への情熱」PHP出版のなかで
「ビジネスを成功させるためには、夢を抱いてその夢に酔うこと」とおっしゃっています。
思いをコトバにするのは、やってみると結構大変で、時間もかかります。
しかしコトバこそが、その創業の理念を正しく伝えていくことになるのです。
起業時に作った思いを伝えるコトバは、
事業で行き詰ったとき
社員と思いがすれ違ったとき
必ず社長や事業主様の大きな手助けとなり、
軌道修正の道しるべになるのです。
会計人として「決算カウンセリング」を行うとき
初心に帰る意味も込めて、私は必ず社長や事業主様に尋ねるようにしています。
語ってみたい、そう思ったらお声掛けくださいね。
つらいとき、大変なとき、そんな時こそ
税理士や社会保険労務士など一緒に帆走してくれるパートナーに
創業の思いを語ってみてください。
きっと喜んで聞いてくれると思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2022年3月10日
家事関連経費とは
確定申告も最終コーナーを回って最後の追い込みです。
個人の方が申告する場合、これは「経費になるのかしら?」と質問をいただきます。
今回は間違えいやすい「家事費」と「家事関連費」についてです。
所得税法での個人に属する支出費用は3つ
所得税法では、個人に属する支出費用は
- 家事上の経費
- 家事上の経費に関する経費(家事関連費)
- 業務上の経費
の3つに区分しています。
基本的には「家事費」と「家事関連費」は必要経費とならず、「業務上の経費」のみが必要経費と認められます。
ただ家事関連費のうち、
業務上の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合は、それに相当する金額
が必要経費にできます。
家事費と家事関連費のちがい
家事費となるのは次のようなものです。
- 自己または家族の「食費」「被服費」「医療費」「娯楽費」などの生活費
- 自己または家族の住宅にかかる「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
- 自己または家族の「生命保険」
- 自己または家族の「税金(所得税・住民税・贈与税など)」
一方で、家事関連費は次のようなものです。
- 店舗併用住宅の場合の「地代家賃」「水道光熱費」「修繕費」「租税公課」「火災保険料」
- 車両やパソコン、携帯電話など仕事にも私用にも使うもの
家事関連費が経費になる要件は、次のふたつとも満たされている場合に限られます。
業務の遂行上必要である
必要である部分を明らかに区分することができる
例えば、カフェを経営していて新聞・雑誌を購入していたとします。
その主たる部分が業務遂行上必要であるかを判断します。
お店においていてもご自身も読むでしょうし、夜になれば自宅に持ち帰って読むかもしれません。
どのような状態であるかによって総合的に判断することになります。
家事関連費の経費計上は按分
家事関連費で、業務の遂行上必要であると明らかに区分されたら、その金額は果たしていくらかを決めることになります。
実務上はここで判断するのですが、具体例を挙げると以下のようになります。
- 支払家賃、減価償却費…床面積の使用割合
- 水道光熱費…面積割合、使用割合、コンセント数、メーター
- 通信費…電話、通信の使用割合、使用時間
- 消耗品…使用割合、使用時間
- 車両…走行距離、使用日数
あいまいに「これくらい経費でしょう」と判断するとやけどしますよ!
税務署が調査に来て否認リスクが高いものになります。
信頼のおける税理士と内容を吟味して、必要経費を計上してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2022年2月10日
事業復活支援金が出ました
新型コロナ・ウイルスのオミクロン株が猛威を振るっていますね。
コロナ禍のなかで3回目の確定申告が始まります。
コロナの影響で事業経営やお金に苦しんでいる方も多いなぁと実感します。
1月24日、政府から新たに中小企業や個人事業主様向けに、コロナからの復活・回復を目指すための支援として「事業復活支援金」がリリースされました。
支援金の対象になる方は
今回の支援金の対象になるのは、
- 新型コロナ・ウイルスの影響を受けた
- 2021年11月~2022年3月の中で、いずれかの月(ひとつき)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間での任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した
事業者様となります。
今までの給付金が、飲食店や観光業など直接的な影響があった方々向けが多かったのに対し、
今回は中小法人や個人事業主さま全事業者向けであることが特徴です。
昨年春に出ていた「持続化給付金」とよく似ていますね。
その第2弾と位置付けられます。
給付額の算定のポイント
給付の申請にあたり、まずは金額の算定について特徴があります。
商いの金額が小さい方であれば、一番少ない売上高の月を対象月としない場合でも、給付金の金額が多くなるケースもありますのでご注意くださいね。
まずは要件にあるように、去年・一昨年・3年前の同じ月との比較で月間売上高に30%以上の減少があるか確認していきましょう。
ここ5か月の中の月別売上高を一つ抽出します。
売上の少ない月から過去3年間の同月比較をしていきましょう。
ここで要件である30%以上の減少であればクリアですね。
これが「対象月の売上高」となります。
違う年度にいくつか該当するのであれば、検討の余地があります。
まず押さえるのは「基準期間の売上高」です。
去年・一昨年・3年前の11月から3月までのそれぞれ5か月間を集計しておきます。
次に対象月の売上高を5倍します。
そして対象月の売上高を求めるときに比較した年度分の基準期間の売上高との差額を計算します。
これが算定金額となり、減少率に応じた上限額まで給付されますよ。
減少率と基準期間の売上高の多寡により給付される金額が変わります。
対象月の売上高ごとに試算し選択しておくとよいですね。
申請が少しラクになる方々
以前に、一時支援金や月次支援金を受給された方は、事前確認が不要です。
過去の申請情報がそのまま使えますので、少しラクになりますね。
また登録関係機関と「継続支援関係」にある方、
例えば登録機関として認定を受けている税理士事務所と顧問契約をしているケースですね、
であれ場事前確認が簡略化され、提出書類の確認有無も省かれます。
国民の皆様から集めた税金を原資に給付されます。
間違いのないように、しっかり計算して申請するようにしたいですね。
「対象になるかな?」「給付金額は合ってるかな?」
そう思ったら、信頼のおける専門家にお尋ねしてみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2022年1月12日
電子帳簿保存法について2年間の猶予期間?
昨年度の税制改正で、電子帳簿保存法の改正があり、
平成4年より電子取引については書面による打ち出し保存が認められなくなりました。
その場合青色取り消しの罰則が明記されたため、
ITリテラシーなど環境が不十分な家族経営や零細企業にとって、
「これは大変厳しい内容だなぁ」と思っておりました。
12月の税制大綱
案の定、そういった声が政府にも届いたのでしょう、
12月の税制大綱、自民党が12月10日に出したのですが、に
「電子帳簿保存法の取引情報に掛る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」
が書き加えられました。
法律が実施される前の一か月もないこの時期においては異例です。
実際の現場サイドからはかなり厳しいところもあったので、ほっとする反面、
法律作成において、多くの家族経営、零細企業に寄り添わない丁寧さに欠ける印象を持ちました。
延期ではなく宥恕
メディアでの報道ですと
「延期」「猶予期間」
と見出しが出ているところもありますが、正しくは
「宥恕(ゆうじょ)」
です。
そもそも「宥恕」ってどういう意味ですか?
使い慣れない言葉ですので理解が難しいです。
宥恕とは、寛大な心で許すことです。
え?許す?
つまり2年間は期限延長や猶予期間ではありません。
やれていないけど大目に見て許してあげる、という意味です。
電子帳簿保存法の改正は予定通り始まっているのです。
大目に見てもらえるのは
税務署長が、電子取引の保存要件に従って、電子的に保存できなかったことについて「やむを得ない事情」があること
とされています。
じゃあ「やむを得ない事情」って何よ?ということが問題ですね。
これ以上は何も書かれていないので、何ともコメントしようがありません。
何もしなくて良いというような無条件ではなさそうです。
現時点での私の理解なら、
電子帳簿保存法の改正に合わせて経理を行いったうえで、
ケースによっては出来なかった、
そういう時は紙で保存は認めるけど、理由ははっきりさせてね。
そういうことかなと思います。
まだ2年ある、そう思わずしっかり手当てを始めていきましょう。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年12月10日
年末ですが固定資産のチェックも忘れずに
12月です。
師走で皆さんも大忙しではないでしょうか。
年賀状や大掃除、お正月や帰省の準備・・・。
会計事務所ではサラリーマンの確定申告である年末調整で大忙しです。
忙しい時期ではありますが、事業を営む方にはぜひ事業用固定資産のチェックをお勧めしたいと思います。
固定資産には税金がかかる
家や土地などを所有していると固定資産税がかかります。
これは個人でも法人でも必ずかかります。
福祉など特別な場合には免除ってことはありますけどね。
同じく事業用固定資産にも税金がかかります。
固定資産税を納める先は、日本国ではなく事業所のある市町村です。
これらは日本国に納める国税とはちがう住民税の一種です。
償却資産税とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、
法人や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産です。
次のようなものが定められています。
① 構築物…駐車場の塗装や看板、門や塀など
② 機械装置(建物付属設備)…工作・印刷機械や駐車場の機械。テナント賃借の場合の内装費など
③ 船舶…ボートなど
④ 航空機…飛行機やヘリコプター
⑤ 車両…大型特殊自動車等(ナンバープレートが「0」または「9」で始まるもの)
⑥ 工具・器具備品…事務机やいす、陳列ケース、パソコン、エアコン、金庫、ゲーム機器など
住民税の課税は、1月1日に所有しているものについて申告して課税がなされます。
だから12月の間にしっかりチェックをして、整理しておきましょう。
もう持っていない、すでに使っていないものは申告しないようにしましょうね。
乗用車やトラックは自動車税や重量税など、別に課税されているんですよ。
償却資産かどうか迷うもの
実務では迷う場面もしばしばあります。
次のような資産でも1月1日現在、事業を営む上で使用することができる状態であれば申告の対象となります。
(1) 建設仮勘定で経理されている資産
(2) 決算期以後1月1日までの間に取得された資産
(3) 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
(4) 償却済資産(減価償却を終えた資産)
(5) 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
(6) 未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
(7) 資産の所有者が、他の者に貸付けその貸付先で事業の用に供されている資産
ただし、その所有者が資産の貸付を事業としている場合は、貸付けられた資産が貸付先で事業の用に供されていると否とにかかわらず申告が必要です。
(8) 取得価額が20万円未満の資産で、税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産
ただし、次のような償却資産は申告の対象となりません。
①耐用年数が1年未満の資産
②取得価額が10万円未満の資産で税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入された資産
③取得価額が20万円未満で、事業年度ごとに一括して3年間で償却し、一括して損金又は必要な経費に算入された資産
(9) 取得価額が30万円未満の資産で税務上「少額資産」として処理された資産
ここで「おやっ」と思いませんか。
15万円のパソコンならどうなるのでしょう。
(8)のように税務会計で「一括資産」としたら償却資産の対象から外れるのですが、(9)のように「少額資産」としたら償却資産の対象になる、とありますね。
他にもまぎらわしいものがあります。
国税申告において、構築物や建物附属設備を建物一式として減価償却していても、
償却資産申告においては個別に申告する必要があります。
なんだかややこしいですね~
うっかり申告漏れなどないように、
もう持っていない資産まで申告しないように、
しっかり確認しておきましょう。
これってどうかな?
そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年11月12日
パート・アルバイトさんが迷う、税務と労務の「かべ」
早いもので、年末調整の時期がやってまいります。
私どもの事務所でも、お客様への案内で大忙しです。
先日ある関与先のスタッフさんから、こんな質問がありました。
「130万円を超えないようにしたいんですが、いつのお給料を調整すればいいのでしょう?」
年末調整のこの時期になると、パート・アルバイトさんは働く日を調整する方も多いようです。
経営者さんからすれば、休まれても困るところもありますけどね(苦笑)。
ですが、税務と労務では「かべ」が違います。
税金も社会保険も給料から天引きされるもの、とひとくくりで考えると良く分かりません。
「扶養家族」の定義も税務と労務では全く違うので、しっかり線引きしておくことです。
まずは税務の「かべ」について確認しましょう。
103万円のかべ
最もよく耳にするのが「103万円のかべ」です。
一年間の給与が103万円を超えると、自分自身が納税することになりますし、また配偶者の税金が増えます。
ですので、少し前までは、サラリーマンの妻で、パート・アルバイトをしている方はこの基準で賃金調整をしていました。
150万円のかべ
2018年の税制改正で、女性活躍推進の目的で103万円を超えて150万円までの給料なら、
今までの103万円のかべ同様に夫(配偶者)の税金が増えないようになりました。
夫の税金は据え置いて助けるので、もう少し頑張って働きましょう、という改定ですね。
とはいえ、ご自身の税金はかかりますからそこはご容赦ください。
納税しても手取りが増えることになりますから、決して働き損になるわけではありませんよ。
201万6千円のかべ
同じく2018年の税制改正で引き揚げられた配偶者の税金が助からない上限です。
サラリーマンの妻のお給料が150万円を超えたとしても、201万6千円までならまだ配偶者の税金は少し安くなります。
これ以上稼ぐと、配偶者の税金は助かりません。
住民税のかべ
103万も150万も201万6千円も、これはすべて国に納める税金についての規定です。
一方、住民税はお住いの地域に納める税金です。
実は住民税は国税より少し低い額からの税金がかかります。
各市町村により金額も異なります。90万円台からかかる市町村も数多くありますので、
「103万下回ってるから税金はかからない」と思っていてギリギリの線まで稼いでいると、
翌年市町村から通知が来てビックリ、なんてこともありますよ。
ここまでが税務のかべですが、税金計算上は1月から12月に支給された給与の合計額で判断します。
たとえば12月分の給料でも、翌月10日に支給であれば、それは12月分であっても翌年1月の給与として集計されます。
この辺りもうっかり勘違いしやすいところです。
また通勤手当は、通常の公共交通機関などであれば、その手当は課税される給与とカウントされません。
税は『弱者保護』の思想があるので、配偶者が高給取りですとこの限りではありません。
130万のかべ
こちらは社会保険の場合のかべです。
収入額が130万円までなら配偶者の扶養家族となりますので、
サラリーマンの妻の場合、夫の扶養家族に入れば、夫一人分の保険料で年金も健康保険料も賄われます。
これは大きなポイントですね。
106万円のかべ
これも社会保険のかべですが、2016年からは制度改正により、106万円以上の年収があり、
適用条件に当てはまる人は配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならなくなっています。
おおむね従業員の多い大企業や中堅企業に勤めているとこちらになります。
社会保険は130万と覚えているとまちがえます。
また
2022年10月からは従業員数が101人以上、2024年10月からは51人以上の企業に段階的に適用されるため、
106万円をギリギリ超えるくらいの収入を得ていた人は、今までと同じ時間働いても、今後は社会保険料を支払うことになります。
社会保険は税務と違う点が二つ
まず年間の収入額の計算が、税務では暦年の1月から12月と年末調整される源泉徴収票によって判断するところ
労務では直近三か月の平均給料から向こう一年分を推計するところです。
したがって税務で130万超えたから社会保険も扶養が外れると一概に言えないのです。
二つ目は通勤費の取り扱いです。
税務では課税される給与にカウントされませんが、社会保険では給料に含めて集計します。
税務では120万円だとしても、月額1万円の通勤費が出ていると、労務では132万円となってしまうのです。
要注意です。
分かり易くポイントだけお伝えしたので、細かな部分まででケアできてませんのでご容赦くださいね。
「自分の場合はどうだろう?」
疑問に思ったら、専門家である税理士、社会保険労務士にお尋ねしてみてください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年10月11日
渡切交際費って知ってますか
法人の税務では、交際費については厳しい取り扱いになることはご存じでしょうか。
会計では経費になるものでも、税金計算上は損金にならないもの、その一つが交際費です。
損金にならないとは、経費として支払ったのに、税金がかかってしまう、ということです。
それはもったいないですよね。
今回は交際にの中で「渡切交際費」と言われるものを取り上げます。
皆さんはご存じでしたか?
渡切交際費とは
渡切交際費という言葉を聞いたことがありますか?
渡切交際費は「交際費」となっているものの、交際費ではありません!
渡切交際費とは、役員だけでなく従業員に、
接待費や交際費、旅費などの名目で支給したものでも、
その使い道の精算を行っていないため、法人の業務に使用したと証明できないものです。
通常は領収書などで精算されますが、それを怠ると渡切交際費となってしまいます。
その場合は、渡した役員または従業員への「給与」として源泉所得税が課税されます。
渡切交際費を役員に毎月支給したら
実務でよくあるパターンとして、非常勤の役員さんに、渡切交際費が毎月定額で支給されているケースです。
これは経済的利益とみなされ、定期の役員報酬として取り扱われます。
交際費として認められないので、役員に支払った場合、過大役員賞与と認定される可能性が高いです。
役員賞与は損金不算入となりますので、通常の法人税がかかり、
さらに本人に源泉課税が行われ、法人・個人ダブルで課税されることになります。
予め役員報酬として経理しておくことが大切です。
渡切交際費は、もらう側からすれば、事業の経費として使うのに、
自己の給与として自分自身に税金がかかるわけです。
何にもトクなことはありません。
それでも、法人が渡切交際費を支給するというのは、よほどの事由があると思われます。
裏を返せば、それなりの理由があるため、税務署としては、調査で突っ込みたくわけですね。
使途秘匿金と判定されると
税務署が突っ込みたくなるのは、それなりの理由がある、
つまりその支出が使途秘匿金(しとひとくきん)になる可能性があるからです。
使途秘匿金とは、
法人が支出した金銭で、
相当の理由が無く、
その相手方の氏名や住所が、帳簿書類に記録されていない
ものです。
社長や他の役員に仮払金などで出金し、
そこから氏名を秘匿したい人間にお金を還流させるなど、悪質なケースもあるようです。
使途秘匿金となれば、支出額の追加課税で40%の税金が課されます。
また支出の内容が贈与であれば、相手方に税率が高い贈与税がかかります。
取引の仮想隠蔽と判断されれば、重加算税が課され、永久に税務署のブラックリストから外れることがありません。
うっかり渡切交際費をしないように。
やけどしますよ!
そういうことがないように、普段から信頼のおける税理士に相談しておきましょうね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年9月10日
インボイス(適格請求書)事業者の届出が始まります
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が10月1日から始まります。
いわばインボイス制度の第2ステージに入ったといえるでしょう。
経営者の皆様もしっかり理解してご準備願いますね!
インボイス制度とは
インボイス(適格請求書)とは、消費税法の規定に従って正式に発行された請求書や領収書のことをいいます。
そう、この制度は消費税と大いにかかわっている制度なんです。
消費税をちゃんと計算して納められるように、請求書や領収書(これらを証憑と言います)に記載することをしっかり決めました
ということです。
実はインボイス制度は2年前から、軽減税率が始まったときにすでにスタートしています。
これまで経過措置が続いていた第1ステージから、徐々に準備を進めていく段階に入ってきました。
本格的にインボイス制度に切り替わるのが、2年後、令和5年(2023年)10月1日です。
インボイス発行事業者は課税事業者に限定
インボイスを発行できるのは、課税事業者のみとなります。
課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主のことをいいます。
現在消費税を申告納税している課税事業者の皆様は、安心のため登録を速やかにしていただくのがいいでしょう。
登録は紙ではなくe-Taxにより行うことをお勧めします。
紙より早く登録番号がもらえますし、顧問税理士にも登録が自動的に通知され、情報共有や管理がスムーズになるからです。
経理する方は、請求書など、インボイス記載事項に合うように様式を変えたり、
会計ソフトの消費税の設定を変更したりする作業が必要になってきます。
取引先がインボイスを発行できないと消費税が増税となる
ただ問題があります。
消費税の原則的な計算方法によれば、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を差し引いて納税額とします。
このとき、経費として支払った先が免税事業者ですと、
インボイス発行事業者(免税事業者)からの仕入や経費は仕入税額控除(マイナス)にならないため、
結果、支払う消費税が多くなってしまうのです(令和8年、11年まで経過措置あり)。
したがって、支払先がインボイス発行事業者であることを事前に確認しておかねばなりません。
駐車場を借りている、
街の小さな商店で買い物をした、
ネットで個人から安く買い受けた、
講師の方に報酬を支払った、
などのケースだと相手がインボイス発行事業者ではない可能性もあります。
免税事業者は登録すべきか検討しましょう
免税事業者は判断に迷うところです。
実務上は売上げた先のお客様が事業主の場合、その取引先が仕入税額控除をできないため、
取引中止のリスクがあります。
登録するかどうかは、登録期限まで取引先の動向を注視しつつ、決めていただくことをお勧めします。
具体的にはどうしたらいいんだろう
免税事業者だけど登録はした方がいいのかな
そんな疑問があったなら信頼のおける税理士にお尋ねしてみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!
2021年8月12日
一燈を掲げる
東京オリンピックが終わり、まもなくパラリンピックが始まります。
そして高校野球の甲子園大会も始まりました。
いつもの夏なら、大いに盛り上がっているところでしょう。
しかし、子どもたちが夏休みに入るや否や、新型コロナウイルスの感染が止まらず、
デルタ株の感染力の強さが際立っています。
「コロナ疲れ」
なんて言葉をちらほら聞きます。
長いトンネルに、出口はまだか、まだかと不安が尽きません。
一燈を掲げて 暗夜を行く 暗夜を憂うことなかれ ただ一燈を頼め
不安という暗い夜道をまだ歩いていかねばならないと思うと、正直辛いですね。
昔見た時代劇では、夜道を歩いている町人は、手に提灯を持っていました。
灯りをもって、足元を照らすから、歩いて行けるのですね。
こちらは、幕末に活躍した儒家である佐藤一斎の「言志四録」からの言葉です。
佐藤一斎の教えは明治維新に大きな影響を与えました。
言志四録は西郷隆盛の終生の愛読書でもあります。
一燈とは、暗闇を歩くときに当時使った提灯です。今なら懐中電灯といったところでしょうか。
「一燈を掲げる」の一燈とは、その人の志です。
事業をなさる皆様、どうか大切な思いを、
志を、一つ掲げてください。
皆様の思いが、その一燈がお客様の足元を照らすのです。
一隅(いちぐう)を照らす、これすなわち国宝なり
最澄が言っています。
一燈で照らすのは、一隅でよいのです。
一隅とは、「ひとすみ」と読みます。意味は「かたすみ」です。
世の中すべてを明るくしろ、そういうことではありません。
お客様のかたすみさえ照らしてあげれば良いのです。
この苦難を皆さんの一燈で乗り切て行ってまいりましょう。
税理士としての使命
私にも一燈があります。
それは
未来を生きる子どもたちに、この国を素晴らしい社会にしてバトンを渡すこと
素晴らしい社会にするための原資として、納税を前向きに考えてくれる人が増えること
いま私たちが暮らす日本は、コロナ禍で大変な状況であります。
しかし、
平和で、自然も豊かで、食べるものに欠くことも無く、素晴らしい国です。
日本人として、忘れてはいけないことがあります。
それは先の戦争で焼け野原になったこの国を、
「豊かな未来」を作る一心で、
懸命に頑張っていただいた諸先輩たちのこと。
先輩たちが一生懸命働いて、税金を納めてくれたおかげで、
この国は復興してきたのです。
本当に「ありがたい」ことです。
だから。
私たちも同じようにしっかり働き、
この国の未来のために、
子どもたちのために、
税金を納めていかねばならないと思うのですね。
税金は、この国を素晴らしい社会にしていくための原資。
「恩を返す」のではなく「恩を送る」
その思いを広げたいと思います。
税金を納める人を「納税者」といいます。
納税者の中には「税金を払いたくない」とおっしゃる方がいます。
その気持ちはよ~くわかります。
私だって「余分な税金は納める必要はない」と思います。
正しい税の知識を持って正しい税金計算をし、
払い過ぎることなく
適正な納税を皆様にして頂くこと。
それが、税理士の使命だと考えています。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月10 日に更新します。
お楽しみに!