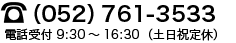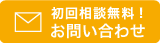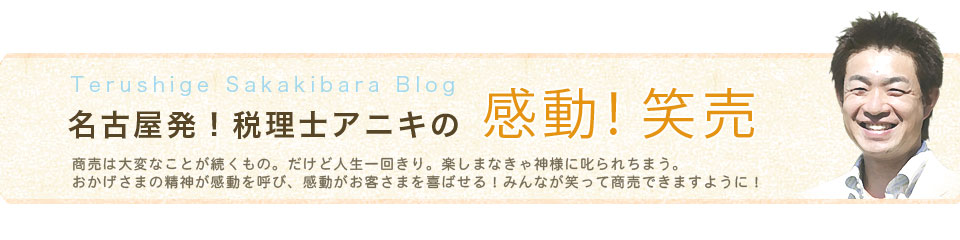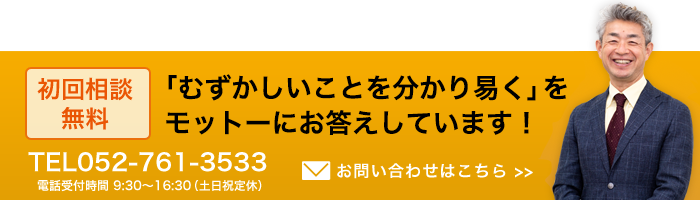2019年10月3日
みなさん、消費税の損得っていったいナニ?
10月1日、消費税率が8%から10%に上がりました。
前日の夜にニュースを見ていると、
ビールを大量に買いだめする焼肉店、
設備投資ができず、店じまいする個人商店の報道がされていました。
消費税の増税の影響があちらこちらで出ています、という趣旨の報道でした。
税理士の視点からすると、少し違和感を感じます。
消費税を負担するのは誰?
そもそも、消費税を負担するのは誰でしょう?
エンドユーザー、いわゆる最終消費者です。
だから、焼き肉店のように
事業をしている人は、税金を負担していない
のです。
え?経費で支払ってますよ。
はい、おっしゃる通りです。
しかし、消費税の計算方法を知れば、その意味が分かります。
モノやサービスを提供したとき、事業主には「売上」が上がります。
その売上額に10%の消費税が課され、事業主が売上と一緒にもらう消費税は「預り金」の性格を持ちます。
一方で、経費を支払えば、その費用に10%消費税が課されます。
消費税は
預り消費税 - 支払い消費税 = 納税する消費税
と計算され、事業主が税金を納めます。
この計算式にあるように、消費税を負担しているのは、あくまでエンドユーザーである消費者となります。
焼き肉店が、あわてて8%の時にビールを買いだめても、結局、納める消費税が増えるだけなのです。
ただ、売上が5000万を下回る事業主なら「簡易課税」方式を選択できるので、
支払う消費税を計算に入れないため、トクをすることはあります。
消費税増税は増え続ける社会保障のため、といいますが
政府、財務省は消費税率を上げる理由として、
増え続ける社会保障費を賄うため
と説明しています。
しかし矛盾する点もあるのです。
消費税率が上がる一方で、下がり続けている税金があります。
それは法人税です。
消費税は平成元年に導入されました。
導入当時、税率は3%で、税収は3.3兆円でした。
それが8%になって、平成30年には17.6兆円、
10%に上がれば22兆円ほどになるでしょう。
平成時代は消費税増税の時代でした。
税率は3%から5%、そして8%、ついには10%まで上がってきたのです。
一方、法人税の税率は、平成元年には40%だったのが、
平成28年には23.4%まで下がりました。
平成元年には19兆円あった税収は、平成30年には12.2兆円となりました。
増え続ける社会保障費を賄うため、というのなら、他の税率も下げるべきではないはず。
荒っぽい言い方になりますが、それはつまり、税金を納めてもらう対象を、法人から個人消費者に移し替えた!ともいえるのです。
もちろん法人税率を下げる理由もいろいろあり、間違いではありません。
人口減少の続くわが国では、税収を確保するために、
所得(儲け)から、消費へ、そして資産へと課税対象が変わっていくことに一理あります。
増税で、私たち国民が注視しなければならないこと、
それは日用品の何が10%で何が8%ではなく、
どんな税金の集め方をすると、国が豊かに、継続していくか、
でしょう。
国民が広く痛みを分かち合う、そういえば美しいですが、
公平性は維持してほしいものです。
間違いないのは、消費税率を上げると、景気はブレーキがかかり、落ち込みます。
その意味では、すべての事業主に大きな影響が出る、損をする、ということになるでしょう。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年9月18日
いよいよ消費税の税率アップ
10月1日が迫ってきました。
いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。
テレビでは連日報道がありますが、
「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。
さて、消費税でいま最も気になるのが、
どのタイミングで10%になるの?
ではないでしょうか。
消費がなされたとき課税されるのが消費税
そもそも消費税は、いつ課税されるのか?
それは
消費がなされたとき
に税金がかかるとされています。
例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、
ではないのです!
使ったときに課税されることになっています。
へ~。
ね、意外でしょう。
ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、
条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。
引き渡し基準が大原則
消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。
例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。
だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、
商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、
消費税は10%となるのです。
しかし例外もあります。
これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。
限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。
公共料金は
まずは公共料金です。
水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。
それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。
必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。
これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。
9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。
ネットでの買い物は
通信販売は要注意です。
楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。
通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。
注文日が9月28日。
商品到着が10月2日。
どうなるでしょう?
引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。
ただ通信販売は、発送日基準なので、
9月30日発送なら8%。
10月1日発送なら10%。
となってしまうのです。
9月末の駆け込み需要もあります。
ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。
航空券やUSJのチケットは
旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。
こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。
不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。
コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。
旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。
ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。
新築の注文住宅は
契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。
経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。
新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。
3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。
ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、
4月以降あったものは、その対象になりません。
10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。
いかがでしょうか。
消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、
買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年9月2日
従業員のため社宅を借りることにしました
最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。
愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。
求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。
企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。
福利厚生を充実させるのも一つの手です。
遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。
社宅の費用も経済的利益
従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、
一定額を超えると、本人さんに課税がされます。
ご注意くださいね。
会社が支払った費用は経費となります。
ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。
え、どういうこと?
前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、
それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。
経済的利益とみなされるのは、
・特定の人だけ優遇
・常識的な金額よりもらいすぎ
の場合です。
一定範囲内までは課税されません
課税される範囲は、税法で定められています。
従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。
通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。
税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。
通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
ややこしや~。
課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。
① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)
家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担
通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、
「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担
課税はされません。
④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている
課税はされません。
社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、
個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。
実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。
したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。
人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。
いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年8月2日
従業員の引っ越し費用
梅雨も明け、夏休みが始まりました。
お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。
また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。
「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。
そんなときの税金は、どうなるのでしょう?
税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、
今回は従業員の税金についてです。
経済的利益とは
会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。
会社へ通うための通勤費、
社内での忘年会費、
結婚したり、出産したときのお祝い金、
健康診断の費用や、
研修のために支払う講師へのお金、などなど。
それらは概ね会社の経費となります。
しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!
それが
経済的利益
と言われるもの。
経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。
・特定の人だけ優遇
・常識的な金額よりもらいすぎ
そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。
引っ越し費用は
では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。
この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。
採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。
必ず引っ越しはしなくてはなりません。
借りたアパートは会社の社宅でもありません。
さて、いかがでしょう。
税務では、
転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税
のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。
新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。
経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。
経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、
従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、
事前に税理士に相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年7月24日
住民税はちょっと違う
住民税は国税ではなく、県や市町村に支払う税金です。
住民税は国税とちょっと違うんです
住民税は賦課課税が多い
わが国での納税の中心的な制度は申告納税制度です。
申告納税とは、「自分で税金計算をして、納める」ことです。
自分で行うといっても、税制は毎年変わりますし、
申告書を作るのだってなかなか大変です。
だから、私たち税理士がそれを代理して行うわけです。
一方、賦課課税制度もあります。
これは、自分から計算するのではなく、役所が計算して
「これだけ税金を払ってくださいね」と言われます。
住民税はこの賦課課税が多いです。
主なものに
所得税
不動産の固定資産税
自動車税
それから国民健康保険税なんてのも。
所得税は、前年の所得に対して計算され、だいたい5月か6月ごろに通知が来ます。
つまりサラリーマンなら年末調整、個人事業主様なら3月の確定申告での申告をもとに計算されます。
新入社員が2年目になると、天引きされる税金が増えるのはこのためなんですね。
国税には予定納税制度があって、前年の所得税を一定以上支払っている方は、
今年の税金を前払いをすることになっています。
その通知が来るのが6月なので、去年の所得に対する住民税、
今年の所得に対する所得税(国税)を同時期に支払うことになります。
なんだか妙な感じです。
課税の判断は1月1日
課税を判断する時期、つまりどのタイミングで課税するかですが
住民税は「1月1日」がポイントとなります。
固定資産税は、その年の1月1日に所有していれば、税金がかかります。
そして1月1日に住んでいる住所地で住民税を支払います。
例えば不動産を8月に売買するとします。
この不動産の固定資産税は所有者が支払っていますから、
譲渡された人にも負担してもらおうと月数按分して支払ってもらうこともあります。
下宿している学生や、転勤しているサラリーマンなら、
住民票の住所は別の市町にある、なんてこともよくあります。
こういう場合は、1月1日に住んでいる市町に住民税を支払います。
住んでいるとは、住民票のある場所ではなく、
居所(いどころ)、生活に実態があるところ、となります。
「アレ?」っと思ったら
専門家に気軽に聞いてみてくださいね。
「へ~、そうなんだ」ということもよくあります。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年7月5日
個人事業主様の老後の備え
人生100年時代、年金以外に2,000万円(こちらは厚生労働省)、いや2,900万円(こちらは経済産業省)必要と言われて、世間を騒がせていますね。
政治家の皆さん、そして霞が関のお役人たち、
「おいおい、しっかりやってくれよ~」とぼやいてみても始まりません。
それではと、「退職してからも、元気だから個人事業主になって一生現役で働くぞ!」
そう思うかもしれません。
とはいえ、不安もつきませんね。
そこで税理士として典型的ではありますが(笑)、個人事業主様向けの制度を整理して、ご紹介したいと思います。
国民年金基金
自営業者が任意に加入し、基礎年金に上乗せして給付を受け取るための年金制度です。
「2階建て」なんて言われてます。
国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は全額所得控除ですので、節税となります。
また年金をもらったときは公的年金等の控除対象となります。
公的年金はもらった年金全額には税金がかからない制度となりますので、
支払うとき、もらうときダブルで節税効果が得られます。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主様が拝評したとき、その後の生活安定を図るため、資金を予め準備しておく共済制度です。
この制度に対する掛け金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除を受けられるため、節税になります。
もし廃業などして受け取る際にも、一時払いでもらう方法と、分割でもらう方法が選べます。
一時払いでもらうと、それは退職所得として取りあつかわれます。
退職金は老後の生活資金としての性格を持つものですから、かなりの部分が非課税となります。ここでも大きく節税効果が得られます。
分割でもらう場合は公的年金等の控除対象となりますので、国民年金基金同様、こちらも節税効果が得られます。
個人型の確定拠出年金制度
いわゆるiDeCoと呼ばれます。
毎月掛け金を拠出し、それを加入さ自らが指図し投資に回します。
そして拠出した元本とその運用益が、将来受け取る給付金の原資となります。ただし投資ですので元本割れのリスクは伴います。
この制度では、拠出した掛け金は小規模企共済等掛金として取り扱われるので、全額が所得控除となります。
そして発生した運用益には課税がありません。
そして受け取る際は、これまら一時受取りと年金が選択でき、それぞれが退職所得、公的年金所得となるため、
所得控除を受けられるため節税になります。
これがいわゆる株式や投資信託だと、拠出した資金は所得控除もありませんし、運用益なら課税されますから、似ていますが税金優遇は大きく異なります。
個人年金
個人年金とは、個人事業主様が任意で民間の生命保険等の金融機関と契約し、
計画的に資金を積み立て、積立金とその運用益を年金または一時金として受け取るものです。
課掛け金は生命保険控除となりますが、いくら支払っても10万円ほどしか所得控除が無いため、節税効果は上記の3つよりは薄くなります。
受け取る場合は年金受給であれば雑所得となり、公的年金等控除はありません。
一時受取は一時所得となるため、退職所得と違い、課税額は多くなります。
民間の生命保険をたくさん入っていても、
意外と、個人年金基金や小規模企業共済を利用していない方も多いよいうです。
自分の老後は、お上頼みだけとせず、
知識を蓄えて、準備をしていきましょう。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
2019年6月21日
連休と有給休暇
10連休!
終わりましたね~。
皆さまはどうお過ごしだったでしょうか。
連休をバカンスとしてとらえる文化
10連休なんて、日本人である私たちには馴染みがありません。
欧米では10日どころか2週間、一ヶ月という長期休暇を取る文化があるようです。
すごいですね。
休暇というよりバカンスというそうです。
「休む」そのものが目的ではなく、いかにリフレッシュするかが目的なのだと思います。
日本人は連休疲れでぐったり、休み明けは憂鬱、なんて記事も目にします。
やはり文化の違いなのでしょうね。
有休の計画的付与
日本でも働き方改革で、今年度から「年5日の有給休暇の取得義務化」が始まりました。
従業員に年間で5日間の有給休暇を与えなければならない、と義務付けられました。
経営者の皆さんには、これをプラスにしてほしいものです。
数年前、認可保育園の園代表として立ち上げたとき、年休の計画的付与制度(計画年休)を使って
9連休を全ての従業員さんに取らせる制度を採用しました。
計画的付与制度(計画年休)は、
「従業員の有給休暇のうち、最低5日間は、本人の自由意志で取らせなければならない。
それを守った上で、有給休暇を消化させるために、
会社が計画的に休暇を設け、有給休暇とすることができる」
というものです。
つまり、会社が指定した日に有休を取らせるものです。
ただし、この計画的付与制度(計画年休)は「労使協議によって協定を結ぶこと」を前提としています。
従業員の了解を得ないで、会社が勝手に「お盆休暇は有給休暇扱いにする」ことはできません。
そりゃそうですよね。
ですから、保育園では年度の最初に、全員から取りたい日を5連休、月曜日から金曜日で希望を聞きました。
もちろん経営上忙しい時期もありますし、他の従業員とも日程がバッティングすることもあります。
そこは話し合い。
上手にバランスよく年間に振り分けます。
計画的に付与することで、経営者サイドは予め人の手配ができます。
従業員サイドは旅行などを早めに計画、準備できるというわけです。
保育園ですから、
リフレッシュして、気持ちも新たに保育の現場に戻ってきて、
パフォーマンスを上げて、子どもたちを喜ばせてください、
それが保育士さんたちのリフレッシュの意味ですよ、と共有しました。
だから休み中は、遊んでもいいし、旅行してもいい。
また、自然と戯れても、スキルアップのための勉強でもいいんですよ、何でも自由にしてくださいとお願いしました。
するとその制度がとても喜ばれ、リクルートにもプラスに働きました。
同じ給料でも、働き甲斐があるといって私たちの園に募集してきてくれました。
有給のとらえ方と使い方
せっかくの有休を使っても、休み明けにパフォーマンスが落ちては元も子もありませんね。
経営者も従業員も「休暇」をどうとらえるか、が大切です。
日本人は勤勉で働き者と言われてきました。
とはいえ新しい世代では価値観も違います。
休みを上手に使って、休み明けにリフレッシュして仕事場に戻る、
経営者も従業員もニッコリ笑顔でスタートしたいものです。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年6月20日
創業時に知っておきたいポイント
今月初めに春日井商工会議所主催の「かすがい創業塾」に講師として行ってまいりました。
およそ20名ほどの受講生の前で、60分と限られた時間でしたが、
税務会計において、起業するときの要点をお伝えしました。
起業するときのポイント
1.青色と白色、どちらで申告しますか
2.経理は出納と記録です
3.会計ソフトの選び方
4.個人事業と法人設立はどちらがお得?
5.開業・創業時の届出は
6.最初は免税だから。いえ消費税の検討は必須。こわいぞインボイス。
7.税務調査を恐れるな
8.あなたに合う税理士を探してください
すでに起業してバリバリ事業を進めていらっしゃる方には、
「ふむふむ、あれね」
とか
「最初はわかんなかったんだよなぁ」
経験からすでに理解していることも多いかと思います。
やはり、専門家から起業前に聞いておくことは有意義ですよね!
その意味では春日井商工会議所さんの取組みはナイスです!
「知ってる」と「知らない」では大違い
無知だと損をすることが税務の世界です。実はトラップがいっぱい潜んでいます。
その中で特に注意しておきたいのが、
「青色申告」と「消費税の届出」
です。
青色申告でのうっかりは、
「事業が軌道に乗ってから」
「最初だから青色でなくても」
「届出を出すタイミングが遅れて」
などの理由で白白申告となってしまうことです。
だいたい事業を始めて最初の年というのは、黒字化が難しいですね。
その時に出てしまった赤字がどうなるかご存知でしょうか。
青色申告であれば、繰越欠損と言って、翌年に赤字を繰越すことができ、
翌年の黒字と相殺ができるのです。
つまり2年目の税金が大きく減るということです。
しかし白色申告だと繰越欠損は認められません。
翌年の黒字にはしっかり課税がされます。
そして、もう一点は、青色専従者給与の届出です。
実はコレ、『青色申告』の届出と別に出さなければならないのです。
もしパートナーが事業にもっぱら従事していれば、家族であっても、
原則として全額が経費として認められます。
しかしこの届出が出ていないと、白白申告と同様の経費しか認められないのです。
税務署に行って「開業する時の届出をください」と言っても、この書類をもらっていない、
そんなこともあるようです。
皆さま、気を付けてくださいね。
そして消費税の届出です。
「事業の最初は免税でしょ、何か必要ですか」
確かに、最初は免税事業者ですが、
最初の年に高額の設備投資をするときは要チェックです。
ひょっとしたら課税事業者にあえてなれば、還付を受けられるケースもあります。
ここは慎重に検討してくださいね。
そして今年の秋に控えている消費税増税。
税率だけでなく、制度そのものが変わります。
そう、インボイス制度の導入です。
経過措置が設けられていて、3年後から本格的に導入となります。
「なんだ、影響はないよね」
そんなことはありません。
実は自分たちが免税事業者だから関係ない、とはいかないのです。
この制度が運用されると、得意先から「課税事業者になってください」と言われる可能性が高いと思ってください。
「え?なんで」
なぜなら得意先の消費税額が増えてしまうからなんです。
「じゃあ、仕方ない。お商売だから従うしかないね」と諦めますよね。
それではと、「消費税課税事業者選択届出」を出すことにします。
そのとき、税金が安く計算されるからと簡易課税を選択します。
ところが、今の税法だと、課税事業者となった後、100万円以上の固定資産を買うと、取得の日から3年間は簡易課税が認められない!!となっているのです。
100万といったら車一台でも買ってしまったらアウトの金額ですよ。
マジか~~!
そんなことになっているなんて。
知っていると対応も変わってきます。
起業するときこそ、
専門家にしっかりと相談することをお勧めします。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年4月17日
変えるものは
4月も半ば、春らしく少しずつ暖かくなってきました。
そうこう言っている間に、すぐに超大型の連休が始まりますね。
街には真新しいスーツを着たフレッシュマンがあふれています。
せっかく入社したからには「五月病」にならず、
元気に会社を通じて、社会へ貢献してくれるように祈っています。
企業は人なり
会社経営では、人が命といっても過言ではありませんね。
「企業は人なり」
経営の神様、松下幸之助さんもこうおっしゃっています。
関与先に行けば、どこも人不足で大変だとお聞きしています。
せっかく入った新入社員を大切に育てたい、そう思っている経営者様も多いことでしょう。
変化すること
とはいえ、経営は試されごとの連続。
うまくいくことが少ないのが現実でしょう。
人の悩みもつきません。
「なかなか思うように育ってくれなくて」
「文句ばかりで困る」
など経営者の皆さまのぼやきもよく聞きます。
さて、何を変えるのか。
ダーウィンの進化論で(どうも後付けで言われている内容のようですが)
「強いものが生き残るのではない 変化できるものが生き残るのだ」
ん~、名言!!
先日、躍進を続け東京オリンピックを確実にしたバスケットボール男子のニュースを拝見しました。
ご存知の方も多いと思いますが、日本バスケット協会の会長は三屋裕子さんです。
そう!女子バレーボールの偉大な選手だった方です。
低迷するバスケットボール男子を変えるために招聘されたのですが、インタビューでは大変興味深いお話しをされました。
全く畑違いで、バスケットボールのことを全く知らないわけですから、
協会の元バスケットボール選手たちだった幹部からはアレルギー反応がすごかったそうです。
でも、全く知らない人間だからこそ、変わることを恐れずにできた、とも。
その結果、何が変わりましたかと問えば、
「変わることを恐れなくなった」
そうです。
変わること、変えるもの。
その難易度は、
環境<行動<能力
個人の能力を変えることは難しい。
だから、まずは環境を変える。
環境が変われば、行動が変わってくる。
人の悩み、能力を変えようと思わず、
できることから始めてみませんか。
それは会社の環境から。
勇気をもって、自分自身を変えていくこと、かもしれません。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年4月4日
消費税増税で思うこと
さて新年度になりました。
新元号も発表されて、いつもと違ってさらに気持ちが引き締まる感じがします。
税制では、今年度は消費税率が8%から10%に上がります。
とても大きな変化ですね。
消費税増税は間違いなく経済のブレーキがかかる
消費税がわが国に導入されたのが、平成元年でした。
消費税は平成と共に歴史を刻んできたのです。
感慨深いですね。
最初は3%でしたが、平成9年に5%へ上がり、
平成26年に8%へ上がりました。
共通するのは消費税増税がなされると
景気は悪化する、またはブレーキがかかる
ことは歴史が証明しています。
この秋に消費税は確実に上がりそうです。
政府指標では景気良好と言われていますが、長いデフレをなかなか脱せず、
国民の皆さんが実感できずにいます。
さらに世界経済も不安含みで下がり局面に入っているようです。
消費税をこのタイミングで上げるべきか、私はどうかなぁと心配しています。
税制はシンプルでなければならない
税理士の視点から言えば、税制はシンプルでなければ、と思います。
政府は消費税の増税を和らげるために、
軽減税率に加え、ポイント還元など様々な調整を行っています。
政治とは調整である
といえば、それはそれでよいのでしょうが、税制の本質から離れていると言わざるを得ません。
付け焼刃的に、ごまかすようなことであってはいけないのです。
そもそも消費税をなくすとどうなるのか
そもそも消費税は上げないといけないのでしょうか。
実は消費税が導入されたときから、法人税率はずっと下がり続けています。
ご存知でしたでしょうか。
ちょっと乱暴に言えば、消費税で増えた税収増と法人税の税収減とトントンぐらいなのです。
一方、日本の国債残高は政権が自民党であろうと、民主党であろうと、増加の一途です。
国債を「借金」と呼べば、大変な財政状態と言えます。
未来を担う子どもたちにたくさんの借金を残してはいけません。
私もそれは望んでいません。
だから財政再建のために増税が必要なのです。
国民の皆さん、我慢してください。
BY 財務省。
聞けばもっともですが、はたして消費税を上げなければいけないのでしょうか?
マクロ経済学では、債務が大きくなることは決してマイナスではないとする考えもあります。
会計の世界でも「貸借対照表」でみれば債務が増えれば資産が増えます。
全体の大きさが大きくなれば、それは経済成長とみなします。
つまり、債務が増えること=よくないこと、ではないのです。
国債を発行して買っているのは誰でしょうか。
今もっとも買っているのは日本銀行です。
外国ではありません。
ギリシャのように財政破綻したらどうなるのか、という意見もありますが
わが国の場合に照らしあわせて議論する必要があるのではないではばいでしょうか。
また、たくさんの紙幣が国中に出回っているので、
インフレの危機ですとか、出口戦略なんてことが言われています。
はたして世界の経済関係の中で日本を考えると、インフレが起きるのでしょうか。
マクロ経済学ってのは、全く分かりません(苦笑)。
ただ一つ言えるのは、
日本の財政がひっ迫しているので消費税を上げるのはやむなし
ではないような気がします。
皆さんはどうお考えになりますか。
この答えは10人いたら10人答えが違うかもしれません。
だからこそ、勉強や議論が必要なのではないかな、
ポイント還元とか、そういう問題ではないと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!