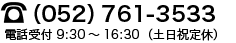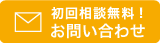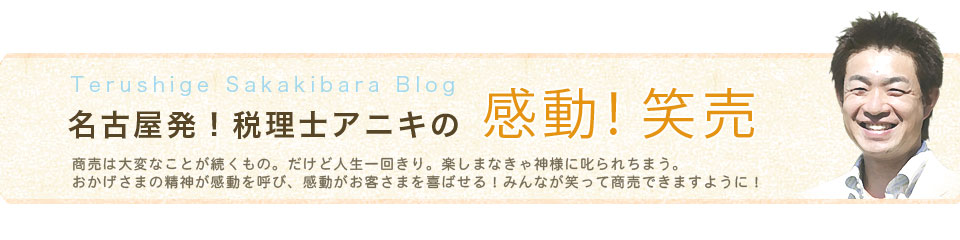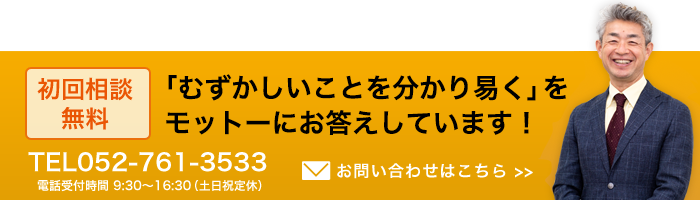2019年3月1日
個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金
さて確定申告も後半戦です。
個人事業主様から最も多い質問は
「これって経費になりますか?」
があります。
費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。
ですので判断基準として、
事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの
となります。
したがって税金でも経費になるものがあります
これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。
会計上は「租税公課」という科目で表します。
個人事業税は経費です
経費性の判断は先にも述べました。
例えば自動車関連の税金。
事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。
細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、
運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。
(税務調査では消費税計算で問題になります)
契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。
事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。
個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。
起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)
個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。
税率は事業内容によって異なり、3~5%です。
この個人事業税は経費になります。
市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。
ご注意くださいね。
消費税の経費はタイミングによる
消費税も経費になりますよ。
税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、
経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。
一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。
そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。
では経費になるタイミングはいつ?
消費税は支払ったときに経費にします。
しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。
つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。
ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、
毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。
所得税と住民税は経費にならない
確定申告で計算して納める所得税、
申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、
これらの税金は、経費にはなりません。
事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。
おや?
そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年2月18日
青色申告の取り消し
さて、確定申告の受付が始まりました。
これから一か月間、私たち税理士は繁忙期です。
税理士が関与している事業主様は青色申告の方が多いです。
青色申告は特典があり、届け出を出して、しっかりお帳面を作れば、かならず節税になります。
一方で取り消されることもあるのです。
期限後申告となった場合
確定申告の期限は3月15日です。この期限に間に合わず、申告したら「期限後申告」となります。
電子申告なら大丈夫ですが、郵便物などは消印基準となるので、夜にポストに入れたのだけど、集荷が翌日だったりすると期限後申告になってしまいます。
昔はエックスパックは信書扱いでなかったため、消印基準の対象とならず、到達基準で基準後申告になった…こともあります。
期限後の申告は加算税などペナルティが課せられるだけでなく、
2事業年度にわたって連続して期限後申告を行った場合、青色申告の承認が取り消されてしまう
ことになります。
うっかりが無いようにしたいものですね。
仮装・隠ぺいがあった場合
仮想隠蔽とは、悪意を持って税金をごまかす、所得を隠すなどの行為です。
国税庁は仮装隠蔽行為の要件について、次のように例示をしています。
- いわゆる二重帳簿を作成していること。
- 帳簿、原始記録、証憑書類などを破棄又は隠匿していること。
- 帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による証憑書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算。
- 帳簿書類の作成又は記録をせず、売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること。
内容を見れば、あきらかに悪いことしていますね~
嘘はいけません。
ペナルティも重く、追徴の税金額の40%の罰金が加算されます。
この仮想隠蔽の金額が大きいと青色申告の取り消しがなされます。
複式簿記の帳簿で作っていない場合
青色申告の要件は複式簿記で計算書類を作ることです。
ですのでこの帳簿を作っていない、税務署から提出・閲覧を求められても応じない、帳簿作成の指導に従わない
と青色申告を取り消されます。
青色を取り消されると、一年間は白色申告となり、様々な特典が受けられません。
これもまたもったいないですね。
正直に、誠実にお帳面をつけ、ごまかさず申告する。
これが大切になります。
「ちゃんとやっている」そう独断で判断せず、専門家に見てもらいましょう。
税理士に相談したり、見てもらうと安心できると思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年2月1日
青色申告の特典
まもなく確定申告が始まります。
2月16日から3月15日までが申告の時期です。
個人で事業をしている皆さまは決算書の作成に忙しい時期ですね。
もちろん青色申告を選択されていますよね!?
「え?していない」
それはもったいないお話しです。
青色申告の特典
申告の方式は2種類あって青色と白色の申告があります。
青色申告をしようとするなら税務署の予め届け出をしておきます。
昔の申告書はすべてが紙ベースでした。
だから青色申告の申告書は青色だったんですよ!
もちろん用紙が違うだけではありません(笑)
青色申告には特典があります。
主なものは次の4つです。
青色申告控除がある
純損失を3年間繰り越せる
家族への給料を全額経費にできる
30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる
青色申告控除とは
税金計算では、利益に税率をかけて税金を計算します。
青色申告なら、その利益からさらに65万円(2020年からは電子申告が要件となります。紙申告なら55万円)を引いてから税率をかけるのです。
つまり65万円に対する税金が節税になりますね。
青色申告を選択すると、帳面をしっかり作らなければなりません。
「複式簿記」の方法で決算書を作るのですが、手書きで作るなら簿記2~3級レベルが必要です。
しかし今は安価な経理ソフトがたくさんあります。
お小遣い帳や家計簿を書けることができる人なら、そんなに難しくはありませんよ。
純損失を3年間繰り越せる
もし赤字が出てしまったら、税金計算はどうなるのでしょう。
もちろんその年は税金はかかりません。
しかし青色申告を選択していると、赤字の分を翌期へ繰り越すことができるのです。
例えば100万円赤字が出たとしましょう。
その年は税金がかかりません。
翌年に100万円利益が出たとします。
普通なら100万円に税率をかけて税金を支払うのですが、
繰り越してきた赤字100万円と利益の100万円を相殺します。
すると所得はゼロとなってしまうので、翌年も税金を支払わなくて済むのです。
事業を始めた年は、まだ売上もおぼつかなく、経費もたくさんかかります。
赤字となることも多いので、開業するときは青色申告の選択をしておくといいですね。
家族への給料を全額経費にできる
小さいお商売だと、配偶者と二人で力を合わせて事業していくことも多いですね。
税法上は配偶者への給料は制限がかかります。
お手盛りで身内にお金を支払うことができるのに、それを経費と認めると税金逃れになる恐れがあるからです。
しかし青色申告なら、従業員へ支払う給料と同じ取り扱いで経費となります。
注意するのは、配偶者控除が受けられなくなることと、青色申告の届け出とは別に届け出が必要になるということです。
30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる
お商売に使う備品や車などは固定資産といいます。
これらを買うために支払ったお金が10万円以上だと、全額がその年の経費になりません。
固定資産は、何年にもわたって売上を得られる効果があるとみなされるので、取得に要した費用は毎年に振り分けて分割していくのです。
これを減価償却といいます。
青色申告だと10万円以上30万円未満の固定資産なら、買ったその年の経費とできます。
パソコンやデスク・チェア、ひょっとしたら中古車なども対象になるかもしれません。
いずれかは経費になるのですが、やはり支出があったときの税金が安くなる方が有難いですよね。
このように青色申告の特典はなかなか節税になります。
お商売を始めるときなどは、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年1月15日
税金は誰のために使うの?
明けましておめでとうございます。
今年最初の記事になります。
年初らしく少しかたい話をしたいと思います。
年の初めは税制改正まっただなか
毎年変わる税制ですが、いつ変わるのかご存知でしょうか。
租税については、憲法84条に租税法律主義といって
税金のことは法律にしないとだめですよ
そう定められています。
では法律にするところってどこでしょう?
そうです、国会ですね。
税制は必ず国会で審議され決まっていきます。
税制改正は、まずは与党である自民党税制調査会(略して自民税調)から始まって、政府税制調査会(政府税調)を12月に経て、原案がまとめられます。
そして年明けに国会で審議が行われ、決まったら施行される、こういう流れです。
税金の使いみちが大切
では税金って、いったい誰のために使われるのでしょう?
私は
税金は入口より出口に関心を持ってください
と常々言っています。
入口は「どう集めるか」。
つまり消費税を10%に上げて集めるとか、所得税で集めるとか、そういうことです。
出口とは「どう使うか」。
集めたお金をどの分野に、どれくらい配分していくか、ということです。
やはり国民の皆さんが一生懸命働いて納めたお金ですので、しっかり国民のために使っていただきたいですよね!
とはいえ、どう使ってほしいかは、これまた個人の要望もそれぞれで違います。
だからこそ、国会議員さんは国民の代表として、しっかり使いみちを議論してほしいと思います。
使いみちで重要な視点
少し前に、ある方から聞いてはっとしたことがあります。
それは「国」と「国家」は違うということです。
私は日本国で生まれ、日本国で育ち、
四季折々の自然や、海の幸山の幸など美味しいものがあって、
それこそ爆弾も落ちてこない時代を生きてきました。
すごいことですよね。
私はこの国のことは大好きです(ダメな部分もいっぱいあるけど、それも含めて)。
このままずっと続いてほしい、そう願っています。
そのために税金を使ってほしい。
未来とは子どもたちです。
子どもたちが健やかに育ち、貧しくならないような環境を作ってほしいと願っています。
「国」は家族の延長線上にある言葉だと思います。
愛するわが子や家族、ご縁のある人、広げていけばそれが「国」となるのです。
「家族愛」の枠を広げていくと「祖国愛」となるともいえます。
決して強制されるものではありません。心の中から発露するものです。
明治から昭和の時代には「お国のために」といって、たくさんの先輩方が亡くなりました。
その方たちが守りたかったのは、家族であり、家族の住む街である場所、「ふるさと」であったと思うのです。
でも「国家」と言葉を変えたらどうでしょうか。
辞書で引けばわかりますが、国家とは「多数人から成る社会集団で統治権を有するもの」とあります。
すなわち政府ですね。
国家のために税金を使う、国家のために命を投げ出す。
そう言われると違和感があります。
政府の人間が「お国のため」に使うと言っても騙されてはいけません。
それは「国」のためなのか、「国家」のためか。
国家は無くなっても、国(民)は無くならないのです。
国会議員の皆さんは国民代表です。
その方々が政府(国家)をまとめているわけです。
誰のために、何のために税金を使うのか。
わが国は国民主権と憲法で規定されています。
本質的な目的をしっかり見据えて頂きたいと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年12月20日
年末調整 還付のタイミング
12月は年末調整の時期です。
年末調整とは
年末調整をひとことでいうと、「サラリーマンの確定申告」
といえばわかりやすいでしょうか。
でも、面倒な申告書を書く必要はありません。
日本では源泉徴収制度を取っているため、給与以外に所得がない場合は
会社や事業主さんが本人に代わって税金計算をすることになっています。
もちろん、他に所得がある、医療費控除を受ける、住宅ローン減税を初めて受ける、そんなときには確定申告をする必要があります。
源泉徴収制度では、毎月「多め」に源泉税を天引きするため、年末調整で正しい税金計算をすると、払いすぎとなっている場合がほとんどです。
多くの会社では、12月のお給料と一緒に還付がなされます。
年の瀬に少しでもお金を余分にもらえると、なんだかお年玉をもらったみたいでおトクなように感じますね。
少し前までは、お給料は振込でも、年末調整の還付金だけは現金でください、なんて従業員さんからリクエストされるところもありました(笑)。
12月のお給料と一緒に還付金を戻す年末調整を、「給与年調」と私たちは呼んでいます。
一方、給料を支払ってしまってから、翌月のお給料と一緒に還付する場合もあります。これを「支給後年調」と呼んでいます。
お給料の締日と支払日を決めるポイント
経営者のみなさんにしっかり決めておいてほしいのが、お給料の締日と支払日です。
お給料の支払うタイミングは、一度決めると変えることはなかなか大変です。
従業員さんからすれば、月末にもらえるはずのお給料が、
会社都合で、翌月10日に変更されてしまったら困りますよね。
そして、お給料が締まっても、すぐ支払いといかないのです。
給与計算もあるし、なにより計算間違いがあってはいけないので、チェックする時間と手間が必要です。
また金融機関には、支払いデータを3営業日前までに渡さないといけません。
土日だけでなく祝日など挟むと4,5日必要な場合もあります。
ですから、締日と支払日は通常、5日以上は開ける方がよいでしょう。
年末調整も同様に考えます。
12月は給与計算に加えて、年末調整計算するわけですのでいつもより手間がかかります。
特に大変なのが、20日締めの25日払いの会社です。
12月は23日が天皇誕生日(平成が終わっても祝日として残るのでしょうね)であるため、
年末調整と給与計算が重なって大変です。
20日締めの末日払いも、年末は銀行の営業日が早まると時間的にタイトになりがちです。
これらのケースは
「給与年調」とせず、「支給後年調」にすると、事務の負担が軽減できます。
私たち税理士事務所も助かります(苦笑)。
そして給料の支払いで気を付けておくもう一つのポイントは、
資金繰り
です。
従業員さんへのお給料の支払いが遅れたり、払われないことがあってはなりません。
会社や事業のお金の流れを見て、支給日を決めておきましょう。
お金に余裕のあるタイミングで支給する日を決めるのです。
例えば月末までに売上の入金があるのなら、お給料日は翌月10日に設定します。
健康保険や介護保険などが売上になる業種なら、25日払いは避け、月末払いにします。
事業が発展してくると、売上の金額も大きくなりますが、従業員さんへのお給料の金額も大きくなります。
一度決めたお給料の締め日と支払日を変えるのは大変です。
慎重に決めていきたいものですね。
こうした事務作業の相談も私たち税理士にお尋ねくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年12月5日
個人事業主さん、年越ししないように師走で行っておきましょう
「先生」も走る師走。
早いものですね~
年の瀬となれば、いろいろしたいことがありますよね。
年賀状の手配、クリスマスの準備、忘年会、
経理の方であれば、年末調整。
大掃除をして、お正月をすっきりと迎えたい。
そして12月は、個人事業主さんにとって決算の月でもあります。
忙しいですね!
売掛金は回収できていますか
さて売り上げたお金はちゃんと得意先様から回収されていますか?
せっかく売り上げたというのに、お金になっていないのであれば、元も子もありません。
会計の基準では、発生基準といって売上は入金したときではなく、
「モノ」や「サービス」の引き渡しが完了して、お代の請求をしたときに、
売上として経理することになっています。
税金計算上は利益に税金がかかるので、
いざ税金を支払おうとするときに入金がまだされていないと、
「お金が足りない」
と困ります。
得意先からの売掛金の回収が遅れているとき、
また回収ができないような状態になっているときは注意が必要ですね。
貸倒損失として経費にするには
もう回収できそうにない、
利益として税金がかかるくらいなら、貸倒損失として経費に落としてしまおう、
それもありだと思います。仕方ありませんね。
ただ税法では貸倒損失として経費になるのは要件が定められています。
① 債権者集会や裁判所などで返済額が決定し、それ以外が切り捨てられることがはっきりした場合
② あきらめて債務免除の通知を送った場合
③ 一定期間取引停止があって、そのご弁済がない場合(ただし要件あり)
この3つです。
①のように、相手が倒産など法的な手続きを取って、通知が来ればいいのですが、
行方知らずや、手続きが遅れていてなかなか進まない、そんなこともあります。
決算月はその判断する時期でもあります。
お金になりそうにない、そう判断したら思い切って債務免除の通知を送ってしまいましょう。
債務免除の通知を「内容証明郵便」の方法で相手へ送ります。
受け取ったかどうかに関係なく、②の要件を満たし、貸倒損失として全額が経費と認められます。
一年の最後にすっきりとして、
新しい年を迎えましょう。
悔しいけど、新たな気持ちで商いしていくために必要なことだと思います。
イチロー選手も三振したとき、こういって切り替えているそうです。
「NEXT!」
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年11月20日
評価は誰がするのか?一度立ち止まって考えてみました。
いま「働き方改革」の取組みが様々なところでなされています。
女性活躍、
長時間労働、
非正規と正社員の格差是正、
同一労働同一賃金、
高齢者の就労促進、など枚挙にいとまがありません。
その中でも、私がNPO活動しているファザーリング・ジャパンで推進しているのが、イクボスです。
イクボスとは
ファザーリング・ジャパンでは子育て支援を目的としているので、今までは「イクメン」推しでした。
そのせいでしょうか「イクボス」というと、子育てに頑張っている社員を応援する上司、と思われがちです。
しかし、ファザーリング・ジャパンが定義している「イクボス」は少し違います。
「イクボス」とは、
職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス(仕事と生活の両立)を考え、
その人のキャリアと人生を応援しながら、
組織の業績も結果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司(経営者・管理職)のことを指します
(対象は男性管理職に限らず、増えるであろう女性管理職も)。
決して、育児に頑張っている社員だけを応援するわけではないのです。
部下を育て、
会社を育て、
社会を育てる。
高い理念を秘めているのです。
自分もこうありたいですね(苦笑)。
職場で部下を評価する
経営者・管理職になれば、部下を育てながら、評価をしていかねばなりません。
そこには公正な判断と明瞭な基準が必要になってきますね。
「俺が法律」「思い込み」で評価される部下はたまったものではありません。
だから、
経営理念だったり、行動指針だったり、開示された評価基準を、
常日頃から部下に伝えておくのです。
評価する側、される側が同じ認識であることが大切ですよね。
経営者は誰が評価する?
イクボスになろうと、部下の言葉に耳を傾けたり、
部下から評価される仕組みを取り入れている会社もあるようです。
私は立場上、たくさんの経営者にお会いしてお話しをうかがいます。
お金の話だけでなく、「人」の話も多いです。
時に、部下からの批判にさらされている経営者の悩みを聞くこともあります。
そんなとき、私が大好きな相田みつをさんの言葉が思い浮かぶのです。
「批判はしたけど じぶんにできるだろうか」
もちろん、批判を受けた側がこの言葉で返すことは違います。
あくまでこの言葉は自分に向けて、謙虚なこころで自問するものです。
経営者だけでなく部下もこの言葉をかみしめていただきたいと思います。
経営者と雇われている側では、おかれている立場が全く違います。
だから経営者を評価するのは部下ではないのです。
経営者の評価はお客様が決める
のだと思います。
経営者はそれを真摯に受け止め、日々を頑張っているのです。
税理士は、経営者を評価する立場では決してありません。
お客様から嬉しい評価をいただいたとき、一緒に喜び、
お客様から悔しい評価をいただいたとき、励まして一緒にカイゼン点を考える、
それこそがパートナーである税理士の役割だと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年11月11日
株の売買で儲けたときの税金は、なぜお金持ち優遇だと言われるの?
年明けの国会に向け、税制の議論が始まります。
兼ねてから株式の売買で生じた利益に対する税金は、欧米のそれに比べて低く抑えられているとの指摘もあり、
見直しや議論が必要とされていましたが、今年の税制改革から早々に【議論しない】と外されました。
税金は「儲け」にかかります
まず税金の計算についておさらいしましょう。
税金は「儲ける」とかかります。
「儲ける」とはすなわち「トク」をすると言ってもいいでしょう。
お給料をもらって「トク」をする
生命保険が満期になってお金が入ってきて「トク」をする
お商売で儲けて「トク」をする
土地や建物を売って「トク」をする
株を売って「トク」をする
そんなとき、税金を納めます。
株式の売買益の課税はお金持ち優遇である?
では、なぜ株を売った「儲け」が、今の税金計算だとお金持ち優遇だと言われちゃうのか?
それは株式をはじめ金融資産に起因する所得は、分離課税で税金計算されるからなのです。
所得税は、二つの税金計算の体系となっています。
ひとつは総合課税で、もうひとつが分離課税です。
通常の税金計算は総合課税で行われますが、
株式の譲渡益や、不動産の譲渡益など別に定めるものは、
総合課税と分離して計算を行う、
これが分離課税です。
総合課税の税率は累進課税といって、所得が増えるほど高くなっていきます。
一番安い税率で5%、一番高くなると45%(高い!)です。
お金持ちの方は、お金に余裕があるので(これを担税力といいます)、
たくさん払ってね、ということなのです。
しかし、分離課税での税率は、一律20%。
どんなに儲けが出ても税率は変わりません。
お金持ちの方には、総合課税ではたくさん払ってもらっているから、
分離課税では抑えめにしますので、チャラにしてね、そんなところでしょうか。
税金ではよくこういうことがなされます。
増税するばかりだと納税者に不満がたまるので、
いくらかおまけをして、調整しましょうという魂胆(笑)です。
課税庁は、「公平」な課税を実現するため、なんて説明します。
うまいこと言いますなぁ。
しかし、よく考えてください。
株や不動産をたくさん持てる人は誰でしょう?
一生懸命を汗かき、お給料もらう人、事業で頑張っている人は総合所得でしっかり課税されます。
一方、「金持ち父さん」のように不労所得で儲ける人は、分離課税なのです。
だから不動産や金融商品をたくさん持っている人は、
持てば持つほど、低い税率の恩恵を得られるのです。
給料で1億円もらったら、4,500万円が税金ですが、
株で1億円儲けたら、2,000万円の税金で済むということです。
あくせく働く必要がないから、不動産や株を買いますよね。
いつも税金の使い道にうるさい私ですが、
やはり、課税の公平性を保つというのなら、一般庶民、広く国民の皆さんが
納得
するような税金のかけ方にしてほしいものです。
とはいえ、株を売った人、不動産を売った人
いまは通常の税率に加えて復興税もかかっていますし、
長期短期の保有で税率も変わったりします。
分離課税は様々な特例があって、複雑な計算で間違いやすいので、
信頼のおける税理士さんに訊いて申告してくださいね。
決して払いすぎないよう、また不足しないようご注意ください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年10月18日
消費税10%アップの盲点
安倍総理が早々に消費税10%引き上げを明言しました。
と同時に、増税ショックを和らげるための施策も各大臣に指示しました。
クレジットカードなどで決済されると2%の還元をするとか。
以前消費税をアップしたとき、多くのスーパーでは「消費税還元セール」と称して値引き販売しましたが、
政府は税金を還付するなんて、ありえないことを想像させるのはけしからんといって、「還元セール」という売り方を禁止しました。
でも、今回は政府そのものが「還元セール」をするようで、なんとも納得しがたいですね。
軽減税率の導入
今回は少しでも増税ショックを和らげるため、
外食を除く飲食料品と定期購読新聞に限り、税率は8%に据え置かれます。
軽減というと安くなる感じですが、ただ据え置かれただけなんですね。
言葉の印象って大きく変わりますね~。
インボイス制度で何が変わるの?
今回の改正は単に税率がアップするだけではないのです。
今までと違い適格請求書保存方式、通称インボイス制度に変更になります。
どういうことかというと、請求書や領収書に税率ごとに区分して表示しなさいよ、ということです。
「なんだ、そりゃ当たり前じゃん~」
「今まで作っていたのと、あまり変わらないね」
いえ、大きな変化が隠されているのです。
インボイス制度では、こう定められています。
国税庁の登録を受けた者から、
交付を受けた適格請求書等の保存を、
仕入税額控除の要件とする。
ちょっと専門的でピンときませんよね。
そう、実はここに盲点があります。
免税事業者が淘汰されるかも
まず、消費税の計算を理解する必要があります。
消費税を負担するのは、消費者ですが、
国に納税するのは事業者です。
納める消費税の計算はというと、
売り上げたときにもらった消費税(預り消費税)と、
経費として支払った分の消費税(支払い消費税)との差額を計算して納めます。
つまり、1000を売り上げると、その8%の80をもらいます。
経費で600使うと、その8%の48を支払います。
納める税金は差額の
80-48=32
となります。
この経費で支払った消費税のことを、
仕入税額控除
といいます。
経費として引ける分、そう考えてください。
消費税には特例があって、商いの小さい事業主には税金の納付をしなくていいとされています。
これが免税事業者です。
基準年度の売上が1000万円を下回れば、税金を納めなくていいというもの。
とはいえ免税事業者でも消費税はオンして商売することになっていますからね。
(たとえ消費税をオンしていないつもりでも、計算上は税込とみられます)
益税は出てしまいますが、税の基本思想である「弱者保護」にもなると思うので、私は良いのかなと思います。
しかし、インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行業者と認められないため、
免税事業者から仕入れたものや支払ったサービスの消費税は、
仕入税額控除として認めない
としたのです。
つまり、上の計算の例でいえば、支払った先が免税事業者だとすると
計算上マイナスできる消費税はゼロとなり、納税額は32ではなく、80となってしまうのです。
そうなれば、課税事業者から(お金を支払う側)見れば、
相手は大きなところと取引しよう
もしくは
相手に課税事業者になってもらう
と考えるかもしれません。
免税事業者からすれば、取引してもらいたいがため、わざわざ課税事業者になる、なんてこともあり得ます。
これは「弱者保護」に反する、とも言えるのではないでしょうか。
一応、経過措置が定められていて、
完全なインボイス方式への移行は4年後の平成35年10月からとされています。
仕入税額控除については、平成35年9月までは、現行と同じ100%の控除、
平成35年から3年間は80%、平成38年から3年間は50%と段階的に引き下がっていきます。
税率が上がることにばかり目が行きがちですが、
制度が変わる時には、こうしたところにも配慮が必要だと思います。
こうした税金の集め方が公平なのかどうか
厳しくチェックしていきたいものです。
制度も複雑で、まだまだいろいろと実務上の取り扱いが明らかになると思います。
不安な方は信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年10月3日
ゴルフの経費、法人と個人での取り扱いが違う!?
暑かった今年の夏も終わり、さわやかな秋晴れ、スポーツの秋がやってきました。
社長や事業主様はゴルフの季節だ!と意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ゴルフの費用は経費になるの?
ゴルフをするといろいろ支出がありますが、どんなものがあるのでしょう。
ゴルフ会員権、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代、そして道具類。
どれが経費になるのか気になりますね。
前提として、法人のケースでお話いたします。
まずは高額なゴルフ会員権です。
ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となり、経費にはなりません。
節税にならず、単にキャッシュアウトするだけなので、税理士として購入はお勧めしません。
最近はネットなどで、気軽にプレーできるところが多いので、ひと昔前のように会員権は必要ありません。
注意したいのが会員権の種類です。
それが個人会員権で無記名式法人会員権が無い場合だと、その個人に権利がくっつくことになり、
法人が支払ったお金は給与扱いとなり、所得税がかかります。
給与となるので、経費と言えば経費ですが、たいていは社長や役員さんの名義で購入すると思われます。
すると役員賞与とみなされ、法人の経費として認められない場合もあります。
次に名義変更料ですが、他人から買った場合は取得に要した費用となり、ゴルフ会員権と一体となって資産計上となります。
ただし個人会員権を別の名義に代えるようなケースでは、交際費として取り扱います。
年会費とロッカー代は、その会員権の取り扱いに準じて決まってきます。
会員権が資産計上されている場合なら交際費、
会員権が給与とされている場合なら給与、
となります。
そして、プレー代。
その目的に応じて取り扱いが異なりますが、会社の業務上必要であれば、交際費となります。
個人的な趣味でプレーしたときは給与となり、所得税が本人にかかります。
交際費であれば、誰とどんな目的でしたかを説明できるようにしておきましょう。
最後に、道具やウェアですが、給与扱いとなります。福利厚生費としても認められません。
個人事業主様はお気を付けください
税法では個人事業主様は所得税法、法人は法人税法の適用を受けます。
実は、ゴルフ会員権と年会費については、両者で取り扱いが異なるので注意が必要です。
所得税法上では、ゴルフ会員権は、
事業用資産に該当しない
こととなっています。
つまり、買っても資産計上すらできません。
ということは、その年会費は法人のように交際費にならない、ということなんです。
つまり、
個人事業主様だと、プレーしたときの費用だけが経費となるのです。
法人と同様に考えていると、経費にならず、うっかり税金がかかる、なんてことも。
楽しくプレーするためにも、
事前に税理士に聞いておけば安心ですね。
くれぐれも遊びでいくプレー代や道具、ウェアは社長自身で出すこと!
公私混同は厳禁ですぞ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!