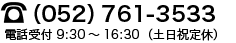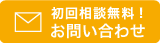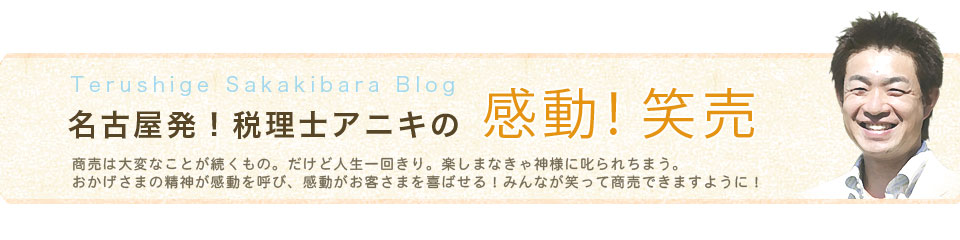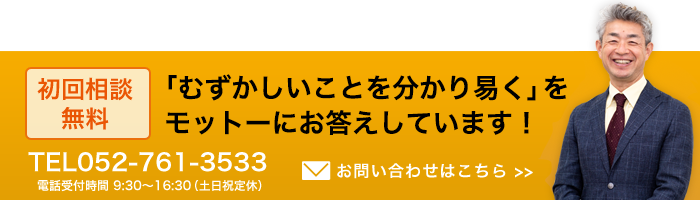2019年9月18日
いよいよ消費税の税率アップ
10月1日が迫ってきました。
いよいよ消費税率が8%から10%へ上がります。
テレビでは連日報道がありますが、
「あがらない」奇跡はもう起こりそうにありません・・・。
さて、消費税でいま最も気になるのが、
どのタイミングで10%になるの?
ではないでしょうか。
消費がなされたとき課税されるのが消費税
そもそも消費税は、いつ課税されるのか?
それは
消費がなされたとき
に税金がかかるとされています。
例えば、切手や商品券は、郵便局で買ったとき、デパートで買ったとき、
ではないのです!
使ったときに課税されることになっています。
へ~。
ね、意外でしょう。
ただ実務上は、使ったことをいちいち証明するのも大変なので、
条件付きで、買ったときに課税処理が認められています。
引き渡し基準が大原則
消費税の消費がなされたとするタイミングは、引き渡し基準によることになります。
例えば、モノを売買して手渡す、サービスの提供が完了する、そんなときです。
だから「買う約束をして、お金だけ前払いした」としても、
商品を受け取る、サービスを受けるのが10月1日以降であれば、
消費税は10%となるのです。
しかし例外もあります。
これらは経過措置といって、国税庁のホームページやQ&Aに、載っています。
限定列挙なので、シビアに判断してくださいね。
公共料金は
まずは公共料金です。
水道や電気など、検針されることで使った量が分かります。
それが月末なら問題は無いですが、皆さんの手元に来ている請求書を見て下さい。
必ずしも月末ではないはずです。ほとんどが月の途中になっていると思います。
これらは10月以降最初の検針までの分なら、8%です。
9月16日から10月15日の使用分が、10月20日に請求されても、それは8%となります。
ネットでの買い物は
通信販売は要注意です。
楽天やamazonで買い物をする方も多いでしょう。
通信販売は、引き渡し基準ではなく、発送日(出荷日)基準となります。
注文日が9月28日。
商品到着が10月2日。
どうなるでしょう?
引き渡し基準なら、商品が届いた10月2日となるので、10%です。
ただ通信販売は、発送日基準なので、
9月30日発送なら8%。
10月1日発送なら10%。
となってしまうのです。
9月末の駆け込み需要もあります。
ネットの買い物は早めに、そして出荷日を確認して注文しましょう。
航空券やUSJのチケットは
旅行の準備で買っておく、新幹線のチケットや、航空機のチケットはどうでしょうか。
こちらは利用日ではなく、支払日基準となります。
不特定多数の方に、前売りする類のものがこれにあたります。
コンサートのチケット、USJのチケットなどもこれらと同じ種類となります。
旅行の予定がある方は、9月中に購入しておくといいですね。
ただし日にち指定できるものは、念のため確認して購入するのが無難ですね。
新築の注文住宅は
契約してから、納品まで時間のかかるものは、経過措置の対象になります。
経過措置の対象になるかは、お手数ですが、国税庁のホームページで確認願います。
新築の注文住宅や結婚式の代金がそのタイプ。
3月まで契約してあれば、引き渡しが10月以降でも8%です。
ただオプション追加や仕様変更、人数変更(増えたら10%!)が、
4月以降あったものは、その対象になりません。
10月に引き渡し、結婚式があるのならその分だけ10%になります。
いかがでしょうか。
消費税が上がるからといって、不必要なものを買う必要はありませんが、
買う予定がある方は、知っていれば、安心できますね!
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年9月2日
従業員のため社宅を借りることにしました
最近、お客様へお邪魔すると「人手不足」とよく聞きます。
愛知県の有効求人倍率は、このところ常に1.9を超えて推移しています。
求人倍率は、経済が活況の時、一つの目安となりますので、結構なことですね。
企業もあの手この手で、社員を確保しようとしています。
福利厚生を充実させるのも一つの手です。
遠方から通う従業員のために、社宅を借りよう、そんなこともあるようです。
社宅の費用も経済的利益
従業員さんのためにと思い、会社が支払った社宅の費用ですが、
一定額を超えると、本人さんに課税がされます。
ご注意くださいね。
会社が支払った費用は経費となります。
ただ、それが経済的利益となると、支払家賃ではなく、給料となってしまうのです。
え、どういうこと?
前回のメルマガでもお伝えしました、経済的利益、
それは「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。
経済的利益とみなされるのは、
・特定の人だけ優遇
・常識的な金額よりもらいすぎ
の場合です。
一定範囲内までは課税されません
課税される範囲は、税法で定められています。
従業員の場合、「通常の賃借料の50%」を基準に判断します。
通常の賃借料とは、支払っている家賃のことではありません。
税務で定める通常の賃借料は、以下の計算式で求められます。
通常の賃借料=(その年の家屋の固定資産税標準額 × 0.2% + 12円×その家屋の総床面積(㎡)/3.3㎡)+ その年の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
ややこしや~。
課税される判断は、本人さんの負担割合で、以下の4つのケースが考えられます。
① 本人さんが全く負担しない(会社が全額負担)
家賃の全額が「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
② 本人さんが通常の賃借料の50%未満を負担
通常の賃借料から、実際に負担した金額を引いた残額が、
「給与」とみなされ、源泉税が課税されます。
③ 本人さんが通常の賃借料の50%以上を負担
課税はされません。
④ 本人さんか負担した金額が、通常の賃借料を超えている
課税はされません。
社宅は、アパートやマンションなど、集合住宅を借りることが多いため、
個別に、固定資産税標準額を調べることは、大変ですね。
実際相場を見ると、税務で定める「通常の賃借料」より、実際に支払っている家賃の方が高いことがほとんどです。
したがって実務上は、実際に支払っている家賃の半分は、本人さんに負担してもらいましょう、とされています。
人手不足の中、会社のお金を使って、従業員さんを確保するわけです。
いらぬ課税がされないよう、注意してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年8月2日
従業員の引っ越し費用
梅雨も明け、夏休みが始まりました。
お勤めの会社では、新学期のタイミングで、異動命の辞令が出る時期かもしれません。
また人手不足の折、就職や転職も多いでしょう。
「引っ越し費用を会社で出してあげるから、ぜひわが社に来てください」なんてお話もよく聞きます。
そんなときの税金は、どうなるのでしょう?
税金がかかるのは、会社にかかる、従業員にかかる、ふたつのケースが考えられますが、
今回は従業員の税金についてです。
経済的利益とは
会社はお給料を支払う以外にも、従業員のために、いろいろとお金を使います。
会社へ通うための通勤費、
社内での忘年会費、
結婚したり、出産したときのお祝い金、
健康診断の費用や、
研修のために支払う講師へのお金、などなど。
それらは概ね会社の経費となります。
しかし、会社側から経費となっても、従業員には税金がかかる場合があります!
それが
経済的利益
と言われるもの。
経済的利益は「現物給与」といって、源泉所得税が課されます。
・特定の人だけ優遇
・常識的な金額よりもらいすぎ
そんなとき経済的利益として税金がかけられるのです。
引っ越し費用は
では、引っ越し費用はどうなるのでしょう。
この場合の引っ越し費用とは、移動に伴う旅費や引っ越し業者に支払うお金です。
採用を決めた従業員が東京の方で、勤務地は名古屋です。
必ず引っ越しはしなくてはなりません。
借りたアパートは会社の社宅でもありません。
さて、いかがでしょう。
税務では、
転任に伴う転居のための、通常必要と認められる支出は非課税
のため、従業員の方の経済的利益として課税はされません。
新しいアパートの保証金などはこれらに含まれませんので、お間違えないようにしてくださいね。
経済的利益は税務では、その範囲が事細かに決まっています。
経営者の皆さま方は、従業員のために、そう思って支払ったのに、
従業員への給料とみなされ、課税されるなんてもったいないことがないよう、
事前に税理士に相談してくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年7月24日
住民税はちょっと違う
住民税は国税ではなく、県や市町村に支払う税金です。
住民税は国税とちょっと違うんです
住民税は賦課課税が多い
わが国での納税の中心的な制度は申告納税制度です。
申告納税とは、「自分で税金計算をして、納める」ことです。
自分で行うといっても、税制は毎年変わりますし、
申告書を作るのだってなかなか大変です。
だから、私たち税理士がそれを代理して行うわけです。
一方、賦課課税制度もあります。
これは、自分から計算するのではなく、役所が計算して
「これだけ税金を払ってくださいね」と言われます。
住民税はこの賦課課税が多いです。
主なものに
所得税
不動産の固定資産税
自動車税
それから国民健康保険税なんてのも。
所得税は、前年の所得に対して計算され、だいたい5月か6月ごろに通知が来ます。
つまりサラリーマンなら年末調整、個人事業主様なら3月の確定申告での申告をもとに計算されます。
新入社員が2年目になると、天引きされる税金が増えるのはこのためなんですね。
国税には予定納税制度があって、前年の所得税を一定以上支払っている方は、
今年の税金を前払いをすることになっています。
その通知が来るのが6月なので、去年の所得に対する住民税、
今年の所得に対する所得税(国税)を同時期に支払うことになります。
なんだか妙な感じです。
課税の判断は1月1日
課税を判断する時期、つまりどのタイミングで課税するかですが
住民税は「1月1日」がポイントとなります。
固定資産税は、その年の1月1日に所有していれば、税金がかかります。
そして1月1日に住んでいる住所地で住民税を支払います。
例えば不動産を8月に売買するとします。
この不動産の固定資産税は所有者が支払っていますから、
譲渡された人にも負担してもらおうと月数按分して支払ってもらうこともあります。
下宿している学生や、転勤しているサラリーマンなら、
住民票の住所は別の市町にある、なんてこともよくあります。
こういう場合は、1月1日に住んでいる市町に住民税を支払います。
住んでいるとは、住民票のある場所ではなく、
居所(いどころ)、生活に実態があるところ、となります。
「アレ?」っと思ったら
専門家に気軽に聞いてみてくださいね。
「へ~、そうなんだ」ということもよくあります。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年7月5日
個人事業主様の老後の備え
人生100年時代、年金以外に2,000万円(こちらは厚生労働省)、いや2,900万円(こちらは経済産業省)必要と言われて、世間を騒がせていますね。
政治家の皆さん、そして霞が関のお役人たち、
「おいおい、しっかりやってくれよ~」とぼやいてみても始まりません。
それではと、「退職してからも、元気だから個人事業主になって一生現役で働くぞ!」
そう思うかもしれません。
とはいえ、不安もつきませんね。
そこで税理士として典型的ではありますが(笑)、個人事業主様向けの制度を整理して、ご紹介したいと思います。
国民年金基金
自営業者が任意に加入し、基礎年金に上乗せして給付を受け取るための年金制度です。
「2階建て」なんて言われてます。
国民年金基金の掛け金は社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は全額所得控除ですので、節税となります。
また年金をもらったときは公的年金等の控除対象となります。
公的年金はもらった年金全額には税金がかからない制度となりますので、
支払うとき、もらうときダブルで節税効果が得られます。
小規模企業共済制度
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主様が拝評したとき、その後の生活安定を図るため、資金を予め準備しておく共済制度です。
この制度に対する掛け金は、小規模企業共済掛金控除として全額が所得控除を受けられるため、節税になります。
もし廃業などして受け取る際にも、一時払いでもらう方法と、分割でもらう方法が選べます。
一時払いでもらうと、それは退職所得として取りあつかわれます。
退職金は老後の生活資金としての性格を持つものですから、かなりの部分が非課税となります。ここでも大きく節税効果が得られます。
分割でもらう場合は公的年金等の控除対象となりますので、国民年金基金同様、こちらも節税効果が得られます。
個人型の確定拠出年金制度
いわゆるiDeCoと呼ばれます。
毎月掛け金を拠出し、それを加入さ自らが指図し投資に回します。
そして拠出した元本とその運用益が、将来受け取る給付金の原資となります。ただし投資ですので元本割れのリスクは伴います。
この制度では、拠出した掛け金は小規模企共済等掛金として取り扱われるので、全額が所得控除となります。
そして発生した運用益には課税がありません。
そして受け取る際は、これまら一時受取りと年金が選択でき、それぞれが退職所得、公的年金所得となるため、
所得控除を受けられるため節税になります。
これがいわゆる株式や投資信託だと、拠出した資金は所得控除もありませんし、運用益なら課税されますから、似ていますが税金優遇は大きく異なります。
個人年金
個人年金とは、個人事業主様が任意で民間の生命保険等の金融機関と契約し、
計画的に資金を積み立て、積立金とその運用益を年金または一時金として受け取るものです。
課掛け金は生命保険控除となりますが、いくら支払っても10万円ほどしか所得控除が無いため、節税効果は上記の3つよりは薄くなります。
受け取る場合は年金受給であれば雑所得となり、公的年金等控除はありません。
一時受取は一時所得となるため、退職所得と違い、課税額は多くなります。
民間の生命保険をたくさん入っていても、
意外と、個人年金基金や小規模企業共済を利用していない方も多いよいうです。
自分の老後は、お上頼みだけとせず、
知識を蓄えて、準備をしていきましょう。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
2019年3月1日
個人事業主様には押さえておいてほしい、経費になる税金
さて確定申告も後半戦です。
個人事業主様から最も多い質問は
「これって経費になりますか?」
があります。
費用になるということは、売上に何らかの貢献があることが必要です。
ですので判断基準として、
事業収益をあげるのに通常必要なもので、直接的なもの
となります。
したがって税金でも経費になるものがあります
これらは意外と勘違いしやすいので、個人事業主様にはぜひ押さえておいてほしいです。
会計上は「租税公課」という科目で表します。
個人事業税は経費です
経費性の判断は先にも述べました。
例えば自動車関連の税金。
事業で自動車を使っていれば、当然に自動車税、重量税は経費になります。
細かく言えば、ガソリン税や軽油税も租税公課ですが、
運送業などでなければ、租税公課でなく燃料費として処理しても、税務調査で指摘を受けることは少ないようです。
(税務調査では消費税計算で問題になります)
契約書や高額な領収書に貼るような印紙、これも租税公課として経費となります。
事業が軌道に乗ってきて、所得が出ると個人事業税がかかります。
個人事業税は所得が290万円を超えると、市町村から納税通知が届きます。
起業したてのころは来ないことが多く「突然来た!」「何これ?」とびっくりされます(笑)
個人事業税は、290万円を超える部分に税率をかけて計算します。
税率は事業内容によって異なり、3~5%です。
この個人事業税は経費になります。
市町村から納税通知が来るので、意外と経費だと思っていない方もいらっしゃいます。
ご注意くださいね。
消費税の経費はタイミングによる
消費税も経費になりますよ。
税抜き経理をしていれば、予め利益が消費税分をマイナスして計算されていますので、
経費にするというより、すでに利益計算上引かれているって感じです。
一方、税込み経理ですと、決算申告時に消費税計算をする場合が多いですね。
そうすると決算でようやく消費税額が分かるのですが、決算処理は翌年に行っています。
では経費になるタイミングはいつ?
消費税は支払ったときに経費にします。
しかし未払い経理をしておけば、その決算の年の経費として認められます。
つまり納税をした年、決算の年、どちらかを選択して経費にすることが可能となります。
ただ会計には継続性の原則といって、毎年同じように経理してくださいね、となっていますので、
毎年処理方法を変えるのは好ましいことではありません。
所得税と住民税は経費にならない
確定申告で計算して納める所得税、
申告によって計算され5月ごろに市町村から納税通知が来る住民税、
これらの税金は、経費にはなりません。
事業に直接要する費用でないことから、理由はあきらかですね。
おや?
そう思ったら信頼のおける税理士に聞いてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年2月18日
青色申告の取り消し
さて、確定申告の受付が始まりました。
これから一か月間、私たち税理士は繁忙期です。
税理士が関与している事業主様は青色申告の方が多いです。
青色申告は特典があり、届け出を出して、しっかりお帳面を作れば、かならず節税になります。
一方で取り消されることもあるのです。
期限後申告となった場合
確定申告の期限は3月15日です。この期限に間に合わず、申告したら「期限後申告」となります。
電子申告なら大丈夫ですが、郵便物などは消印基準となるので、夜にポストに入れたのだけど、集荷が翌日だったりすると期限後申告になってしまいます。
昔はエックスパックは信書扱いでなかったため、消印基準の対象とならず、到達基準で基準後申告になった…こともあります。
期限後の申告は加算税などペナルティが課せられるだけでなく、
2事業年度にわたって連続して期限後申告を行った場合、青色申告の承認が取り消されてしまう
ことになります。
うっかりが無いようにしたいものですね。
仮装・隠ぺいがあった場合
仮想隠蔽とは、悪意を持って税金をごまかす、所得を隠すなどの行為です。
国税庁は仮装隠蔽行為の要件について、次のように例示をしています。
- いわゆる二重帳簿を作成していること。
- 帳簿、原始記録、証憑書類などを破棄又は隠匿していること。
- 帳簿書類の改ざん、虚偽記載、相手方との通謀による証憑書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算。
- 帳簿書類の作成又は記録をせず、売上その他の収入の脱漏又は棚卸資産の除外をしていること。
内容を見れば、あきらかに悪いことしていますね~
嘘はいけません。
ペナルティも重く、追徴の税金額の40%の罰金が加算されます。
この仮想隠蔽の金額が大きいと青色申告の取り消しがなされます。
複式簿記の帳簿で作っていない場合
青色申告の要件は複式簿記で計算書類を作ることです。
ですのでこの帳簿を作っていない、税務署から提出・閲覧を求められても応じない、帳簿作成の指導に従わない
と青色申告を取り消されます。
青色を取り消されると、一年間は白色申告となり、様々な特典が受けられません。
これもまたもったいないですね。
正直に、誠実にお帳面をつけ、ごまかさず申告する。
これが大切になります。
「ちゃんとやっている」そう独断で判断せず、専門家に見てもらいましょう。
税理士に相談したり、見てもらうと安心できると思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2019年2月1日
青色申告の特典
まもなく確定申告が始まります。
2月16日から3月15日までが申告の時期です。
個人で事業をしている皆さまは決算書の作成に忙しい時期ですね。
もちろん青色申告を選択されていますよね!?
「え?していない」
それはもったいないお話しです。
青色申告の特典
申告の方式は2種類あって青色と白色の申告があります。
青色申告をしようとするなら税務署の予め届け出をしておきます。
昔の申告書はすべてが紙ベースでした。
だから青色申告の申告書は青色だったんですよ!
もちろん用紙が違うだけではありません(笑)
青色申告には特典があります。
主なものは次の4つです。
青色申告控除がある
純損失を3年間繰り越せる
家族への給料を全額経費にできる
30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる
青色申告控除とは
税金計算では、利益に税率をかけて税金を計算します。
青色申告なら、その利益からさらに65万円(2020年からは電子申告が要件となります。紙申告なら55万円)を引いてから税率をかけるのです。
つまり65万円に対する税金が節税になりますね。
青色申告を選択すると、帳面をしっかり作らなければなりません。
「複式簿記」の方法で決算書を作るのですが、手書きで作るなら簿記2~3級レベルが必要です。
しかし今は安価な経理ソフトがたくさんあります。
お小遣い帳や家計簿を書けることができる人なら、そんなに難しくはありませんよ。
純損失を3年間繰り越せる
もし赤字が出てしまったら、税金計算はどうなるのでしょう。
もちろんその年は税金はかかりません。
しかし青色申告を選択していると、赤字の分を翌期へ繰り越すことができるのです。
例えば100万円赤字が出たとしましょう。
その年は税金がかかりません。
翌年に100万円利益が出たとします。
普通なら100万円に税率をかけて税金を支払うのですが、
繰り越してきた赤字100万円と利益の100万円を相殺します。
すると所得はゼロとなってしまうので、翌年も税金を支払わなくて済むのです。
事業を始めた年は、まだ売上もおぼつかなく、経費もたくさんかかります。
赤字となることも多いので、開業するときは青色申告の選択をしておくといいですね。
家族への給料を全額経費にできる
小さいお商売だと、配偶者と二人で力を合わせて事業していくことも多いですね。
税法上は配偶者への給料は制限がかかります。
お手盛りで身内にお金を支払うことができるのに、それを経費と認めると税金逃れになる恐れがあるからです。
しかし青色申告なら、従業員へ支払う給料と同じ取り扱いで経費となります。
注意するのは、配偶者控除が受けられなくなることと、青色申告の届け出とは別に届け出が必要になるということです。
30万円未満の償却資産を一時期で必要経費にできる
お商売に使う備品や車などは固定資産といいます。
これらを買うために支払ったお金が10万円以上だと、全額がその年の経費になりません。
固定資産は、何年にもわたって売上を得られる効果があるとみなされるので、取得に要した費用は毎年に振り分けて分割していくのです。
これを減価償却といいます。
青色申告だと10万円以上30万円未満の固定資産なら、買ったその年の経費とできます。
パソコンやデスク・チェア、ひょっとしたら中古車なども対象になるかもしれません。
いずれかは経費になるのですが、やはり支出があったときの税金が安くなる方が有難いですよね。
このように青色申告の特典はなかなか節税になります。
お商売を始めるときなどは、ぜひ税理士に相談してみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年11月11日
株の売買で儲けたときの税金は、なぜお金持ち優遇だと言われるの?
年明けの国会に向け、税制の議論が始まります。
兼ねてから株式の売買で生じた利益に対する税金は、欧米のそれに比べて低く抑えられているとの指摘もあり、
見直しや議論が必要とされていましたが、今年の税制改革から早々に【議論しない】と外されました。
税金は「儲け」にかかります
まず税金の計算についておさらいしましょう。
税金は「儲ける」とかかります。
「儲ける」とはすなわち「トク」をすると言ってもいいでしょう。
お給料をもらって「トク」をする
生命保険が満期になってお金が入ってきて「トク」をする
お商売で儲けて「トク」をする
土地や建物を売って「トク」をする
株を売って「トク」をする
そんなとき、税金を納めます。
株式の売買益の課税はお金持ち優遇である?
では、なぜ株を売った「儲け」が、今の税金計算だとお金持ち優遇だと言われちゃうのか?
それは株式をはじめ金融資産に起因する所得は、分離課税で税金計算されるからなのです。
所得税は、二つの税金計算の体系となっています。
ひとつは総合課税で、もうひとつが分離課税です。
通常の税金計算は総合課税で行われますが、
株式の譲渡益や、不動産の譲渡益など別に定めるものは、
総合課税と分離して計算を行う、
これが分離課税です。
総合課税の税率は累進課税といって、所得が増えるほど高くなっていきます。
一番安い税率で5%、一番高くなると45%(高い!)です。
お金持ちの方は、お金に余裕があるので(これを担税力といいます)、
たくさん払ってね、ということなのです。
しかし、分離課税での税率は、一律20%。
どんなに儲けが出ても税率は変わりません。
お金持ちの方には、総合課税ではたくさん払ってもらっているから、
分離課税では抑えめにしますので、チャラにしてね、そんなところでしょうか。
税金ではよくこういうことがなされます。
増税するばかりだと納税者に不満がたまるので、
いくらかおまけをして、調整しましょうという魂胆(笑)です。
課税庁は、「公平」な課税を実現するため、なんて説明します。
うまいこと言いますなぁ。
しかし、よく考えてください。
株や不動産をたくさん持てる人は誰でしょう?
一生懸命を汗かき、お給料もらう人、事業で頑張っている人は総合所得でしっかり課税されます。
一方、「金持ち父さん」のように不労所得で儲ける人は、分離課税なのです。
だから不動産や金融商品をたくさん持っている人は、
持てば持つほど、低い税率の恩恵を得られるのです。
給料で1億円もらったら、4,500万円が税金ですが、
株で1億円儲けたら、2,000万円の税金で済むということです。
あくせく働く必要がないから、不動産や株を買いますよね。
いつも税金の使い道にうるさい私ですが、
やはり、課税の公平性を保つというのなら、一般庶民、広く国民の皆さんが
納得
するような税金のかけ方にしてほしいものです。
とはいえ、株を売った人、不動産を売った人
いまは通常の税率に加えて復興税もかかっていますし、
長期短期の保有で税率も変わったりします。
分離課税は様々な特例があって、複雑な計算で間違いやすいので、
信頼のおける税理士さんに訊いて申告してくださいね。
決して払いすぎないよう、また不足しないようご注意ください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年10月18日
消費税10%アップの盲点
安倍総理が早々に消費税10%引き上げを明言しました。
と同時に、増税ショックを和らげるための施策も各大臣に指示しました。
クレジットカードなどで決済されると2%の還元をするとか。
以前消費税をアップしたとき、多くのスーパーでは「消費税還元セール」と称して値引き販売しましたが、
政府は税金を還付するなんて、ありえないことを想像させるのはけしからんといって、「還元セール」という売り方を禁止しました。
でも、今回は政府そのものが「還元セール」をするようで、なんとも納得しがたいですね。
軽減税率の導入
今回は少しでも増税ショックを和らげるため、
外食を除く飲食料品と定期購読新聞に限り、税率は8%に据え置かれます。
軽減というと安くなる感じですが、ただ据え置かれただけなんですね。
言葉の印象って大きく変わりますね~。
インボイス制度で何が変わるの?
今回の改正は単に税率がアップするだけではないのです。
今までと違い適格請求書保存方式、通称インボイス制度に変更になります。
どういうことかというと、請求書や領収書に税率ごとに区分して表示しなさいよ、ということです。
「なんだ、そりゃ当たり前じゃん~」
「今まで作っていたのと、あまり変わらないね」
いえ、大きな変化が隠されているのです。
インボイス制度では、こう定められています。
国税庁の登録を受けた者から、
交付を受けた適格請求書等の保存を、
仕入税額控除の要件とする。
ちょっと専門的でピンときませんよね。
そう、実はここに盲点があります。
免税事業者が淘汰されるかも
まず、消費税の計算を理解する必要があります。
消費税を負担するのは、消費者ですが、
国に納税するのは事業者です。
納める消費税の計算はというと、
売り上げたときにもらった消費税(預り消費税)と、
経費として支払った分の消費税(支払い消費税)との差額を計算して納めます。
つまり、1000を売り上げると、その8%の80をもらいます。
経費で600使うと、その8%の48を支払います。
納める税金は差額の
80-48=32
となります。
この経費で支払った消費税のことを、
仕入税額控除
といいます。
経費として引ける分、そう考えてください。
消費税には特例があって、商いの小さい事業主には税金の納付をしなくていいとされています。
これが免税事業者です。
基準年度の売上が1000万円を下回れば、税金を納めなくていいというもの。
とはいえ免税事業者でも消費税はオンして商売することになっていますからね。
(たとえ消費税をオンしていないつもりでも、計算上は税込とみられます)
益税は出てしまいますが、税の基本思想である「弱者保護」にもなると思うので、私は良いのかなと思います。
しかし、インボイス制度では、免税事業者は適格請求書発行業者と認められないため、
免税事業者から仕入れたものや支払ったサービスの消費税は、
仕入税額控除として認めない
としたのです。
つまり、上の計算の例でいえば、支払った先が免税事業者だとすると
計算上マイナスできる消費税はゼロとなり、納税額は32ではなく、80となってしまうのです。
そうなれば、課税事業者から(お金を支払う側)見れば、
相手は大きなところと取引しよう
もしくは
相手に課税事業者になってもらう
と考えるかもしれません。
免税事業者からすれば、取引してもらいたいがため、わざわざ課税事業者になる、なんてこともあり得ます。
これは「弱者保護」に反する、とも言えるのではないでしょうか。
一応、経過措置が定められていて、
完全なインボイス方式への移行は4年後の平成35年10月からとされています。
仕入税額控除については、平成35年9月までは、現行と同じ100%の控除、
平成35年から3年間は80%、平成38年から3年間は50%と段階的に引き下がっていきます。
税率が上がることにばかり目が行きがちですが、
制度が変わる時には、こうしたところにも配慮が必要だと思います。
こうした税金の集め方が公平なのかどうか
厳しくチェックしていきたいものです。
制度も複雑で、まだまだいろいろと実務上の取り扱いが明らかになると思います。
不安な方は信頼のおける税理士さんに聞いてみてくださいね。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!