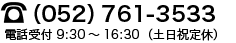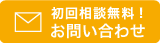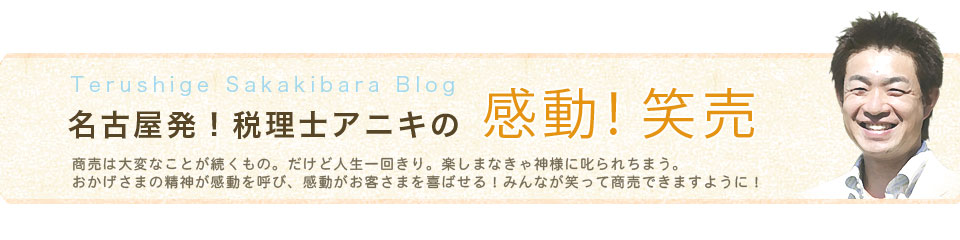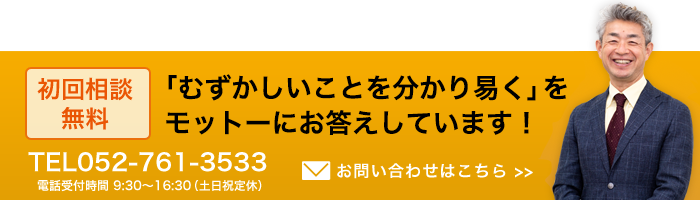2018年10月3日
ゴルフの経費、法人と個人での取り扱いが違う!?
暑かった今年の夏も終わり、さわやかな秋晴れ、スポーツの秋がやってきました。
社長や事業主様はゴルフの季節だ!と意気込んでいる方もいらっしゃるかと思います。
ゴルフの費用は経費になるの?
ゴルフをするといろいろ支出がありますが、どんなものがあるのでしょう。
ゴルフ会員権、名義書換料、年会費、ロッカー代、プレー代、そして道具類。
どれが経費になるのか気になりますね。
前提として、法人のケースでお話いたします。
まずは高額なゴルフ会員権です。
ゴルフ会員権は原則的には、資産計上となり、経費にはなりません。
節税にならず、単にキャッシュアウトするだけなので、税理士として購入はお勧めしません。
最近はネットなどで、気軽にプレーできるところが多いので、ひと昔前のように会員権は必要ありません。
注意したいのが会員権の種類です。
それが個人会員権で無記名式法人会員権が無い場合だと、その個人に権利がくっつくことになり、
法人が支払ったお金は給与扱いとなり、所得税がかかります。
給与となるので、経費と言えば経費ですが、たいていは社長や役員さんの名義で購入すると思われます。
すると役員賞与とみなされ、法人の経費として認められない場合もあります。
次に名義変更料ですが、他人から買った場合は取得に要した費用となり、ゴルフ会員権と一体となって資産計上となります。
ただし個人会員権を別の名義に代えるようなケースでは、交際費として取り扱います。
年会費とロッカー代は、その会員権の取り扱いに準じて決まってきます。
会員権が資産計上されている場合なら交際費、
会員権が給与とされている場合なら給与、
となります。
そして、プレー代。
その目的に応じて取り扱いが異なりますが、会社の業務上必要であれば、交際費となります。
個人的な趣味でプレーしたときは給与となり、所得税が本人にかかります。
交際費であれば、誰とどんな目的でしたかを説明できるようにしておきましょう。
最後に、道具やウェアですが、給与扱いとなります。福利厚生費としても認められません。
個人事業主様はお気を付けください
税法では個人事業主様は所得税法、法人は法人税法の適用を受けます。
実は、ゴルフ会員権と年会費については、両者で取り扱いが異なるので注意が必要です。
所得税法上では、ゴルフ会員権は、
事業用資産に該当しない
こととなっています。
つまり、買っても資産計上すらできません。
ということは、その年会費は法人のように交際費にならない、ということなんです。
つまり、
個人事業主様だと、プレーしたときの費用だけが経費となるのです。
法人と同様に考えていると、経費にならず、うっかり税金がかかる、なんてことも。
楽しくプレーするためにも、
事前に税理士に聞いておけば安心ですね。
くれぐれも遊びでいくプレー代や道具、ウェアは社長自身で出すこと!
公私混同は厳禁ですぞ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年9月20日
お酒と税金について考えてみます
ワインの表示方法がこの10月30日から変わります。
左党である私にとっては大歓迎です。
小さいワイナリーが頑張るようになる
いままでの日本産ワインは市場では玉石混合でした。
評価が高いものもあれば、粗悪な商品もありました。
フランスのように表示を厳格化することで、品質が良くなっていくことが期待されます。
いままでの法律では、外国産のブドウでも、国内の醸造所で製造すれば「国産ワイン」となりました。
今回の改正で、これらは「国産ワイン」という表示はできなくなります。
「国産」と「国内製造」では印象は違いますね。
輸入ブドウは、主に大手メーカーが作るワインに使われています。
輸入ブドウを使うことが少ない地方の中小ワイナリーには、大いにチャンスとなるわけです。
こだわって作られる美味しいワインがたくさん出回り、選べる楽しさもが増していきますね。
嗜好品には高い税金をかける
一方で、ワインは平成32年から段階的に増税されることが決まっています。
美味しいワインが増えるのは喜ばしいけれど、値段がさらに高くなるのはうれしくありません。
ワインの消費が増えるので、税金をしっかりと集めよう、そんな思惑が透けてみるようです。
日本の酒税法では、原材料の比率や作り方などで税金が決まってきます。
だからビールはメーカーが製法を研究し、発泡酒や第3のビールを生み出しました。
味も当初はビールと大きく異なりましたが、最近はとても美味しくなりました。
メーカーさんの努力には頭が下がります。
安くて美味しい、左党にとってはうれしいことです。
しかし、これら発泡酒も第3のビールも、平成32年からビールと同じ税率が課されることになり、
値上げが確実です。
お酒やたばこなど、嗜好品には高い税金をかける、それがわが国の政府の考えなんですね。
ワインの例を採れば、フランスは品質を上げるために法律を作り、
日本は税金をたくさん徴収するために法律を作る。
あ~~~
美味しいお酒を安く飲めるといいのになぁ。
嘆くばかりです(苦笑)。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年9月4日
取引先が倒産!資金繰りが悪化!そんな時のために
現在の日本の景気は、おおむね好調に推移していると言われています。
(中小零細には厳しい感じがあるのですが・・・)
そんなときこそ、万が一に備えをしておく、これも経営者の務めです。
もし、取引先が倒産していまい、資金繰りが苦しくなったら・・・。
銀行に駆け込んで相談?
備えておくのは、生命保険?
いえ、別の方法もあります。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構か行っている、 中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度です。
中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。
昭和40年代後半オイルショックがあり、大きな景気後退が起こりました。
中小企業では、日本中で倒産件数が増加する中、突然の取引先企業の倒産で被害を受ける連鎖倒産が引き起こされました。
そこで中小企業の相互救済のための仕組みとして作られたのです。
この制度はおよそ50年を経た今でも中小企業の味方です。
掛け金総額の10倍のお金を借りることができる
この制度を使うと、
掛け金総額の10倍の貸付けが即時受けられます!
例えば今までで200万円の掛け金がなされていれば、その10倍である2,000万円が貸付金額となります。
(ただし不良債権の金額が上限ですが)
助かりますよね~
また、倒産していなくても、緊急の物入りの時は一時的に貸してくれる制度もあるのです。
それなら、預貯金と変わらんじゃないか、
いえ、大きな違いがあります。
掛け金は全額損金となる
預貯金なら銀行に預けても、単に資金の移動です。
しかし、この制度では
掛け金はすべて損金(費用)
となります。
その分利益が圧縮されるので、納める税金が少なくなり節税となります。
しかし、物入りの時にはお金に換えられる(利息はかかりますが)のは、通常の銀行借り入れより手続きもラクで助かります。
さらに、この制度の特徴として、40ヶ月継続すると、
任意解約しても解約返戻金が100%が保証
されているのです。
解約返戻金が100%は民間の生命保険会社の商品ではあり得ません。
お金を掛け金に回せるようなときは、利益が出ているときでしょう。
掛け金が損金になれば節税になるので助かりますね。
逆に、お金を引き出したいときは赤字の時でしょう。
解約返戻金は雑収入として益金処理しますが、その時の赤字と相殺すれば、これまた税金は助かります。
タイミングは注意する必要がありますが、
節税しながら、万が一に備えられる。
制度を知らなかった、加入していなかった個人事業主様や経営者の皆さま、
ぜひご一考ください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年6月22日
保険を法人契約する際のポイント
前回まで、法人と個人事業の選択のお話をしてまいりました。
その中で法人のメリットとしてご案内したものの一つに、生命保険があります。
生命保険の種類は様々
一口に生命保険といっても、日本の会社の保険から外資の保険まで様々です。
保険ですから、何か不測の事態が起きたときのために、お金が下りるようになっています。
社長が病気になったら・・・
社長が障がい者になってしまったら・・・
社長が要介護状態になってしまったら・・・
そして
社長が亡くなってしまったら・・・
私たち税理士が関わるお客様は、上場会社と違い、
オーナー経営者の方々ばかりです。
社長に何かあったら、経営はすぐに影響を受け、
たちまちお金が大変なことになってしまうケースもしばしば。
そのためにも保険は大切なのですね。
税務上の取り扱いは
そんな不測の事態に備えて、保険に入ります。
では、税務上支払った保険料は損金(経費)になるのでしょうか
まず税務上、保険は、その内容によって3つに大別します。
① 養老保険
満期、または被保険者の死亡によって保険金が支払われます。
② 定期付養老保険
①の養老保険がメインですが、定期保険も特約でついています。
③ 定期保険
一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われます。生きている間にもらう生存保険はありません。
そして受取人をだれにするかで取り扱いが決まっています。
養老保険の場合、
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期付養老保険の場合、
定期保険の保険料の保険については
① 法人
② 被保険者の遺族
養老保険の保険料については
① 法人
② 被保険者またはその遺族
③ 死亡保険金が遺族で、生存保険金が法人
定期保険の場合、
① 法人
② 被保険者の遺族
国税庁のHPに詳しく書いてありますから、ご確認いただけます。
損金になる場合と資産として取り扱う場合に分かれます。
また損金といっても、「お給料」扱いになって源泉税を納めなくてはならないケースもあります。
気を付けるポイントはひとつ
さて、区分してケースに分けると分からなくなってきますね(苦笑)
ややこしい。
でもポイントはひとつです。
それは
保険金は誰がもらうのか
です。
税務の考え方として、支払うのは法人ですから、
法人がもらうことになっていれば、支払保険料は損金、受取保険金は益金になります。
個人がもらうことになっていれば、それは受けるメリットが個人に移動するので、個人に課税がなされることになります。
よく節税対策目的で、決算間際に相談を受けます。
しかし保険はあくまで保険。
損金になれば、それは節税といえますが、キャッシュが外に出ていくことになります。
保険の性格と目的をしっかりおさえて、有効に活用してくださいね。
保険マンには「節税になるよ、損金になるよ」と言われても、
うっかりがないよう、かならず確認をなさってください。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年6月4日
法人と個人事業の選択~その4~
前回まで3回にわたって法人のメリットについてお話ししてきました。
今回は法人化のデメリットと個人事業のいいところをお話しします。
法人化のデメリットは、裏を返せば個人事業のメリットでもあります。
法人登記でお金がかかる
まず法人化するのにお金がかかります。
今から14年前、2006年の会社法改正で最低資本金制度が撤廃されました。
昔は株式会社を作るには資本金が1,000万円、有限会社で300万円が必要でした。
起業するのにこれだけのお金を用立てするとなれば大変ですよね。
それが改正で1円からでも起業できるようになったのです。
確かに資本金を用意しなくてもよくなりましたが、会社登記にはやはり30~40万円かかります。
しかし個人事業でしたら、思い立ったが吉日、その日からお商売が始められます。
自由に使えるお金は
プライベートに使えるお金の自由度は個人事業の方に分があります。
利益となったお金は、極端な話、税金と借金さえ返せば自由に使うことができます。
法人でも、普段から個人で計画的に預貯金などしてあれば良いのですが、
子どもが私立大学に入学した等、急なもの入りの時に、法人からお金を引き出すことは難しいです。
公私混同はNGなんですね。
役員報酬は原則前もって定額で決めていますので、そのようなときには余分にお給料ください、とはなりません。
会計や税務が複雑
やはり申告書ひとつにとっても法人税の方が難解です。
租税特別措置も多岐にわたっています。
個人の確定申告なら税理士に頼まずとも、なんとかできるかもしれませんが、
法人となれば専門家に頼まないと難しいです。
そうなれば費用もかかってきますね。
税務調査でも違いが
税務調査では、経験則上、法人の方が厳しいと思います。
法人税は個人の所得税より難解でもあり、
税務処理が難解ということは、その運用でも意見の相違が出やすいと言えます。
また個人事業の場合は、課税は最終的に相続税で補完することができると考えられます。
したがって税務調査の強弱でいえば差が出るかもしれません。
青色申告控除が個人事業にはある
個人事業主特有の制度と言えば、青色申告控除があります。
青色申告をすれば利益のうち65万円を非課税にしてくれます。
個人の方が頑張ってお帳面を付けたご褒美のようなものでしょうか。
この金額をもって税理士費用にと考えている人もいますね。
自分限りの事業なら
会社を大きくして子どもに継がせるなら会社にするのもありですが、
自分の代だけで終わるお商売なら法人にする意味合いも薄れます。
法人は赤字でも支払わなければいけない均等割という税金や、
運営に関して税理士や社会保険労務士等に支払う費用も多くなります。
社会保険料の負担が大きい
社会保険料は従業員と会社の折半で支払います。
役員報酬なら、将来の自分の年金に反映しますが、従業員の分は持ち出し。
額面より10%多く人件費を支払う心づもりでいてください。
とはいえ社会保険完備は採用には有利ですから、その点はメリットにもなるかと思います。
4回にわたって個人事業と法人の選択についてご紹介してきました。
法人であれ、個人の事業主様であれ、黒字を出して税金は納めてほしいとは思います。
でも、税金を払いすぎるのももったいない。
節税だけでなく、
事業の将来や、目指すところも考えて法人化を検討してみてくださいね。
もし法人化を考えているのなら、信頼のおける税理士さんにぜひ相談してくださいね。
節税以外でも大局的にアドバイスしてくれる人なら、良きパートナーとなってくれると思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年5月15日
法人と個人事業の選択~その3~
前回は法人化するメリットをお話ししました。
今回もまだまだある法人化のメリットをご紹介してまいります。
繰越欠損金が9年もある
青色申告が要件ではありますが(とはいえおそらくほとんどの法人様は青色でしょう)、
繰越欠損金の繰越期間が9年間あります。
繰越欠損というのは赤字を翌年に繰り越して、翌期の黒字と相殺ができるというもの。
もし多額の欠損金が出たら、翌年以降の利益額にもよりますが、数年間は納税不要となる場合もあります。
個人事業主であれば繰越欠損の期間は3年間。
法人はその3倍となるわけです。
消費税が免税となる
こちらもご存知の方も多いですね。
消費税は売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。
その支払う年度はというと、2年前の売上額が1,000万円を超えていた年。
「今年1,000万円を初めて超えちゃったよ~。今年の申告で消費税を払わないかん?」
いえ、消費税を支払う年は再来年です。
消費税は2年前を基準年度として判定することになっているのですね。
つまり法人成りしたら(個人事業を法人化すること)、基準年度が最初の2年間はないため免税事業者となり、
消費税を支払わなくてよいとなります。
ただし、資本金が1,000万円以上だったり、
大会社の子会社や、最初から利益が出て年1,000万円以上の給料を出したりしているとこの限りではありません。
税理士さんに必ず相談してくださいね。
将来事業を承継しやすい形を作れる
会社は株式という単位をもって売ったり譲ったりできます。
もし将来、子どもに商売を譲ろうと考えるのなら株式会社は便利です。
子どもに譲ろうと思ったときは、当然子どもからももらってうれしい成長会社であるはずです。
(赤字会社だと困ります)
だけど全部もらうとなると贈与となり、多額の税金がかかってしまいます。
しかし法人化しておけば、株式の単位に小分けすることができるので、
課税を抑えながら計画的に贈与することが可能になります。
事業年度を自由に決められる
個人事業であれば税金計算する時期は決められています。
1月~12月の暦年を基準として、決算をして翌年の3月15日までに確定申告をします。
しかし法人であれば決算月は自由に決められますし、途中で変更することもできます。
忙しい時期や、お金がいる時期に申告や納税が重なると大変です。
比較的時間やお金に余裕がある時期を決算月とすることをお勧めします。
さて、いかがでしたでしょうか。
法人にするメリットはいっぱいありますね。
でもちょっと待ってください。あわてないで。
次回はデメリットにも触れて考えていきたいと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年5月1日
法人と個人事業の選択~その2~
さて、前回は所得税と法人税の税率の違いに着目してみました。
今回は法人化するとメリットがいろいろありますよ、というお話をしたいと思います。
代表取締役の給与では給与所得控除が受けられる
前回もお話ししましたが、給与としてもらうことに変更するだけで、節税ができます。
事業所得(利益)だと、その金額全部に税率をかけて計算するのですが、
給与であれば給与所得控除といって、給与のおよそ20~35%くらいが経費とみなされ非課税となります。
つまり給与所得控除分が節税となるわけです。
奥様や家族に対する給与が役員報酬として決められる
個人事業であれば、青色専従者給与として届け出た金額しか経費になりません。
専従者ですから「もっぱら事業に従事している」事実が必要となります。
しかし法人であれば、役員報酬は非常勤であっても支給が可能となります。
またその金額が適正であれば、自由に決めることができるのです。
代表者への退職金が受け取れる
会社の役員を退くときには退職金を出すことも可能になります。
退職金は、退職後の生活資金の性格があるため、税法では非課税の枠が大きいため節税になります。
一方、個人事業主だと経費として認められません。
小規模共済へ加入してその掛け金が所得控除として認められるだけで、
退職金の金額も掛け金に応じた金額となります。
将来受け取る年金額が増える
個人事業ですと国民年金が基本的な年金となります。
残念ながら支給される年額は90万円ほど。物価スライドとはいえ十分ではありません。
(もちろん個人年金基金や、確定拠出年金、生命保険会社の個人年金へ別途加入することはできます)。
法人であれば給与額に応じて保険料が決まっており、会社側が半分を負担するため、
個人で負担する掛け金が同じとするなら、将来もらえる年金額はぐっと多くなります。
生命保険の使える幅がぐっと広がる
個人の場合、生命保険にはいっても税金の恩恵は小さいです。
生命保険控除といって最高でも12万円までしか所得控除がありません。
多額の掛け金を支払っても、所得税率が20%の人なら、12×20%=2.4万円しか税金は助からないのです。
法人であれば違ってきます。
目的に応じていくつも入れます。
退職金の原資として使えば、法人でも課税を抑えながら、個人へ資金を移動することも可能になってきます。
(このあたりの仕組みは税理士さんに聞いてくださいね)
保険商品によっては、積みたてるものもあれば、全額経費となるものがあります。
法人税を抑えながら、将来の不測の事態に備えることができるのです。
私たち税理士が応援する会社は、同族会社とされる家族経営の会社が多いです。
個人で頑張って稼いだ財産を様々な方法で節税したい、
そう考えると上記のように法人化するメリットも多いと思います。
次回はまだまだ使える、こんな法人化のメリットをお話ししたいと思います。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年4月20日
法人と個人事業の選択~その1~
個人事業をしている方から、よくいただく質問として
法人化をするとしたら、いつがいいですか
があります。
法人の税率は
この質問の背景にあるのが、所得税と法人税の税率の違いがあります。
税率は毎年の税制改正でよく変わるので、注意が必要ですが
この記事を書いている30年4月現在の税率を見てみます。
法人税の税率は一定で、23.2%です。
しかし中小企業には税金をまけてくれます。
ここにも「弱者保護」の思想が現れていますね。
中小企業の場合、
所得(もうけ)が800万円までは19%です。
しかも時限立法で向こう2年はさらにおまけしてくれてまして15%となっています。
いや~助かります!
とはいえ、支払う税金は法人税だけでなく、住民税である県税や市税、加えて事業税もあります。
それらを足すとどれくらいになるのでしょうか。
これを実効税率といいます。
新聞などでは大企業の実効税率が報道されます。
今ですとおよそ35%くらいですね。
諸外国に比べて…というときは大概この数字をさします。
それに対して、私たち税理士が関わる中小企業の実効税率は25%くらいです。
1,200万円利益が出たら300万円を納める、そう理解しておいて下さいね。
個人事業の税率は
では個人事業の税率はどうなっているのでしょう。
所得税では、累進課税といって所得(もうけ)が増えていくと税率が高くなります。
つまり所得が低い人は税金は安くするという仕組みです。
これも「弱者保護」の思想が効いていますね。
では税率はというと
所得が195万円まで 5%
所得が195万円から330万円まで 10%
所得が330万円から695万円まで 20%
所得が695万円から900万円まで 23%
所得が900万円から1,800円まで 30%
所得が1,800万円から4,000万円まで 40%
所得が4,000万円~ 45%
ここで知っておいていただきたいことがふたつあります。
ひとつは、税金がかかるのは「所得」であって「収入」ではありません。
そして、税率はそれぞれの段階でかけて計算するということです。
例えば個人事業での利益が1,200万円の人だとどうなるのでしょう。
ざっくりと考え方だけを説明したいので所得控除などは考慮しません。
「収入」は売上、「所得」は利益、そう考えてください。
利益は1,200万円であれば、これを所得と読み直します。
おお、所得は1,200万だから税率は30%で、
税金は1,200万円×30%=360万円。
おっと、これは早合点です。
税率はそれぞれの段階での税率をかけて計算しますので、所得税はもっと少なくなり、242万円となります。
個人の場合、住民税は一律10%ですので、1,200万円×10%=120万円
あわせて、およそ362万円となるわけです。
では、どれくらい儲けが出ると法人がおトクなの?
法人税で納めるか、所得税で納めるか
どちらがおトクかという視点で見てみましょう。
上記でみたように、
個人事業での利益が1,200万円なら362万円。
これを法人の利益とするなら300万円です。
なんだか法人の方が少なそうな気がしますね。
法人となれば、会社から事業主様は「給与」としてお金をもらうことになります。
すると利益1,200万円をすべてお給料としてもらうとすれば、
給与所得には給与所得控除といって、給与の経費相当分として220万円が非課税となりますから、
(ここが節税のポイント)
1,200-220=980万円が給与所得となります。
所得税は170万円、住民税を加えても270万円となるわけです。
法人にした方がぐっと支払う税金が少なくなりそうです。
実際は、各種の所得控除も考慮して計算するので、正しい税金額は変わります。
少し荒っぽい言い方になりますが、事業の利益が800~900万円を超えて続くようなら、
法人化したほうが納める税金は少なくなりそうです。
税理士さんに一度シミュレーションをお願いするといいでしょう。
しかし!
法人化は納める税額のみで決め手にはなりませぬぞ。
他にもメリット、デメリットがありますから、
法人を作って将来どうしたらいいか、何をしたいのかをしっかり考えてくださいね。
そのあたりは次回へ。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
2018年3月23日
医療費控除の申告現場から思うこと
確定申告が終わりました。
お客様にも、
スタッフであるシャインズの皆さんにも
助けられ、無事過ごすことができました。
感謝です。
ありがとうございます!!
税理士会主催の無料相談
確定申告時期には、
税理士会の会務で「無料相談」が区役所で行われます。
これは正しい納税を推進すると同時に、税理士会の公益性から地域の方へのボランティアという意味もあります。
ですからお越しになる方の多くはお年寄りで、
年金を受け取っているような方がほとんどなんですね。
医療費控除の変更
さて、今回の申告から変更になった点で「医療費控除」があります。
医療費控除はたくさん医療費がかかった方は大変なので、税金をおまけしてあげるという趣旨のものです。
だから「私はこんなにも医療費がかかりました~」と申告すれば税金がまかります。
医療費控除の意外と知らないシリーズ。
- 自由診療でも医療費控除が受けられる
- 家族分をまとめて計算できる
- 未払いは計算対象にならない
- 保険などで補助が受けられる、受けられそうなものは金額から差し引く
- 歯列矯正など高額でも受けられる
全部がイエスです。
それで今回の変更は何かというと
薬局でのお薬を購入が対象になるセルフメディケーション税制と
申告に使う用紙が変わって領収書を提出しなくてもよい
ことになったのです。
領収書を提出しなくてもよい、これは申告する方にとっても税務署にとってもメリットはあると思います。
確かに税務署の方も大量の領収書をチェックするのも、保管する場所も大変だわ!と思います。
ただ領収書を添付しなくてもいいのは、今回から新しくなった用紙を使って申告した場合のみ。そして、
その用紙を使わないと医療費控除が受けられない!!
ということなのです。
問題なのは、申告に来たお年寄りたちのほとんどが、それを知らなかった!!ということです。
そりゃ確かに様式に沿って書かないといかんと思うけどさ…。
税金の思想は弱者保護ですぞ
さすがに国税庁も鬼ではありません(苦笑)。
向こう3年間は今まで通り、領収書を提出すれば医療費控除は受けられるそうです。
言い換えれば3年後からはきちんと様式通り書かないと、
たとえ領収書を出したからといって医療費控除は受けさせませんぞ、
となったのです。
いや、弱者保護の思想からすると、ちょっと優しくない!
そりゃあ、納税は国民の義務であるけれど。
「お上」のやり方っぽくないですか?
『もうちょっと税金を納めている国民の皆さんに寄り添ってほしいな~』
とお年寄りの申告を手伝っているときに思いました。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!
2018年2月15日
保険金の受取りは思わぬ課税があるので要注意
さて、確定申告が始まりました。
税理士事務所も本格的な繁忙期が始まります。
保険金の課税関係は大丈夫?
保険金を受け取ると税金がかかります。
この時期、確定申告で取り扱うのは「贈与税」と「所得税」になります。
皆さんが入っている保険はどの税金がかかるのかご存知でしょうか?
うっかり税金がかかってきた、なんてことがないようにしたいですね。
税金を判断するために知っておくこと
保険金の課税を整理していきましょう。
まずは「契約者」「被保険者」「受取人」この3つを理解してくださいね。
契約者…生命保険会社と保険の契約を結び保険料を負担する人
被保険者…その人の生死・ケガ・病気などが保険の対象となっている人
受取人…保険金を受け取る人
そして保険にまつわる税金は3つです。
そして税金が安い(負担が少ない)順に
相続税<所得税<贈与税
となります。
ちなみに、所得税では契約内容によっては雑所得として計算する場合(年金保険)と、
一時所得として計算する場合(満期保険金)があります。
かかってくる税金を判断するポイントは
契約者と被保険者が同一か
契約者と受取人は同一か
となります。
あなたが入っている保険はどのタイプ?
具体的に見ていきましょう。
契約者と被保険者が同じケースとしては、父が死亡保険に入って保険料を支払っておき、自分が死んだら家族に保険金がおりる、ものです。これは相続税がかかります。
また契約者と被保険者が同じケースでも、保険料を定期で支払い、満期の時期が来たら保険金がおりる、ものがあります。
これは贈与税か所得税がかかります。
この場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の一時所得で計算します。
一方、契約者と受取人が別人であれば、受け取った人に贈与税がかかるのです。
贈与税は税率が高いので、受取人を決めるときは要注意ですよ。
あれ?自分が契約したけど、受取人は子どもにしてしまったぞ!
なんてこともあるかもしれません。
ただ、契約途中で受取人を自分に変更しておくことも可能ですので、
もし受取人を妻や息子にしている、なんて方は検討してみてくださいね。
最も辛いうっかり
それから最も注意してほしいのは、満期保険金で契約者と保険料の支払い者が違っていた場合です。
例えば、妻を契約者としたけれど、保険料は夫である自分の銀行口座から引き落とされている、なんてケースです。
もちろん夫婦ですから生計同一ですし、お金が家計から出ていくには違いないので、
契約時はうっかり見過ごしてしまいがちなのです。
税務ではお金を負担している人で判断するので、契約者が妻だとしても、
受け取った満期保険金には、夫から妻への贈与として、しっかり贈与税がかけられてしまいます。
満期保険金が500万円で、支払った保険料が400万円だとします。
一時所得であれば、課税される所得は25万円となり、税率が10%であれば25,000円が支払うべき税金となります。
これが贈与税になると、53万円(特例贈与なら48.5万円)が支払うべき税金となります。
この差にはびっくりしますね!
保険の営業マンから契約時には、税金についても説明があるので大丈夫と思いますが、
心配でしたら一度ご自身が入っている保険について、税理士さんに相談してみてもいいかもしれません。
メルマガ
【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。
お楽しみに!