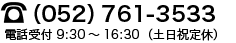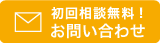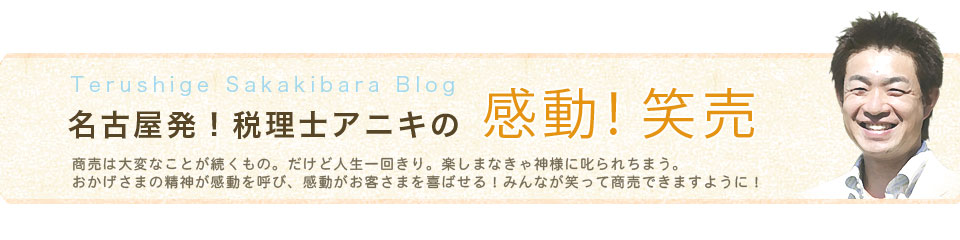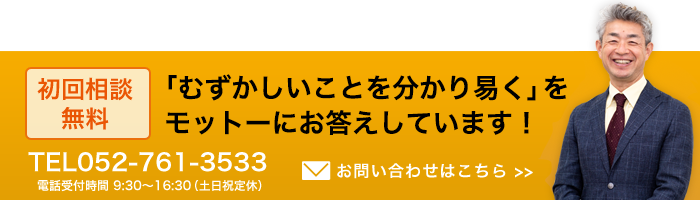2015年11月2日
個人事業主様の経費・税金編
風が肌寒く感じる季節になってきました。
個人で事業をしている方は、あっという間に年末、決算を迎えることになります。
ここからが早いんですよねぇ。準備はしっかりやっていきましょう。
さて、個人の方が事業していて
経費となる税金について、おさらいをしてみたいと思います。
法人とは違うケースがあるので要注意です。
経費になるものを見ていきましょう。
まずは消費税です。
消費税は売上が1,000万円を超えてこないと納める必要がありません。
正確にいうと2年前の年が1,000万円を超えていたら、今年は支払わなければなりません。
ただ消費税の支払時期は、決算が終わって翌年確定申告時に納めます。
じゃあ、いつの経費になるの?
実は決算年度の経費にしてもよいし
支払った年の経費にしてもよいのですね。
個人事業の場合、所得税は累進課税ですから、
税率が高くなる年の経費にした方が節税効果が得られることとなります。
次に事業税。
年間の事業所得が290万円を超えてくると、
翌年の夏ごろ、市役所や区役所から納付書が送られてきます。
突然送られてくるのでびっくりしますが
お商売が順調にいている証拠です!
こちらは通常、支払ったときの経費となります。
良く似ているものに事業所税があります。
こちらは事務所や店舗、倉庫などがある程度の規模がある場合、
納めることになっています。
分かりやすくたとえるならば「場所代」ですか。
こちらも経費となります。
契約書や領収書に張る印紙税。
こちらも経費になります。
印紙はうっかり貼り忘れてしまうことも多いので、
税務調査の時には結構指摘を受ける項目です。
税務調査において印紙を貼付していないことが発覚した場合、
必要な印紙税の額だけでなく、その2倍の過怠税が徴収されることになります。
まとめて支払うとなると相当な額となってしまいます。
建設業など請負金額が大きな業種に方はお気を付け下さい!!
そして、自動車関連税。
自動車税や車検の時に納める重量税などです。
事業で使っている車両なら、もちろん経費となります。
最後に固定資産税。
例えば、ご自宅の一部をお店にしているときなど
「お店の分は経費になりますか?」時々質問を受けますが
答えはYES!!
ただし事業に使っていると認められる部分だけになるので、一部が経費になるというわけです。
残念ながら自宅の部分は経費になりません。
もちろんアパート経営など不動産所得の時は全額経費になりますよ!
一方、経費にならない税金です。
住民税の均等割。
「場所代」のようなニュアンスで事業所税と似ていますが、
こちらは経費となりません。
個人の事業主様は住んでいる場所で申告をするのですが
別の区や市町にお店や事務所があったりします。
そういうときは均等割を納めることになるのですが、経費にならないんですね。
事業で使っている場所なんですが、ダメなんです。
ちょっと納得がいかないですねぇ。
次に。
交通違反をした時に支払うような罰金。
「えっ?」と思われるでしょうが、結構聞かれるんですよ。
「営業車でちょっと荷物を下ろしに行っていたら、
駐車禁止で罰金を支払わないといけなくなった!
これって経費になりますよね?」
なんて。
残念ですが、罰はその人個人の行為に対してなされるため、経費にならないんですね。
さて、いかがだったでしょうか。
きちんと理解して、経費に落ちる落ちるだけでなく
印紙税のように知らなかったではすませられない火傷もあります。
これ以外でも「おやっ?」
そう感じたり、迷ったら、
専門家である税理士にお尋ねしてくださいね!
ブログ【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!
2015年9月3日
戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度 その2
旧暦では210日を過ぎると、「処暑・天地 はじめて 寒し」といい
秋雨前線が出て冷たい空気が流れてきます。
まさに、全国ニュースでは関東地方が肌寒いと報道されていますね。
日本のテレビはシャープさん♪
日本の税制はシャウプさん♪
ダジャレも,
寒いですね(汗)
さて、今回は前回の続きです。
昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。
すごい人なんですよ!
何がすごいかって。
それは
源泉徴収と確定申告制度。
源泉徴収とは、所得の発生する場所で、あらかじめ天引きしておいて、税金を納める制度です。
例えば、サラリーマンなら所得の発生する場所はどこでしょう?
答えは会社ですね。
その会社が、給与を支払う時に、全額を本人に渡さず、
あらかじめ税金を天引きして、本人に代わって税金を納める制度です。
実はこの制度、シャウプさんが来る前に誕生していました。
昭和15年に戦争のお金のため、税金を確実に徴収するために創設されたのです
そして戦後もそのまま残されました。
さて、ポイントは
サラリーマン本人ではなく、会社に税金を納めさせる義務を負わせたところなんです。
お金って,
あったらあっただけ使ってしまいますよね、それが人間です。
だから使う前に確保。
納税の義務者は会社ですが、本人ではありませんから困るわけではないですね。
徴収忘れすると、なんと会社がいったん税務署に支払わなきゃいけないんです。
え~~。
本人からは会社がもらってください、と。
会社としてはそれはいやなので、しっかり天引きをするというわけです。
国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減るわけですね。
よく出来てますよね!
それから確定申告制度。
確定申告とは、期間を決めて(今は一年です、昔は大変だったんで半年)、
働く本人が自分の儲け(利益のこと)を自分で計算し、(←これを決算という)
自分で税金を確定し、申告をするのです。
確定申告をいうと3月の時期を思い浮かべますが、それは個人の申告期限です。
法人も自分たちで決めた決算期に確定申告しているんですよ。
自主申告が進むようにと、青色申告を導入したことが、インセンティブとなりました。
ここでも!
国からすれば、自分たちが動かず、取りぱぐれがぐっと減る仕組みを作ったわけです。
さて、ポイントは
自主申告というところ。計算間違いがあったとき対応が分かれます。
たとえ払い過ぎたとしても、自分たちで確定したわけですので、税務署は何とも言ってきません。
そのままです。
しかし足りないと思われる時は、税務署は「ちょっと計算間違いしてないですか~」と税務調査にやってくるのです。
ホント、よくできた制度ですよね~!!
でも税理士の仕事があるのも、この制度のおかげではありますが・・・。
しかし、この制度は大きく変わるかもしれません。
マイナンバー制度がが平成28年から導入され
随時その範囲が広がっていきます。
え?それが関係あるの?
大ありです。
もしかしたら。
税理士の仕事も無くなるかもしれません。
その話は、また別の機会に!
ブログ【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売】
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年8月21日
戦後の税制はシャウプさん 源泉徴収と確定申告制度その1
お盆も過ぎました。
あいかわらず暑いですが、夕方の日差しや風に夏もひと段落を感じさせます。
今年の8月15日は戦後70年という節目だけに、いつもの年より世の中は「戦後」を意識していたように思います。
日本のテレビはシャープさん♪
日本の税制はシャウプさん♪
昭和24年にシャウプさんは来日され、日本の税制の枠組みを作っていきました。
すごい人なんですよ!
日本の税制については、国税庁のホームページ内に「租税史料ライブラリー」があり、
読んでみるととても面白いので、興味ある方はぜひのぞいてみてくださいね。
例えば「戦後税制のスタート」のページを見ると以下のように書いてあります。
昭和21年、戦後処理のために戦時補償特別税と財産税が創設されました。
戦時補償特別税は、戦後の財政再建を図るため、
戦時補償請求権に100%課税することで
戦時補償の支払いを打ち切るための措置でした。
また財産税は、10万円以上の財産を所有する個人に課税されました。
え~~~、すごすぎる!!
戦争で発行した国債は100%税金がかかる、
つまり紙切れにしちゃう・・・ということです。
しかも加えて財産を持っているだけで課税とは!
いやもう、滅茶苦茶です。
国民の財産の保全は、どうなっちゃったの?
そして次のように説明が続きます。
戦後の本格的な税制改正は昭和22年に実施され、
所得税・法人税などに申告納税制度が導入されました。
しかし深刻な財政危機のもと、
納税者数の激増、
新制度への不慣れや職員の大量補充、
各地の軍政部の徴税への関与など、
終戦直後の税務行政には多くの混乱が生じました。
そりゃそうだわ~
でも戦後のどさくさに思いをはせれば、まあ大変だったなと思い知ります。
そんな中シャウプさんがやってきたわけです。
混乱をおさめ、税制の基礎を作っていくのです。
すごいなぁと思うこと、それは。
源泉徴収と確定申告制度。
長くなりそうなので
何がすごいかは、次回にお話ししますね。
税理士の仕事は節税だけではありません。
しっかりと税金の本質を理解して、正しい納税をしていただけるように説明するのも仕事なんですね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年8月3日
空き家になると、税金が増える?しっかり対策を始めておきましょう。
空き家問題。
実は税務の専門家の間ではタイムリーな話題です。
去る5月から「空家等対策推進特別措置法」が完全施行されました。
またまた漢字がん並んでいかにも難しそう・・・。
なんで法律の名前ってこうも感じが並ぶんだろう(苦笑)。
この法律、簡単に言うと
空き家を放っておくと税金たくさん納めていただきますよ
空き家を放っておくと行政が処分しちゃいますよ
というものなんです。
空き家は
その家に住んでいる方が亡くなったり
介護が必要になって施設に移られたり
そういう時に生じます。
日本では住宅数はおよそ6,060万戸となのですが、
およそ13.5%の820万戸が空き家となっています。
しかもその割合は年1%ずつ増えていくとか。
空き家になると困ることが多くなります。
家というのは住んでいないと朽ちていくわけで
ゴミを放置されたり
放火のリスクも高まります。
つまり、周りのご近所さんにとって迷惑になりうる可能性が高いのです。
これは、他人ごとではありません。
昭和の時代は、いつかは夢のマイホームと頑張って働いて家を買いました。
私の父親もそうでした。
ですが、子どもたちが住んでいたのはわずか十年ほど、
それぞれが所帯を持ち、
それぞれがマンションを購入して別の持ち家があります。
実家には年老いていく母親だけ・・・。
多くの世帯でそうなっているのではないでしょうか。
普段は意識することは少ないでしょうが、大きな問題を抱えているのですね。
いつ当事者になるのか分かりません。
さて、では空き家になると税金が増えるのでしょうか。
これまでは税務上では二つが指摘されていました。
①空き家にして3度目の年末を過ぎてから売却すると、3,000万円控除の特例が使えない
⇒ 譲渡所得税がかかる
②相続した時点で被相続人が住んでいないと小規模宅地の評価減が使えない
⇒ 相続税がかかる
これらに加えて、今回の法律で固定資産税と都市計画税の減免が無くなることになりました。
今までは空家でも「住宅用地」として取り扱われていたのですが、行政から特定空き地として勧告を受けると
固定資産税がおよそ6倍
都市計画税がおよそ3倍
になるのです。
その請求先は
相続していれば、実家をもらったあなた、
親の面倒を見ていれば、介護をしているあなたです。
まだまだ先のこと、
そう思わず今から対策をしておくことをお勧めします。
ちょうどお盆になれば実家に家族が集まる機会でしょう。
情報を税理士からゲットして、家族でお話ししておくといいかもしれませんね。
税理士が先を見据えた相談にのってもらえると思います。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年7月17日
住宅資金を贈与してもらうのは今年か来年か、どちらがお得?
両親から、祖父母から、
住宅を建てるときに資金を出してもらったら、普通なら贈与税がかかるのですが、
現在は贈与税がかからない特例が出されています。
しかし、そのタイミングが違うと非課税枠が大きく異なるので注意しましょうね!
特にいま、住宅資金を贈与しようか考えている方は要注意です。
というのも、
平成27年12月までの非課税枠は1,500万円
平成28年10月~平成29年9月の非課税枠は3,000万円!!
なんと少し待てば贈与税の非課税枠がおよそ倍!!
(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)
3,000万円贈与したら、税金にして470万円も節税になるのです。
でもおいしい話には落とし穴も。
3,000万円の非課税枠を使えるのは、消費税10%を支払った場合のみ
なのです。
消費税を支払っても、節税効果が高くなるのはおよそ2,000万円以上贈与するケースになってきます。
また、
ちょうど間にあたる平成28年1月~9月だと非課税枠は1,200万円に下がってしまいます
そして、
平成29年9月を過ぎちゃうと、非課税枠は元の1,500万円に戻っちゃいます。
贈与金額を考えて、適切な時期に住宅を建ててくださいね!
こうした特例は増税がなされるときの救済的な役割を果たします。
信頼のおける税理士さんから情報をあらかじめゲットして、賢い選択をしてくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年7月3日
マルサの女はやっぱり怖いですよね
テレビドラマの「税務調査官・窓際太郎の事件簿」シリーズは時々見ますが面白いですね。
税理士という職業柄、つい見てしまいます。
主人公の税務調査官、窓辺太郎はさえないヒラ調査官で、ニックネームが「窓際」と呼ばれるのですが、
事件が起きるとその持ち前の正義感で、勧善懲悪ぶりを発揮して楽しませてくれます。
税務調査官と題材にした映画といえば、「マルサの女」。
これが一番でしょう。
およそ28年も前の映画ですが、今見てもとても面白い。
伊丹十三監督作品はしっかりとした取材に基づき作られているため、かなりリアリティがあります。
もっとも宮本信子さんが演じる主人公はありえないキャラクターです(笑)。
そこがコミカルで楽しいのですが。
さて
今回は税務調査の話題を少しお話しいたしますね。
いま6月は税務調査官の異動の時期です。
公務員の異動は通常は3月なのになぜ?
それには訳があります。
個人の確定申告が3月、法人の確定申告のピークが5月。
それが落ち着いてから・・・移動となるのです。
7月ごろまでは引き継ぎを終え、いよいよ調査チームを結成して、どこに調査へ行くか決まります。
申告データはスーパーコンピューターにより管理され、イレギュラー情報ははじかれます。
そして秋から年末までが税務調査の季節。
税務署から会社に電話がかかってきます。
「○○税務署です。今度税務調査に伺いたいのですが・・・」
皆さんは、このセリフ聞いていかがですか。
血の気が引きますか、脂汗かきますか?
私は税理士ですが、やっぱりドキドキします。
税理士仲間には喜ぶご仁もいるようですが(苦笑)。
しかし税務調査は通常は任意調査といって、事前に通知があり日程も交渉できますから
そこは安心です。
税務調査は、あくまで調査なので何もなければ「是認(ぜにん)」といって追徴がない場合もあります。
いわゆる勘違い、ミスで追徴が出る場合もあります。
「見解の相違で」といって修正申告に応じることもあります。
しかし、悪質な仮装・隠ぺいがあったりすると、罰金である「重加算税」が課されます。
だから新聞などに税務調査の記事が載ったら、追徴額ではなく、重加算税の額をチェックすると興味深いですね。
「マルサ」は国税局査察部のことで、悪質な脱税、巨額の脱税を摘発する部署ですから、予告なしで来るんです。
会社に入ってきていきなり、
「動くな~」
やっぱり怖いです。
税理士はそんな怖い思いをしないための用心棒みたいなもの。
あ、税務署とケンカするわけではないですから誤解しないでくださいね。
普段からお帳面を見て、税務上の問題はないか、しっかりチェックしています。
備えあれば憂いなし。
あなたとあなたの会社をしっかりと守ります。
「マルサの女」をみて、怖い!
そう思った方は信頼のおける税理士と日ごろからお付き合いくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年6月17日
小規模事業共済をつかっていますか?
小規模事業共済って知っていますか?
漢字ばかりで、なじめんわ、と思われるかもしれません。
実はこれ、小さい事業主さんには喜ばれるものがいっぱいありますので要チェックなんです。
まず、制度を一言でいうと
国がつくった「経営者の退職金制度」
なんです。
個人商店などでやっている事業を思い浮かべましょう。
八百屋さん(今でいうと街中にある食品スーパー)や、コンビニなどが分かりやすいかもしれません。
個人でお商売をしていて、
ご主人と奥さんで頑張っていて、
近くに住むパートさんやアルバイトさんを雇って・・・
そうすると毎日が大変で、老後の蓄えは貯金と国民年金、そして生命保険でなんとかというところ。
利息も低く、国民年金も満額で年80万ちょっとの、このご時世。
将来を思えば大変心細いでしょう。
『ウチにも大企業みたいに退職金があればな~』
そう思うのもよ~く分かります。
そんなときにこそ、小規模事業共済がぴったりです。
メリットは3つあります。
ひとつめ。支払ったときに節税できます。
掛け金が税金計算上、所得控除になるので支払う税金が少なくなります!
ふたつめ。もらう時に節税できます。
満期になった時、もらい方が全額もらうか、分割して毎年もらうかを選択できます。
もし全額もらった場合は、退職金控除を使って節税できます。
分割してもらった場合は、もらった分がその時の雑所得として取り扱われるので、税率も低く節税になります。
みっつめ。資金繰りに困った時に助かります。
事業をしていると資金繰りに困るときは必ずあります。
銀行は傘がいるときに傘を貸してくれる、わけではありませんね。
でも小規模事業共済に加入していると支払った掛け金の範囲ではありますが、すぐ貸し出しに応じてくれます。
それ以外にもまだあります。
今までは、小規模事業者が対象だったので、法人になると加入できませんでした。
しかし、最近制度変更があって法人成りになった場合だと、役員さんはそのままで継続することができることになったんです。
役員を辞めるときに退職金としてもらえちゃう。
助かります。
個人事業主さんの応援も私たち税理士の仕事です。
もちろん、事業が大きくなって法人成りするときもお手伝いしています。
確定申告の税金計算だけではありません。
ぜひ活用してくださいね。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年6月4日
新設法人の消費税、2年間は免税と言われていますが、そうではありません!
消費税には落とし穴がいっぱいあります。
今回はその一つをご紹介します。
消費税はどんなときに支払うのでしょうか?
はい、モノを買った時ですね。
では税務署に消費税を支払うのは誰でしょう?
消費者?
いえ、違います。
お商売をしている事業主様や会社が支払うのです。
ここで、売上で預かった消費税と、経費で支払った消費税の差額を計算して納めることになっています。
しかし、事業主様や法人でも納めなくてもいい人たちがいます。
これを免税事業者と言っています。
免税事業者は、2年前の売上が1,000万以下の方です。
今年の、ではありませんからね。
売上が1,000万もないのは規模が小さいので、消費税計算はおまけしておきますね、そういうことです。
一般的に
『お商売を始めて2年間は消費税を支払わなくてもいいよ』
と言われているのはこのためです。
しかし、消費税がかかる例外もあるので要注意。
資本金が設立当時に1,000万円を超える会社は最初から消費税を納めることになっています。
それから、個人で事業を営んでいて、会社にした方(法人成りと言います)や
法人から分社の形で新しく会社を作った方も要注意です。
1年目の半期の売上が1,000万円を超えると、2年目から消費税を納めなければなりません。
こうした経緯の会社は、もともと収益力があるため、税金が課されるようになっているのです。
意外と皆さんご存知ないようです。
しかし例外的に、売上が1,000万円を超えていても、人件費が1,000万円より少なければ免税事業者で構わないとされています。
粗利が少ない卸売業などが該当するのですが、
売上がそこそこあっても、原価の占める割合が高く、利益が出ない商いだとお給料は少なくなります。
そういう時は『弱所保護の観点』から納税はされないことになっているのですね。
大切なのは、事前に売上と役員報酬や給料の予算をしっかり組んでおくこと。
消費税を支払ってでもお給料を会社からもらうのか、
消費税を支払わないようにお給料を決めるのか、
消費税を支払って法人税を抑えるのか、
などいろいろなパターンが考えられます。
法人成りを考えている事業主様、要注意です。
信頼のおける税理士さんに相談して、しっかりシュミレーションをしておきましょう。
税金を払い過ぎないようにしてくださいね!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年5月16日
賃上げ、新採用の会社さん、減税になります。忘れないで!
最近の新聞に『トヨタ自動車、純利益が2兆円超』との見出しが出ていました。
すごいですね!国家の税金歳入がおよそ50兆円ですからその25分の1ですよ。
利益が出たら、もちろんお給料も上げないと!
賃上げも政府主導で大手企業から始まっています。
もちろん税制も賃上げをする企業をあと押ししていますよ。
主なものは二つあります。
所得拡大促進税制と、雇用促進税制
と呼ばれるものです。
所得拡大促進税制は、前年より従業員への給料を増額したら、中小企業ならその増加分の10%の税金控除となります。
例えば、昨年の従業員へのお給料が総額で1億円だったとしましょう。
今年は1億500万円になりました。500万円の増額です。
そうすると500万×10%=50万円の税金が節税になります。
雇用促進税制は、前年より従業員数を増やしたら、増やした人員につき一人あたり40万円の税額控除となります。
例えば、昨年より3人従業員増やして新たに雇ったとすると、
40万円×3人=120万円の税金が節税になります。
要するに
給料を増やしたら…所得拡大促進税制。
人を増やしたら…雇用促進税制。
を使ってくださいということです。
雇用を増やせば、給料も増える、だから両方とも使えるんじゃない?
そんな疑問点、ごもっともです。
ただ注意する点ふたつあります。
まずは一つ目。
実はこの税制は、どちらか有利な方だけ選択して使うことになっているのです。
だから有利判定をして、どちらかしか使えません。
残念ながら「一粒で2度おいしい」とはならないのでした。
注意点の二つ目。
雇用促進税制を使いたい場合は、あらかじめ雇用促進計画をハローワークに出しておかないといけないのです。
出しておかなければいけないのは前期の決算申告期限まで、
つまり、今期の最初の2ヶ月以内に提出しておく必要があるのです。
後になってでは遅い!
転ばぬ先の杖なので要注意です。
それから、新設法人であっても所得拡大促進税制は使えることになっています。
前年度は営業活動をしていないわけですから、新設法人ならほぼ100%対象になってきます。
ありがたいですね~
人を採用したい、お給料を増やしたい、
そう思った社長様、まずは税理士に事前に相談してくださいね。
いろいろと条件や上限額も付いているので、専門家に尋ねて活用していただければ大きく税金が減ると思いますよ!
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!
2015年5月1日
固定資産税が上がってる!?払い過ぎにはご注意を。
区役所からわが家のマンションの固定資産税の通知が来ました。
皆さんのところにも届いていることでしょう。
中身をじっくり見ました?
私は…見ましたとも!だって専門家ですから!
「去年よりも上がってる~!?」
名古屋市では3年おきに不動産評価の見直しを行っており、
今年はその評価替えで土地の価格が上がったのです。
うん納得。
しかし少し前に話題になったニュースが頭をよぎります。
去年の6月ごろです。
埼玉県の新座市で、老夫婦がお金の都合をつけるために自宅を売ったら、なんと27年間も固定資産税を払い過ぎた事実が判明しました。
しかし払い過ぎた税金は全部が戻らないと分かったというニュースです。
新座市ではこの事件をもとに知らべたら、なんと8億円も市民に返還しなければならないほど誤りがあったのです。
驚きです。でも極端な例ではあります。
税理士さんは何やっているんだ~。
固定資産税については、正直に申します。
実は私たち税理士も明るいわけではありません。
というのもわが国では申告課税方式と賦課課税方式の2種類で納税しています。
申告課税方式は、自分たちで計算をして、税額を計算して納めます。
税理士は会社や事業を営む方の申告をお手伝いをしているのです。
賦課課税方式は、役所がこれだけ納めてくださいね、と通知が来て納めます。
税理士はここに直接関係はしていないのです。
言い訳っぽいですが、普段あまり接する機会がない・・・。
とはいえ、新座市のニュースは非常にセンセーショナルですね。
誤って税金を請求したケースは総務省の発表によると0.2%。
およそ500件に1件の割合だそうです。
多いのか、少ないのか。
それは皆さんのご判断に任せます(苦笑)。
払い過ぎは困ります。
なぜこんなことが起きるのか。
最近こそITが普及し情報管理がしっかりしていますが、
少し前までは担当者からの申し送りで紙の資料で管理をしていました。
市町村合併などもあり、前任者の前任者までさかのぼっていき正誤を確かめるということは困難です。
また、相続があると
名義の変更、住まなくなったり、立て壊したり、新たに建て替えたり
などがあるため評価が変わってくる可能性があります。
通知が来たら、ぜひご確認ください。
まず税金がかかる不動産の名義、対象物は合っていますか。
面積は正しいですか、地目はどうなっていますか。
そしてその用途は合っていますか。
意外かもしれませんが、税の世界では基本思想は「弱者保護」です。
したがって実際住んでいる家と、ただ所有している家では税金は違います。
もちろん住んでいる家の方が安くなります。
小規模宅地の特例といって税金が軽減されているのです。
新座市のケースもこちらだったようです。
ですがこちらから直してね、と申告しないとそのまま放置されちゃいます。
「おやっ?」
そう思ったら、信頼のける税理士に相談してみてくださいね。
一緒に調べてくれたり、アドバイスをくれると思いますよ。
名古屋発!税理士アニキの感動!笑売
は毎月1日、15日に更新しています。お楽しみに!!